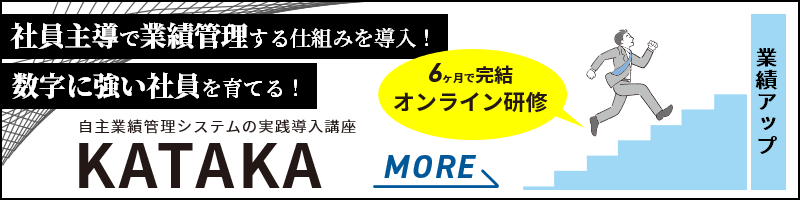事業計画の立て方・作り方を解説!ヤマチの事例と重要なポイントも紹介
業績管理・経営計画


こんにちは、ヤマチユナイテッドの石崎です。
経営方針に沿って社員一人ひとりに行動してもらうため、必要になってくるのが事業計画。
ヤマチユナイテッドでは、事業計画をかなり重要視しています。
とはいえ、「そもそも事業計画を作っていない」「数字だけの計画に終始してしまっている」という会社も少なくありません。
しかし、事業計画は業績アップにつながる大切な計画です。
特に、業績の伸び悩みを感じている中小企業の経営者の方にとっては、ぜひ事業計画を作ってみることをおすすめします。
そこで今回は、事業計画の立て方・作り方についてのお話です。
ヤマチユナイテッドが事業計画を立てる際の流れと、実際の作り方もご紹介します。
あわせて、事業計画と経営計画の違いや得られるメリット、事業計画を作成する際に重要なポイントも解説しますので、ぜひご確認ください。
目次
- 事業計画とは?経営計画との違いや得られるメリットから確認
- 事業計画の立て方・作り方は?事業計画書に含める内容もご紹介
- 【事例】ヤマチが事業計画を立てる際の流れは?実際の作り方もご紹介
- 業績アップにつながる事業計画を作るために重要な10のポイントと注意点
- 事業計画の立て方・作り方の流れやポイントを押さえて、業績アップにつなげよう
事業計画とは?経営計画との違いや得られるメリットから確認
「事業計画」とは、名前のとおり事業を運用していくために必要なプランを整理・分析し、計画していくものです。
自社の既存事業におけるサービスや事業内容についてはもちろん、新しいビジネスのコンセプト、市場調査、売上や経費といった事業収益の提示、マーケティング方法などについても記載し、「どのように実行していくべきか」を明確にします。
要は、計画した事業内容を実現するための具体的なフローを作成するのが、事業計画なのです。
このフローを、社員全員がわかりやすい形で簡潔に文書化したものを「事業計画書」と呼びます。
一般的には、経営者や事業責任者が事業計画を作ることが多いですが、ヤマチユナイテッドでは、幹部や社員を巻き込みながら、みんなで考えてもらったものを形にしていきます。
もちろん事業計画そのものも重要ですが、私たちは「作り上げるまでのプロセス」を非常に重要視しています。
自分たちで意見を出し合って作った事業計画には納得感があり、その後の業務にも自主的に取り組みやすくなるからです。
事業計画と経営計画の違い
現状から目標へと至るまでの筋道として存在するのが「経営計画」。
一方、経営計画の目標を達成するために、一つひとつの手順をどう実現させていくかを具体的に示すのが「事業計画」です。
例えるなら、経営計画という「地図」であり、事業計画という「目的地までのルート」の2つが揃って、はじめて事業を前に進めることができます。
目標を達成したなら、次はさらに上を目指すために。
未達成ならやり方を見直して、課題をクリアするためにも、事業計画は必要なのです。
また、新規事業を立ち上げる際に重要になる計画として、「投資回収計画」もあります。
詳しくは、「投資回収計画とは?収支計画との違いや計画を立てる際のポイントも」でご紹介しています。
さらに、ヤマチユナイテッドでは、事業部内に複数存在する部門それぞれが効果的かつ有機的に機能するように「部門方針書」も導入しています。
部門方針書とは?例文とともに作り方や効果的な活用方法を解説!
興味のある方はぜひあわせてご覧ください。
事業計画を立てる目的・得られるメリットも知ろう
事業計画を立てる目的は多岐にわたりますが、事業の方向性を明確にし、関係者と目標を共有することが挙げられます。
計画を言語化することで、自社の戦略や課題を整理でき、行動に一貫性が生まれます。
また、社内での情報共有がスムーズになり、業務効率やモチベーションの向上にもつながるでしょう。
事業計画を作ることで得られるメリットについても、詳しく見ていきましょう。
メリット①思考の整理とアイデアの可視化
計画を文章にまとめることで、頭の中にある構想や戦略を整理できます。
言語化する過程で考えが深まり、新たな視点やアイデアが生まれることもあるでしょう。
事業計画を立てることは、漠然としたビジョンを明確にする第一歩になるのです。
メリット②方向性を共有し、業績アップ
事業計画書は、関係者との認識をそろえるツールとしても機能します。
事業計画を作ることにより、仕事の目的、方向性が共有されることで、チームの連携が強まります。
その結果として、社員のモチベーションが上がれば、業績アップにもつながると思いませんか?
業績アップだけでなく、主体的に働く社員がより増えてリーダーシップをとれる人材が育つなど、会社に大きなメリットをもたらすでしょう。
例えば、「昨年これだけの利益があったから、来期はこのぐらいを目標に」と考える企業は多いかもしれません。
しかし、会社としてどんな方向へ向かうのか、社員は普段何を目指して仕事をするのか、という目的の共有がない状態でただ利益を追求しても、達成か未達成かという結果が残るだけ。
これでは手応えもやりがいもないものになってしまうため、明確な事業計画書を示すことは大変有効です。
メリット③自社の強みや弱みを客観的に把握できる
事業計画を作っていく中で、目標を達成するための方法を考えることで、自社の強みや弱みなどが明確になるというメリットもあります。
また、自社や自分の事業、競合他社の状況を客観的に見つめ直すことによって、新しい事業につながるアイデアが生まれる可能性もあるでしょう。
現在の事業についても、新しい切り口から顧客を開拓できるようになるなど、業績アップにつながる可能性があります。
メリット④資金調達時の提案として有効
今回のコラムでご紹介するのは、主に社内での生産性や業績を上げるための事業計画ですが、事業計画書は資金調達のために対外的に活用されるケースもあります。
例えば、銀行やベンチャーキャピタルなどに融資や投資を求める際には、事業の概要や将来性、魅力をわかりやすく伝えるための資料として、事業計画書を提出します。
この場合、資金調達ができるかどうかは、事業計画書の良し悪しにかかっています。
想定顧客、ビジョン、ビジネスモデル、提供価値、市場規模、ニーズ検証の結果、競争優位性、マーケティング戦略などの項目を盛り込み、しっかり魅力を伝えることが大切です。
事業計画の立て方・作り方は?事業計画書に含める内容もご紹介

一般的な企業でとても多いのは、事業計画の中身や根拠、理由も全部社長の頭の中にしかないというケース。
決算期末か期初の1〜2週間で書類を作って「このように進めてほしい」と指示が出されることも少なくありません。
しかし、この方法だと、部下からしてみると上から降ってくる計画なので身が入らなかったり、意図が十分に伝わってこなかったりという可能性もあるでしょう。
そのままでは非常にもったいないですよね。
ここでは、事業計画の立て方・作り方について、流れに沿ってご紹介していきます。
事業計画の立て方・作り方の流れ
一般的な事業計画の立て方・作り方のステップを見ていきましょう。
1. 環境分析を行う
事業を取り巻く「外部環境(政治・経済・競合など)」と「内部環境(人材・財務・設備など)」を把握します。
自社の強み・弱みを整理する際には、SWOT分析を活用すると効果的です。
2. 目標を設定する
分析結果をもとに、将来の目指す姿を明確にします。
売上などの具体的な数値目標を立て、現状とのギャップを把握し、解決すべき課題を挙げましょう。
3. 課題解決の計画を立てる
目標達成に必要な行動計画を作成します。
大きな課題は細分化し、具体的なアクションや数値目標を設定すると実行しやすくなります。
4. 実行と見直しを繰り返す
計画を実行し、定期的に進捗をチェック・評価します。
必要に応じて内容を修正し、継続的に改善を重ねることが成果につながります。
事業計画書に含める内容
事業計画書には、以下の要素を盛り込むことが望ましいです。
- 企業・事業概要:会社情報、事業内容、ビジョン・ミッションなど
- 従業員状況:現在の人員、将来的な採用計画
- 市場・競合環境:競合分析、市場規模、顧客層の特徴
- 自社の強み・弱み:SWOT分析の結果、課題と改善策
- 商品・サービスの特徴:提供する価値、差別化ポイント
- 販売戦略・ビジネスモデル:流通経路、プロモーション方法、利益の仕組み
- 組織体制・人員計画:役割分担、組織図、必要な人材の配置や育成計画
- 財務計画:売上予測、利益計画、資金繰りや資金調達の計画
順序立てて取り組み、関係者と共有しながら柔軟に見直していくことで、現実的かつ実行可能な事業計画を完成させることができます。
【事例】ヤマチが事業計画を立てる際の流れは?実際の作り方もご紹介
ヤマチユナイテッドの事業計画を作る際の流れと、実際の作り方をご紹介していきます。
事業計画の立て方・作り方①会社のビジョンを明確にする
まず、明確にすべきは「ビジョン」です。
事業計画を作るにあたって、全員が同じ方向を向いて進むためにも、お互いの価値観を共通のものとした上で方針をすり合わせていく必要があります。
経営者をはじめ、幹部が同じ志を持って取り組むことで、社員にとっての良い見本となります。
「将来的にこうなりたい」という会社の理想像を具体的に思い描いてください。
どのくらい先かというと、3年、5年、7年、10年のように、期間で区切って考えるのが一般的ですが、3年後、5年後あたりがリアルにイメージしやすいと思います。
ヤマチユナイテッドでは、最初に今後3年間の中長期ビジョンを設定することからスタートしています。
事業計画の立て方・作り方②中長期的な経営計画を決める
ビジョンが定まったら、それを実現するための中長期的な経営方針を策定。
この経営方針に基づいて、より具体的な経営計画を作成します。
その上で、経営計画から逆算して作る単年度の計画が、事業計画というわけです。
中長期計画の作り方のポイントや、経営計画発表会の目的については、こちらのコラムもぜひご参照ください。
中長期経営計画の作り方は?会社の未来に筋道を引く方法とヤマチの事例
経営計画発表会の目的とは?成功ポイントや見逃せないメリットも
事業計画の立て方・作り方③事業計画の案を何度も議論する
ここからは、社員も巻き込んで決めていく段階に入ります。
そのため、事業計画の完成までには約半年と長い時間がかかります。
ヤマチユナイテッドでは、当初立てた事業計画に対し現状把握・要因分析・重点課題の振り返りを行います。
そして振り返りを元に、次年度のテーマ・方向性や、方策(対策や測定可能な指標)を考えています。
3月の年度スタートに向けて、9月あたりから決算予測に着手し、同時に「次の期はどう進めていこうか」という議論も始まります。
こういった会議は1度だけでなく、何度も場を設けて煮詰めていきます。
なぜかというと、幹部から各事業部の責任者、マネージャー、リーダー、そして現場の社員.まで下ろしていくことで、全員にとことん考えてもらいたいからです。
各事業部、各部門で「どうすれば営業利益や生産性を上げられるか」といったテーマを、自分たちで考えるプロセスが、事業計画作成において大切なのです。
事業計画の立て方・作り方④案を持ち寄って修正する
事業計画を社員に考えさせるとはいっても、何でもはじめから自由に考えさせて、そのままOKを出して、その通りにさせるということではありません。
取りまとめた案を持ち寄って議論を重ね、見直すべきところや足りないところがあれば「またみんなで考えよう」と下へ戻します。
修正案が上がってくれば、再度フィードバックを行い、繰り返すことで改善していきます。
社員とこのようなやりとりをするには、日頃から教育的指導をしたり、時には厳しくフィードバックをしたりしながら、時間をかけてコミュニケーションを取る必要があります。
意見のキャッチボールができるようになれば下地はOKです。
時間はかかりますが、現場の一人ひとりに考えさせることが社員の育成につながります。
なお、事業計画とあわせて採用計画・育成計画を立てることも重要です。
詳しくは下記コラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください。
採用計画・育成計画の立て方とは?経営計画と紐づけるポイントも確認
業績アップにつながる事業計画を作るために重要な10のポイントと注意点
業績アップや組織の成長につながる事業計画を作るためには、現実的かつ実行可能な考え方や視点を押さえておく必要があります。
ここでは、ヤマチユナイテッドの事例も交えながら、事業計画を作成する際に重要な10のポイントと注意点をご紹介します。
計画づくりで悩んでいる方や、見直しをしたい方のヒントになれば幸いです。
1. 事業計画は「自分たちのため」のもの
銀行から融資を受けるときなど、対外的な目的で計画書を作成することもありますが、みなさんが作るべきは会社のため、自分たちのための事業計画であるということです。
社内文書なので、会社や事業内容によって盛り込まれる項目は異なっていて当然といえるでしょう。
なお、成功を目指すためには、売上高や事業拡大の時期など、具体的な数値や期限を含んだ目標を立てることが必要です。
しかし、達成困難な目標は、経営資源の浪費や従業員の意欲低下を招く可能性もあるため、事業環境や市場状況、自社のリソースを踏まえた上で、実現可能な範囲で設定することが重要。
ちなみにヤマチユナイテッドの場合は、売上、粗利、粗利率、人件費、他経費、経費計、営業利益、生産性人数、組織人数、生産性などの項目で数値目標を立てます。
他にも、組織のあり方、商品・サービスの販売手法、労務環境など、数字以外の項目も入った計画書になっています。
2. 社員全員でビジョンを共有することが大切
業績が上がる事業計画を作るには、社長以下の社員全員が価値観と目指す方向性を共有していることがポイントです。
例えば、「3年後にはこんな会社にしたい。そのために、できることをみんなも考えてほしい」というように、思い描いたビジョンをどんどん幹部以下へ、上から順番にすり合わせながら下ろしていってください。
とはいえ、現場から率直な声が上がってくるまでには、ある程度の時間がかかるかもしれません。
そのため、普段から社員同士のコミュニケーションを密にして、発言しやすい雰囲気を作っておくことも大切です。
ビジョンは「作る」だけではなく、社内に「浸透させる」ことがカギになります。
詳しくは下記コラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください。
ビジョンとは?会社も社員も前向きになれるビジョンの作成方法と事例を紹介
なぜビジョンが浸透しない?企業ビジョンの重要性とヤマチの成功事例
3. トップダウン重視を捨てられるかがカギ
現状、トップダウンで経営を進めている方は「社員を巻き込む」という経営方針に転向できるかどうかが、事業計画の成否を分けるポイントになるかもしれません。
トップダウン自体がダメというわけではありませんが、ボトムアップやミドルマネジメントの併用によって、より実効性のある計画づくりが可能になります。
当社のような事業計画の作り方を取り入れるには、経営方針の柔軟な見直しも必要です。
トップダウンかボトムアップかで悩んでいる方は、「会社の意思決定。人や組織が動くのはトップダウンよりボトムアップ?」も、ご参考ください。
経営者の意思を伝えつつ、社員が主体的に働ける会社にするために必要な仕組みについて紹介しています。
4. 経営数字をオープンに
経営者の方にとって高いハードルと思われるのが、社内で経理上の数字をオープンにできるかどうかということ。
しかし、社員に事業計画を考えさせるにあたっては予算の計上にも関わりますから、会社の経済状況の情報は不可欠です。
経営者の中には、利益が出ていても出ていなくても、数字を社員にオープンにする勇気が出ないという方も多いように思います。
理由は「あまり儲かっていないから」「部門間で収益の差がありすぎてそれぞれに気を遣って出しづらい」「安心してぬるま湯に浸かるんじゃないか」など、さまざまです。
しかし、経営数字を隠したままでは社員が現状を正確に把握できませんから、先述したような方法は一切機能しないままです。
勇気をもって経営数字をオープンにしてこそ、業績アップにつながる事業計画を作ることができるのです。
5. 計画書の構成と内容の明確化
事業計画書は、意思決定者が素早く理解できる構成にすることが大切です。
表紙や概要ページを設けるほか、内容は具体的かつ論理的に記載し、客観的なデータやスケジュールを用いて説明しましょう。
これにより、計画の信頼性と説得力が高まります。
6. 新規事業の意義と根拠の提示
特に新規事業においては、「なぜ今、この事業に取り組むのか」「社会的・市場的価値があるのか」を明確に示すことが重要です。
また、参入市場の規模や顧客の需要、競合との差別化ポイントなど、事業の成功可能性を裏付ける根拠を示すことで、社内外の理解と共感を得やすくなります。
7. 顧客ニーズの的確な把握
事業計画を練る上で、顧客が何を求め、どんな課題を抱えているかを正確に捉えることは欠かせません。
アンケート、インタビュー、既存顧客の分析を通じて顧客の声を反映させることで、市場に受け入れられる商品・サービスの開発につながります。
8. 競合分析と自社の強みの活用
市場での立ち位置を理解するために、競合他社の戦略、製品、価格設定などを分析し、自社との違いや優位点を明確にします。
技術力、特許、サービス品質など自社の強みを最大限に活かす戦略を計画に組み込むことで、競争力のある事業運営が実現します。
9. 数値計画の現実性とリスク管理
売上、コスト、利益の予測は、過去のデータや市場動向に基づき、無理のない範囲で策定しましょう。
また、市場変動や資金繰りなどのリスクに備え、具体的な対策を盛り込むことで、不測の事態にも柔軟に対応可能な計画となります。
10. 第三者の意見を取り入れる
計画作成の過程では、専門家、業界関係者、顧客の意見を積極的に取り入れ、思い込みによる視野の偏りを防ぎ、改善点に気づきやすくなります。
多角的な視点を取り入れることで、より現実的で実現性の高い事業計画に仕上がります。
事業計画の立て方・作り方の流れやポイントを押さえて、業績アップにつなげよう
事業計画とは、事業を運用するために必要なプランを分析し、計画するものです。
事業計画を作ることで、会社の方向性が共有でき、自分の事業を客観的に見直すきっかけにもなるため、業績アップにつながる可能性があります。
事業計画には新規事業における市場調査、収益予測、マーケティング戦略などの要素を盛り込むのが一般的です。
経営計画が企業全体の目標設定であるのに対し、事業計画は目標達成のための具体的な手段やステップを示すものといえます。
計画作成には、環境分析、目標設定、課題解決策の立案、進捗の見直しといったプロセスも欠かせません。
また、社員全員が参加し、意見を出し合いながら事業計画を作成することで、現場の声が反映されやすくなり、実行力の高い計画に仕上がります。
事業計画を言語化することで、社内で方向性が共有されるだけでなく、社員のモチベーション向上や業績アップにつながります。
さらに、資金調達時には計画書が外部への説得材料としても有効に機能します。
事業計画を成功させるには、現実的な数値目標の設定、競合分析、リスク管理、第三者の意見を取り入れるといった視点も大切です。
ヤマチユナイテッドでは、実際に社員研修の現場をお見せしている視察ツアーや、経営セミナー・イベントを随時開催しています。
気になる方はぜひチェックしてみてください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員
石崎 貴秀
1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。
連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。
入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。