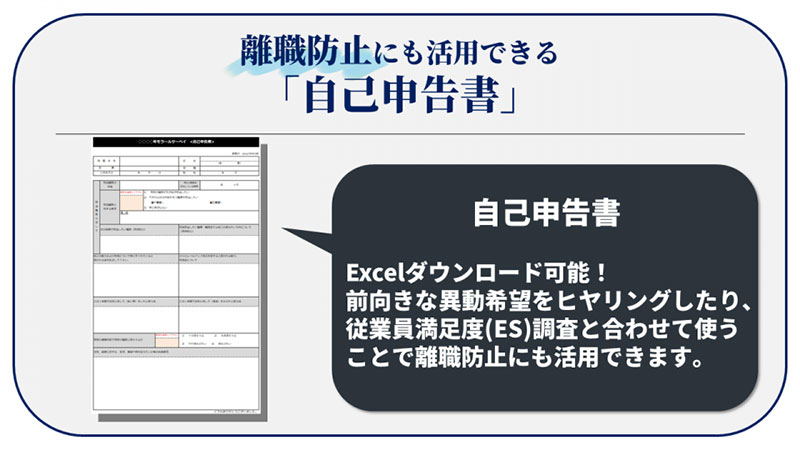自己申告書とは?社員と信頼を築く会社制度をご紹介!ヤマチの事例も
採用・育成


こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。
「社員が何を考えているのかわからない」「本音を言ってくれない」と感じている経営者の方は多いのではないでしょうか。
日々の業務に追われる中で、一人ひとりの社員としっかり向き合う時間を確保するのは、決して簡単なことではありません。
そこで今回は、社員の本音を把握し、信頼関係を築くための具体的な手法として「自己申告書」制度をご紹介します。
制度の目的や導入によるメリット、ヤマチユナイテッドの実際の運用事例まで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
自己申告書とは?自己申告制度の目的も確認
自己申告書・自己申告制度とは、社員が自分の現在の気持ちやキャリア希望、悩みなどを定期的に書いて会社に提出する制度です。
この制度は、会社が社員を一方的に評価するのではなく、社員からの発信を受け止める重要な機会となります。
自己申告書では、異動希望とその理由、将来のキャリア志向、自己分析、体調面、改善提案や自由意見などを聞きます。
前向きな意見だけでなく、現在抱えている悩みや不満についても率直に記入してもらうことで、組織の課題を早期に発見できるのです。
自己申告書の本来の目的
自己申告書制度には、主に3つの目的があります。
1. 社員の内面やモヤモヤを可視化する
普段の業務では表面化しにくい本音や不安を把握できます。
2. 組織の状態を早期に把握し、対話の起点を作る
離職の兆候や職場の問題を早期に察知し、適切な対応を取ることができます。
3. 上司との面談や人事判断の参考材料として活用する
客観的な情報に基づいた人事運営が可能になります。
ヤマチユナイテッドの自己申告書フォーマット
ヤマチユナイテッドでは、実際に以下のような項目で自己申告書を実施しています。
【自己申告書の主な項目】
- 担当職務の内容・期間
- 担当職務に対する希望(継続希望/異動希望/特になし)
- 異動希望の第一希望・第二希望
- 次の段階で担当したい職務
- 将来担当したい職種・職務、または自己の進みたい方向
- 自己の能力および性格について、特に優れていると思われる面
- さらにレベルアップ・改善を要すると思われる能力・性格面
- この1年間で会社に対して「良い事」をしたと思う点
- この1年間で会社に対して「迷惑をかけた」と思う点
- 現在の健康状態で現在の職務に堪えうるか(4段階評価)
- 会社・経営に対する要望、提案、何を変えたいかなどの自由意見
これらの項目は、担当職務に関する基本情報から始まり、将来のキャリア志向、自己分析、体調面まで幅広くカバーしています。
特に、健康状態の4段階評価(十分堪えうる~堪えがたい)では、ストレスチェックでは見えにくい心身の変化を捉えるきっかけにもなっています。
また、「この1年間で会社に対して『良い事』をしたと思う点」「『迷惑をかけた』と思う点」を振り返ってもらうことで、本人の業務や影響を棚卸しして把握し、さらには自己評価と会社の評価のギャップを把握できます。
最後の自由意見欄は、組織の課題や改善点を発見し、経営計画に反映させるための重要な情報源となっています。
ヤマチユナイテッドの自己申告書フォーマットは、こちらのページからダウンロード可能です。
自己申告書を導入するメリット・デメリット

自己申告書制度の導入を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解しておくことが重要です。
成功のカギは、「書かせる制度」ではなく、「対話と信頼の制度」として運用できるかどうかにあります。
自己申告書を導入して企業が得られるメリット
経営側から見ると、自己申告書は組織運営の重要な情報源となります。
離職前の兆候を察知できる
離職の兆候は、多くの場合、退職願が出される前から現れます。
例えば、自己申告書で「最近やりがいを感じにくい」「将来に不安を感じる」といった心情の吐露や、体調面で「やや耐えがたい」「耐えがたい」といった記述が見られることも。
これらは、離職の予兆を示すサインとして、早期に気づくきっかけになります。
逆に「特にない」といった無気力な状態も、実は離職の前兆かもしれません。
これらの兆候を早めに把握できると、早期に対策を講じることができます。
離職を防ぐ取り組みには、職場環境や仕組みも重要です。
こちらのコラムで詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
⼈が辞めない職場を作るには?離職を防ぐ職場作りのポイントや事例も紹介
社員のキャリア志向や配置希望を把握できる
「将来的に事業責任者をやりたい」「新規事業に関わりたい」「マネージャーになりたい」といった前向きな希望から、「今のままでいい」という現状維持志向まで、社員の持つ具体的な希望を把握できます。
これにより、適材適所の人材配置や育成計画の策定が可能になります。
職場環境・組織風土の改善に役立つ生の声が拾える
自由意見欄からは、日常業務では気づきにくい現場の問題を具体的に把握できます。
例えば、「チーム内のコミュニケーションが不足している」「業務量が偏っている」といった現場の実情を知ることで、組織改善に向けた具体的な施策を検討できます。
これらの情報は、組織改善の貴重な材料です。
社員が得られるメリット
社員の立場から見ると、自己申告書は自分の想いを伝える重要な手段の一つです。
普段の業務では表現しにくい本音や希望を文章で整理して伝えることができ、組織への参画意識を高める効果も期待できます。
意見を聞いてもらえるという安心感がある
自己申告書の内容に対して会社が真摯に対応することで、社員は「会社が自分を見てくれている」「意見を聞いてくれている」という安心感を得られます。
適切なフィードバックを受けることで、「会社に大切にされている」という実感を得られ、従業員満足度の向上にも直結します。
従業員満足度については、こちらのコラムもご覧ください。
従業員満足度(ES)調査の目的とは?質問項目や分析方法を解説
キャリアを言語化するきっかけになる
自己申告書を書く過程で、「この1年間で頑張ったこと」「まだ足りないと思うところ」「将来なりたい姿」を、自身でも整理できます。
普段は忙しくて考える時間がない中で、自己分析の機会となり、自身のキャリア形成の第一歩となります。
上司との面談やフィードバックのベースになる
自己申告書で整理された内容を基に、具体的で建設的な面談を行うことができます。
例えば、「発言力やリーダーシップを身につけたい」「人前で話すのが苦手」といった記載があれば、今後の成長に向けた具体的なアドバイスが準備できるでしょう。
自己申告書導入時のデメリットと注意点
一方で、自己申告書が適切に運用されない場合は、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
活用されないと不信感につながる
特に避けたいのが、せっかく提出してもらった内容を放置することです。
社員が「伝えても何も変わらない」「聞いてくれない」と感じてしまうと、かえって会社への不信感が高まります。
「形だけの制度」として認識され、会社への信頼を損なう結果となってしまうでしょう。
正直に書きづらい風土だと形骸化する
「会社にどう見られるか」を気にして本音を書けない職場環境では、制度が形骸化してしまいます。
特に直属上司との関係が悪い場合、その上司に自己申告書を見られることを恐れて、当たり障りのない内容しか書けません。
会社に対する信頼・信用がなければ、そもそも本音を書いてもらえないでしょう。
情報の開示範囲や共有範囲を事前に明確にしておくことが必要です。
目的が曖昧なまま導入すると効果がない
目的を明確にしないまま、なんとなく自己申告書を導入しても、社員側に「やらされ感」が生まれてしまい、本来の効果が期待できません。
経営参加の一環として位置づけるのか、人事運営の参考にするのか、自己分析の機会とするのかなど、明確な目的設定が必要です。
ヤマチユナイテッドの自己申告書活用事例
ヤマチユナイテッドでは、自己申告書制度を効果的に活用し、組織運営に大きな成果を上げています。
実際の事例を通して、制度をどのように活用しているか、効果的な運用方法をご紹介します。
部署を超えた異動事例
社員一人ひとりの希望に基づいた異動を実現し、キャリア形成や組織全体の活性化につなげた事例があります。
①営業からマーケティングへの転身
住宅営業で培った営業感覚を生かし、マーケティング部で営業支援を行なっている事例です。
現場の感覚を理解した上でのマーケティング施策により、大きな成果を上げています。
②工事管理から営業への挑戦
住宅の工事現場管理から営業部門への異動事例もあります。
建築における専門知識と接客スキルの組み合わせが、顧客の不安に寄り添った丁寧な営業スタイルを生み出しました。
③パートから正社員、そしてトップセールスへ
インテリアショップのパート社員が住宅営業への挑戦を希望し、正社員として営業部門に異動した事例です。
店舗で培った接客経験、コミュニケーション力を生かして、トップセールスに成長しました。
組織課題の発見と制度改善
ヤマチユナイテッドでは、自己申告書から得られた声を基に、制度の改善にも積極的に取り組んでいます。
改善事例をピックアップしてご紹介します。
- 資格取得補助制度の新設
- 各種手当の見直し
- 新入社員向け研修の充実と中途入社者向け研修の新設
- 人事評価制度の再構築
中でも特に大きなものは、人事評価制度の整備です。
評価制度はもちろんありましたが、「将来どうなったら給料が上がるかわからない」「昇進の基準が不透明」といった声が寄せられたのを機に、数年かけて人事評価制度を再構築しました。
現在も改善を続けており、社員が将来設計を描けるような制度作りを進めています。
記名式での運用と信頼関係の構築
ヤマチユナイテッドでは、あえて記名式で自己申告書を運用しています。
記名式にすることで、社員も責任を持って書く必要があることを周知し、意見を表明できる仕組みをつくるためです。
これは無責任な批判ではなく、建設的な意見や提案につながります。
また、「経営参加の一つとして、意見の参加をお願いしています」という位置づけで運用することで、社員の当事者意識を高めているのです。
この制度が機能する前提として、「申告すればちゃんと反映される」「真摯に受け止めてもらえる」という信頼関係があるからこそ、記名式でも本音を書いてくれるでしょう。
実施タイミングと経営計画への反映
ヤマチユナイテッドでは、経営計画策定の直前に自己申告書の提出を実施しています。
人事異動、組織変更、制度改善などに関する意見・要望を事前に把握し、それらを経営計画に反映させるためです。
自己申告書で得られた情報は、以下のように個人レベルから会社全体まで段階的に分析・活用されます。
- 個人レベルの課題や要望:必要に応じて個別の面談を実施(直属上司ではなく別の管理職が対応する場合も)
- チームレベルの課題:事業部内で対応し、改善に取り組む
- 会社全体の課題:経営計画に組み込まれる
【資料プレゼント】ヤマチユナイテッドが実際に使用している「自己申告書」フォーマットをぜひご活用ください!
自己申告書をこれから導入したい、フォーマットを参考にしたい方に向けて、ヤマチユナイテッドで実際に使用している自己申告書フォーマットを公開しています。
離職防止にも活用できるツールとして、ぜひ貴社の制度設計にお役立てください。
自己申告書とは、会社と社員の信頼関係を築くための重要な制度
自己申告書とは、単なる評価制度を超えた、会社と社員の信頼関係を築くための重要な仕組みです。
「社員が何を考えているのかわからない」という悩みを抱える経営者にとって、社員の本音を把握し、組織の課題を発見する有効な手段となります。
制度を成功させるためには、「書かせる制度」として形だけを整えるのではなく、「対話と信頼の制度」として運用できるかが大きな鍵となります。
ヤマチユナイテッドでは、記名式で自己申告書を運用しています。
社員が責任を持って記入し、それに対して会社が真摯に対応することで、「会社が自分を見てくれている」という安心感が生まれています。
自己申告書制度を通じて、離職防止、適材適所の配置、組織風土の改善など、さまざまな効果が期待できるでしょう。
ただし、自己申告書に書いてもらった内容を放置したり、目的が曖昧なまま制度を導入したりすると、逆効果になる可能性もあるため、導入にあたっては十分な準備と継続的な改善が必要です。
ヤマチユナイテッドでは、実際に使用している「自己申告書」フォーマットを公開しています。
こちらのページからダウンロードしていただき、お役に立てていただければ幸いです。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員
石崎 貴秀
1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。
連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。
入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。