新人育成で大切なことは?新人育成計画を立てるポイントや手順も確認
採用・育成


こんにちは、ヤマチユナイテッドの山崎です。
ヤマチユナイテッドにはHRD(Human Resourse Development)というグループ全体の採用と人材育成の役割を担う部署が存在します。
当社の新人教育の育成方法はOJTや外部のOff-JTだけでなく、企業理念への理解を深め、価値観を共有するための下地づくりにも時間を割くのが特徴。
さらに、決まったマニュアルに沿ったやり方ではなく、新人のうちから自分の頭で考えて行動させることに重点を置いており、それが実務にも役立っています。
今回は当社での実例を挙げながら、新人教育で大切なことや心構え、新人育成の手順などについて、考え方やポイントをお伝えしたいと思います。
目次
新人育成で大切なことは?持っておくべき心構えを確認
当社が新人育成で大切にしていることや心構えについてご紹介します。
新人育成で大切なこと①新人育成は入社前からスタート!
新人育成というと、入社後にスタートするイメージがありませんか?
実は新人育成は入社前からスタートさせるのが吉!
新人教育担当者もそのつもりで心構えをしておきましょう。
当社では、入社前に2回のタイミングで新人教育の場を設けています。
研修を重ねた内定者は、4月の入社時には学生っぽさが抜け、ヤマチユナイテッドの一員としての発言、行動、立ち居振る舞いがある程度できている状態になります。
社風としてビジネスマナー講習のような研修は一切やらない代わり、「ヤマチらしさ」がよく出るコンテンツを工夫することで「ヤマチらしさ」を身につけてもらうようにしています。
当社では内定者研修の段階から幹部社員育成の下地づくりを視野に入れているので、社風や理念を早いうちから理解させることは長期的観点から見ても非常に大切なのです。
とはいえ、1回程度の内定者研修ではなかなか吸収できるものではありません。
回数を重ねて徐々に浸透させていくのがもっとも効果的です。
ここで、当社の入社前の新人教育についてご紹介しましょう。
(1)内々定授与式
当社では例年、6月1日に内定出しをしたあとすぐに内定者を集めて「内々定授与式」を行います。
ここではグループ代表の山地章夫が講義をし、当社のミッションや働き方、仕事内容などについて丁寧に伝えます。
この内々定授与式で当社がやろうとしていることをだいたい理解してもらえるので、その後の内定者研修がスムーズになります。
(2)内定者研修
内定者研修は7月から2カ月に1回のペースで開催します。
いずれの回にも共通する目的は、当社の価値観を共有すること、そして入社後すぐに配属先の部署になじめるように、会社に対する理解と事業に対する理解を深めることです。
具体的には座学のほか、さまざまな部署の業務について深く知ることを行なっています。
入社後の配属先とは異なる部署へインタビューに行かせ、どのような業務であるか学んできた内容を既存社員の前で発表させて、社員から直接フィードバックをもらうという内容です。
内定者研修について詳しくは、こちらのコラムもご確認ください。
内定者研修の目的とは?同期の結束が高まる内定者研修のポイント
新人育成で大切なこと②自ら考えさせるコンテンツや活躍の場を
新入社員、既存社員を問わず、当社では「日々の業務や会社の未来をより良くするためにはどうしたらいいか」を一人一人に考えさせ、行動させるという経営方式を取っています。
内定者研修の話に戻りますが、最終課題として与えているのが「学生のうちにしかできないことで、未経験のことにチャレンジしてみよう」というもの。
チャレンジの過程は10分程度のスピーチにまとめ、既存社員の前で発表する場を設けます。
こちらからは「これをやって、あれをやって」という指示は一切せず、「あとになって『学生時代にやっておけばよかったな』と思わないように、できることを思い切りやってみて」とだけ伝えます。
そうすると本当にチャレンジ内容は多種多様で、遠く離れた実家に歩いて帰るとか、100人とフリーハグなどとユニークなものも。
2020年の内定者研修では、父親のルーツをたどろうと長野県に住む父の友人宅をアポなしで訪ねたところ、祖父母の同級生までもが登場し、みんなで宴会をしたと発表してくれた子がいました。
チャレンジを通じて、それぞれの個性や考え方が見えてくるのが面白いところです。
この課題は「何をやりたいか」「どのように行動したらいいか」「聞き手をワクワクさせるにはどうすればいいか」という部分を考えていかないとクリアできません。
元々は企画力やプレゼン力、スピーチ力を養うためのプログラムですが、先述したように当社は一人ひとりが考えて行動するスタイル。
実際に、入社後はざっくりと指示されることも多いので、それに対して「自分でどう考えて、どう行動するかを求められる場面があるよ」ということを、課題を通じて伝えているような部分もあります。
「うちは指示出さない会社だよ」と口で言ったら、新卒にとっては恐怖でしかないですからね(笑)
さて、新人たちの「考えて行動する」技量が試されるのが、入社後1年にも満たない次の就活シーズン。
新入社員の中から適性に応じてリクルーターを任命し、採用の場で活動してもらうのです。
当社のリクルーターは1〜4年目の社員で構成され、1年目であっても、学生に対して自分の言葉で当社の魅力をPRし、今度はインターンシップを進行する側として動かなければなりません。
ですが、リクルーターに選ばれること自体、当社ではステータスといって良いくらい嬉しいことなので、新人たちは生き生きと働いてくれるのです。
どんな企業でも、入社後は自分で考えて行動に移さなければいけない場面があるはずです。
その時にとまどったり困ったりしないように、やさしい課題から順々に目標を達成させ、あらかじめ訓練しておくことも必要ではないでしょうか。
こちらのコラムもあわせてご覧ください。
新入社員が成長する研修プログラムとは?成功ポイントや事例を紹介
新人育成で大切なこと③新人教育の内容に一貫性をもたせる
当社の新人教育は、内々定授与式と内定者研修、入社時研修と続いた後、OJTと並行してスピーディーに即戦力を育てるフレッシャーズキャンプを月1回開催する流れになっています。
ちなみに、当社のグループ全体の採用と人材育成を担当するHRDという部署は、2018年3月に設立されました。
それまでは部署という形ではなく、専任の採用担当が人事にあたっていました。
HRD設立以前もほぼ同じ流れで新人教育が行われてきましたが、決定的に違うのは各研修の運営がバラバラであったという点です。
例えば、入社時研修は採用担当者が対応し、フレッシャーズキャンプは若手社員による事務局が進行、各部署のOJTは現場の先輩社員の手に委ねられるといった具合。
流れはあっても一つ一つにつながりがありませんでした。
現在はこれらの運営をすべてHRDが統括することにより、それぞれの研修で教えること、やっていることに一貫性が生まれました。
学んだことに基づいて次のステップをすぐに用意することができるようになったので、毎年内容がレベルアップしていることを実感しています。
このほか、HRDがグループ全体にまたがって介入することで得られるメリットは、新人教育の面だけでもたくさんあります。
新人の上司と研修内容をはじめとした情報共有ができること、新人をフォローするメンター制度では状況を踏まえていち早く改善策を提示できることなど、連携が取りやすくなりました。
また、当社で採用する際の参考にすることもある「ゴレンジャー理論」で言えば、過去はリーダー気質で周りを引っ張るアカレンジャータイプが非常に多い状態でした。
そのため、アカレンジャータイプに合うような新人教育を行なってきました。
しかし、HRDを通じて俯瞰的な見方ができるようになると、今後は冷静で分析力に優れたアオレンジャータイプを育てていくなど、会社のニーズに合わせた考え方が可能になりました。
「うちはそこまでの規模じゃないから」と思っている皆さんも、少なくとも新人育成の研修内容にブレが出ないよう統括役を配置してみてはいかがでしょうか。
「前回と言っていることが違う」「人によって指導方針が変わる」といったことは新入社員の不安をあおりますし、会社への不信にもつながりかねません。
新人育成で大切なこと④既存社員とのコミュニケーションも大事に!
内定者研修の話でもお伝えしたように、当社では新入社員と既存社員との接点をなるべく増やすよう努めています。
内定者の疑問や不安を解消する場として設ける座談会もその一つ。
就職活動真っ只中の時期は、「この会社に入りたい!」という一心で周りが見えなくなりがちなので、給与や休みなど待遇面を気にかける余裕がありません。
内定後、「そういえばどうだったっけ?」とようやく気がつくのですが、タイミングを逃してしまってなかなか確認できない人も多くいます。
せっかく内定までこぎつけたのに、いざ入社したら思っていた仕事と違ったと、ミスマッチで辞めてしまうなんていうのはよく聞く話です。
そこで採用担当や配属先の部署の社員を入れて内定者との座談会を開き、「今疑問に思っていることはない?」と、面談のフォローのようなことをするのです。
実はこれも新人教育の一環で、「こうして優しく接してもらったから、来年の新人には自分たちも同じようにしなきゃいけないな」と思わせる狙いがあります。
既存社員にもこの感覚は定着していて、内定者が集まっていると聞きつけると、自主的に集まってきて情報交換に応じるなど、積極的に交流してくれています。
新入社員の早期離職を防ぐための対策については、こちらのコラムでも解説しています。
新入社員の早期離職対策とは?面談制度「フレッシャーズサポート制度」を紹介
新人育成で大切なこと⑤既存社員の成長の機会でもあるという心構えで
「新人育成」とはいいますが、そこに携わる既存社員にとっても新人育成の一連のプログラムに関わることは大きな成長の機会です。
人に教える=アウトプットするためにはインプットや事前の準備が必要ですから、教える側にも学びの要素はあるわけです。
また、新入社員に対して話したことに責任感が生じます。
「うちの社員としてはこうありたいね」と言葉に出せば、自らもそう振る舞うよう意識が向上することも成長の一端であると思います。
新人教育の担当を決めたいが人選に迷うという場合、既存社員にも成長の機会を与えるという心構えで選出しても良いかもしれませんね。
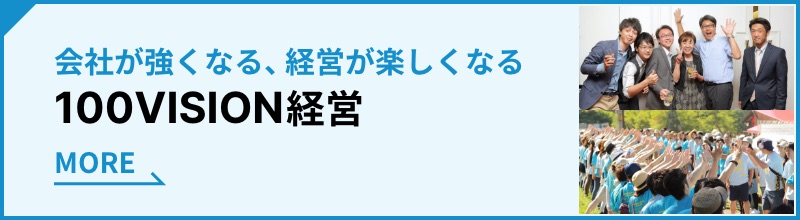
新人育成計画を立てるポイントや手順

当社では、新入社員の育成計画は採用計画とセットで考えます。
当グループでは「企業は人なり」という信念のもと採用・育成を進めています。
3年後、5年後の組織図を思い描き、そこから逆算して経営幹部、事業責任者候補、大活躍人材をどのように増やしていくかが当グループの重要な経営課題となっています。
将来ビジョンは当然現状より高い位置にありますから、今と3年後や5年後の将来のギャップを採用でどう埋めるかがポイントです。
新人育成計画を立てる際のポイント
会社を成長させる採用計画・育成計画を立てるために当社でポイントとしているのは下記の3点です。
- 将来ビジョンから逆算した計画を立てること
- 採用活動から育成までの戦略に一貫性があること
- 採用・育成に全社員で取り組むこと
将来ビジョンや企業理念・経営理念にしっかり紐付いた採用計画を立てられれば、求める人材にマッチしたアピールが可能となります。
新人育成計画を立てる前に考えておくこと
人材の育成計画は、3年後、5年後にどのような会社でありたいかを考えた上で採用活動を行なっていけば方向性がおのずと決まっていくものです。
採用活動や新人育成を行う前に、下記のようなことを考えておきましょう。
- 3年後、5年後の会社の将来ビジョンを実現するには?
- 現状とのギャップを採用で埋めるにはいつまでに、どんな人を、どれくらい採ったら良いか?
- 企業理念・経営理念に基づき、競合企業にはない自社の魅力と、ほしい人物像を結びつけるポイントは何か?
- 自社の魅力とほしい人物像をキャッチーに表現する採用コンセプトとキャッチコピーはどんなものか?
これらの方向性が社員に共有され、十分に浸透していれば、インターンシップの受け入れを依頼する際や、研修のために新人を担当業務から一時的に離してもらう際などに協力してもらいやすくなります。
詳しくはこちらもご覧ください。
採用計画・育成計画の立て方とは?経営計画と紐づけるポイントも確認
新人育成で大切なことや心構えを知って、頼りになる社員を育てよう
当社が新人育成で大切にしている心構えとして、5つのポイントをご紹介しました。
- 新人育成は入社前からスタートする
- 自ら考えさせるコンテンツや活躍の場を用意する
- 新人教育の内容に一貫性を持たせる
- 既存社員とのコミュニケーションも大事にする
- 新人育成は既存社員の成長の機会でもある
新人育成計画を立てる際には、3年後、5年後にどのような会社でありたいかを考え、そこから逆算してプランニングしていくことが大切です。
将来ビジョンや企業理念・経営理念にしっかり紐付いた採用計画を立てられれば、求める人材にマッチしたアピールが可能となるでしょう。
企業としての方向性を社員に共有し、十分に浸透させることも大切なことだといえます。
ヤマチユナイテッドでは、新人教育をはじめ、会社経営のノウハウやミッションの導入方法などが学べる、ワークショップやセミナーを随時開催しています。
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
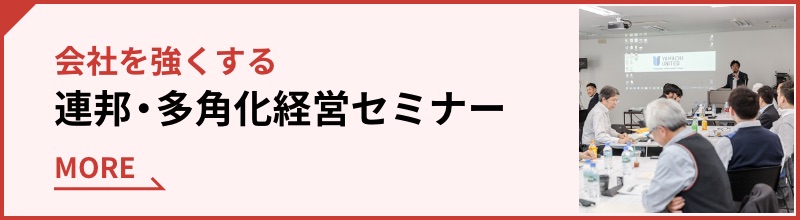
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|経営支援事業部|カンパニー長
山﨑 舞
人材総合サービス会社の営業部勤務を経て2018年(株)ヤマチマネジメントへ入社。前職では採用広告サービスの販売営業部で戦略スタッフとして企画・販促・アシスタント業務を担当。その際、元々取引先だったヤマチユナイテッドの社風やミッションに惚れ込み、転職を決意。現在は経営支援事業部で企画・運営を担当しつつ、営業推進チームリーダー兼人財開発コンサルタントとして活動。企業の新卒採用・育成を支援している。
