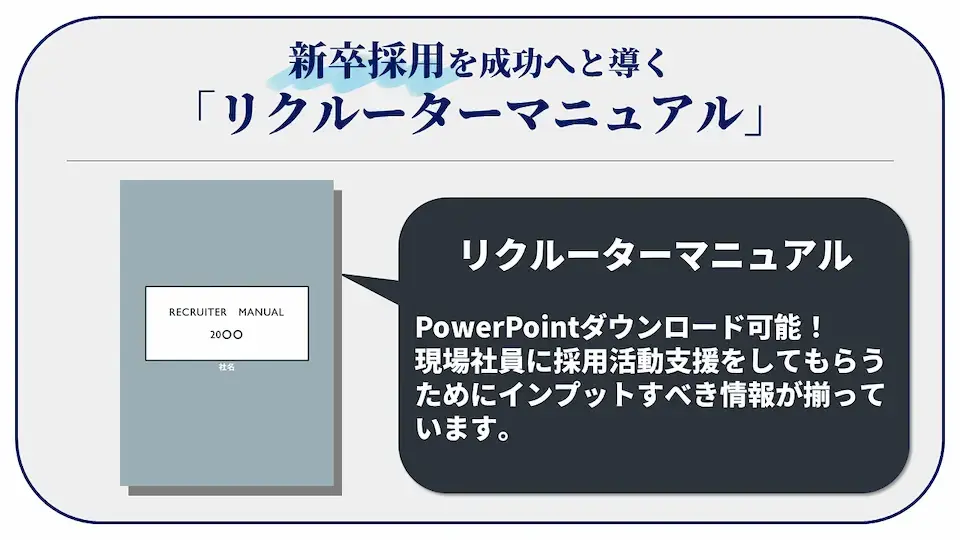新人教育を丸投げして成功するコツは?ヤマチの新入社員研修プログラムを紹介
採用・育成

こんにちは、ヤマチユナイテッド代表の山地です。
あなたは「新卒の新入社員は即戦力にならない」と思い込んでいませんか。
「じっくり時間をかけて育てる余裕はないから」と、ノウハウや実績のある中途採用に絞っている会社もあるでしょう。
しかし、ヤマチユナイテッドでは、実務経験のない新卒社員が短期間で力を身に付け、重要なポジションを担うことも少なくありません。
そんな人材を育成する新人教育は、入社2〜3年目の若手社員たちに「丸投げ」して任せています。
とはいえ、若手社員に教育の方針から全て丸投げするわけではありません。
ヤマチユナイテッドでは「新卒の新人を1年以内で一人前に育てる」ための独自の教育プログラム「フレッシャーズキャンプ」を用意しています。
社長がプログラムを作り、その運営を若手社員に「丸投げ」することで、先輩社員も一緒に成長し、新規事業などを任せられる人材に育っていく仕組みです。
今回は、新人教育を若手社員に丸投げして成功するコツについてお話します。
新人教育の目的や必要性だけでなく、丸投げする方法として新入社員研修プログラム「フレッシャーズキャンプ」の特徴や効果についてもご紹介しましょう。
目次
新人教育の丸投げによって生じるリスクとは?予防策も確認
一般的に、新人教育を社員に丸投げすると、さまざまなリスクが考えられます。
丸投げすることで起こり得るリスクと、それを防ぐ予防策も確認しましょう。
新人教育の丸投げによって生じるリスク
新人教育を社員に任せきりにすると、次のような問題が起こりやすくなります。
担当者の負担が集中する:教育と通常業務が重なり、キャパオーバーになりやすい
教え方・基準が人によって変わる:「人によって教わった内容が違う」という不公平感が生まれやすい
育成が属人化する:担当者が休職・退職すると、ノウハウごと失われてしまう
組織としての育成力が育たない:人材育成が個人任せになり、全体の質が安定しない
リスクを防ぐために有効な仕組み
新人教育を組織全体で支えるために、次のような仕組みが役立ちます。
教育内容を可視化し共有する:チェックリスト・マニュアル・手順書・動画などを整備し、「誰が教えても同じレベルになる」状態をつくる
フォロー体制を複数名で組む:育成担当を一人に固定せず、サポート役をつけて負担を分散する
定期的に情報共有や振り返りを行う:教え方のばらつきをなくし、改善ポイントをチームでアップデートする
新人教育を組織の仕事として位置づける:担当者任せにせず、チーム全体で新人を支える文化をつくる
新人教育の必要性とは?スピーディに即戦力にすることが重要
新人教育は、企業にとって新入社員が組織に適応し、効果的に業務を遂行できるようにするための重要なプロセスとなります。
多角化戦略を成功させるためにも、新人を即戦力にすることが必要不可欠です。
ここでは、新人教育の必要性とその際の課題を詳しく解説します。
新人教育の必要性
新人教育は、企業の未来を支える人材を育てるために欠かすことのできない取り組みです。
新入社員が安心して業務に取り組めるようにするための大切な準備期間と言えます。
仕事に必要な知識やスキルを身につけることで、早い段階から力を発揮できるようになります。
また、会社の価値観や目指す方向を理解してもらうことで、組織の一員としての意識が育ち、目標に向かって行動しやすくなるでしょう。
教育を通じてコミュニケーションやチームで動くための基本を学ぶ機会にもなり、良好な人間関係づくりや職場の雰囲気づくりにも役立ちます。
こうした関わりを通じて会社への信頼感が高まり、早期離職の防止につながることも。
さらに、教育を担当する側にとっても自身の知識整理や指導力向上の機会となり、組織全体の育成力を高めることができます。
新人育成で大切なポイントについては、「新人育成で大切なことは?新人育成計画を立てるポイントや手順も確認」もご覧ください。
新人育成と即戦力化の課題
新人教育の最大の目的は、一人前の人材を育て、仕事の現場で活躍してもらうことでしょう。
「新卒の新人は即戦力にならない」
「成果が出るようになるまでじっくり育てる」
多くの会社では、このようなスタンスで新人採用をしているかもしれません。
確かに、新卒社員は会社にフレッシュな風を吹き込んでくれますが、残念ながらすぐに成果を求めるのは酷。
ノウハウも経験もないのですから当然です。
しかし、多角化戦略を成功させるためには、できるだけ効率の良い方法で新人を即戦力にすることが必要です。
多角化戦略とは、現在の主力事業の他に新しい製品やサービスを既存・新規のマーケットに展開すること。
売上や利益アップが見込めるだけでなく、不測の事態で経営環境が大きく変化してもフレキシブルな対応ができるようになるなどのメリットがあります。
多角化戦略について、さらに詳しくはこちらをご覧ください。
中小企業の活路は多角化戦略にあり 《連邦・多角化経営概論》第1回
多角化経営と人材育成の重要性
多角化を進めるために積極的に新規事業を立ち上げていれば、必然的に人材が不足します。
しかも、新しい事業を軌道に乗せるには、やる気だけではなく、十分なビジネス知識やノウハウも必要です。
新規事業の多くは、少数精鋭のチーム編成にならざるを得ませんから、責任と覚悟を持ち、先頭に立って事業を引っ張っていくリーダーシップが求められます。
多角化経営を実践する会社にとっては、一人前の人材をスピーディに育てることは避けて通れない道なのです。
そのため、新人教育はただ丸投げで任せるのではなく、計画的で「仕組み化された教育」が重要となります。
ヤマチユナイテッドでは、新卒採用を成功へと導く「リクルーターマニュアル」をご用意していますので、ぜひご活用ください。
新卒採用を成功へと導く「リクルーターマニュアル」フォーマット
新人教育を丸投げする方法とは?ヤマチの新入社員研修プログラム「フレッシャーズキャンプ」
新人教育のおすすめのやり方として、ヤマチユナイテッドの新入社員研修プログラム「フレッシャーズキャンプ」をご紹介します。
ヤマチユナイテッドは、100の事業を立ち上げ、100人の事業責任者を創出する「THE 100VISON」実現を目標に、新入社員全員を将来の経営者として育てる方針で採用・教育を行なっています。
その取り組みの中でも、自社開発の新入社員研修プログラム「フレッシャーズキャンプ」は、特に象徴的な教育制度といえるでしょう。
これは、若手社員に新人教育を丸投げすることで、スピーディに即戦力へと育成する方法です。
「フレッシャーズキャンプ」の研修プログラムを開発した当初は、社長の私が中心になって行いましたが、2年目以降は事務局の社員たちに運営を任せています。
事務局のメンバーは入社して2〜3年目の「フレッシャーズキャンプ」の卒業生が中心です。
「フレッシャーズキャンプ」をスタートさせたきっかけや、具体的な内容・特徴をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
「フレッシャーズキャンプ」を立ち上げたきっかけ
かつて私たちの会社では、新人教育の大部分を外部の研修会社に任せていました。
基本的なビジネスマナーや知識を学ぶにはある程度有効でしたが、即戦力の人材を短期間で育てるには限界があります。
実際、新卒で入社した新人のほとんどが1〜3年間は「お客さま扱い」というのが現実でした。
しかし、仮に「新人が2年間、成果を出せない」という状態が続くと、大きな問題があります。
なぜなら、入社2年目の社員が一人前になっていないと、翌年に新人社員が入ってきた段階で、成果の出ない社員が2倍に増えてしまうからです。
例えば、ヤマチユナイテッドでは毎年15人から20人程度の新卒者を採用していますから、常時約40人の成果が出ない社員を抱えることになります。
3年間お客さま扱いにしていれば、成果が出ない社員が最大60人も生まれることに…。
こうした状況は、多角化経営を掲げ、常に変化している私たちの会社にとっては、大きなハンディキャップといえます。
そこで思い立ったのが、新卒の新人社員を1年以内で一人前に育てるための教育プログラム「フレッシャーズキャンプ」です。
新卒社員をビジネスのプロに鍛え、即戦力として働いてもらうために、独自の新人研修プログラムを2012年から始めました。
「フレッシャーズキャンプ」の内容や特徴
新人は全員、各部署に配属されてOJTで仕事を覚えていくと同時に、毎月1回のペースで開催されるフレッシャーズキャンプに1年間参加します。
フレッシャーズキャンプのプログラムは多彩な内容です。
私(グループ代表・山地 章夫)の基調スピーチに始まり、ビジネス書や新聞の読み解き、先輩社員へのインタビュー、グループ討議や模擬プレゼンテーション、社外からゲスト講師を招いての講演会など、学びの機会が幅広く用意されています。
フレッシャーズキャンプ中はいくつもの宿題が出されるので、新入社員は通常の業務と並行して取り組みながら、忙しくも充実した日々を過ごすことになります。
フレッシャーズキャンプの特徴は、人前で発表やスピーチをする機会が多いことです。
「読む、書く、話す」という基本的な能力が、ビジネスで成功するために必要なことだと考えているからです。
なかでも、人前で話す能力は大きな武器となります。
例えば、下記のような内容について、毎月キャンプの参加者の前で発表してもらいます。
先輩が課題図書に選んだビジネス書を読んでまとめたレポート
日本経済新聞の中で気になった記事を選び、自分なりの考察を加えたレポートなど
さらに、プログラムの中で非常に有効なのが「新規事業開発コンテスト」です。
このプログラムに取り組むことで新規事業開発に対するネガティブなイメージが払拭され、新しいことへ前向きに挑戦する社員へと成長していきます。
フレッシャーズキャンプについては、下記コラムで詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
新しいことに挑戦する会社にするには?変化を受け入れられる社風を作る
新入社員が成長する研修プログラムとは?成功ポイントや事例を紹介
新入社員研修では何をする?フレッシャーズキャンプ運営事務局の仕事を大公開!
幹部育成プログラムにおすすめ!新入社員向け研修「フレッシャーズキャンプ」
また、当社では新卒採用も若手社員を巻き込んで行なっています。
詳しくは「新卒の採用活動を若手社員に活躍してもらうのが一番良い理由」もご覧ください。
新人教育を先輩社員に丸投げする研修プログラム「フレッシャーズキャンプ」の3つの効果とコツ
ヤマチユナイテッドが新卒の新人社員の教育に「フレッシャーズキャンプ」を取り入れるのは、新人、先輩社員、そして組織にとって、多くの成長効果が期待できるからです。
「フレッシャーズキャンプ」で得られる効果について、視点別にそれぞれご紹介します。
新人に起きる変化と成長効果
教育担当(先輩)に起きる成長効果
組織全体に起きる変化と効果
①新人に起きる変化と成長効果
新人が得られる成長効果を見ていきましょう。
発表経験で「自信」と「表現力」が身につく
最近の若者は、面接などの少人数の場ではあがらずに話ができても、大勢の人の前だと緊張してしまい、自分の考えや意見をうまく伝えられない人が多いように思います。
しかし、フレッシャーズキャンプを通じて、毎回人前で発表をこなしていると、だんだんと慣れて度胸がついてきます。
多くの新卒社員がキャンプの後半では伝え方も上手になり、みんなの前でイキイキと自分を表現できるようになります。
例えば、ある理系出身の新卒社員は、当初、人前に立っただけで、緊張で手足がガクガクと震えてしまい、思うように話ができませんでした。
ところが、入社から半年が過ぎた頃には、見違えるほどに発表やスピーチが上手に。
最終的には、フレッシャーズキャンプで一番輝いていた人を相互投票で選出する「MVF(Most Valuable Fresher)」を受賞するほどに変身を遂げました。
フレッシャーズキャンプで発表やスピーチを繰り返した新人の中には「人前で話すことが楽しくて仕方がない」と感じられるようになった社員がたくさんいます。
多くの人の前で自分を表現し伝える力は、場数を踏むことによって磨かれ、自信へとつながっていきます。
新人のうちから人前で発表する機会を与えることは、成長を早める上でも効果的な方法ではないでしょうか。
経営感覚を早期に育み「数字に強い新人」をつくる
フレッシャーズキャンプでは、会社の収益構造を学ぶプログラムがあります。
たとえ新人であっても、基本的な会計の知識をもち、計算力を身につけることが大切だと考えているからです。
全社員が経営感覚を持っていることほど、強いことはありません。
そのためヤマチユナイテッドでは、新人や若手社員にも経営のルールをはじめ、会社の収益構造や売り上げ、粗利益、営業利益、経費の内訳といった会社の数字も積極的に共有しています。
こうした学びを通じて「どうすれば会社の業績が良くなり利益を生み出せるのか」「自分たちの待遇を良くするにはどうすれば良いか」といったことを自主的に考え、行動してくれるようになります。
私は「100事業100人の社長をつくろう」という当社の「100VISON経営」について、採用段階からしつこいほど繰り返し伝えています。
将来、事業を立ち上げて経営幹部として活躍するには、早くから会社の数字をはじめ経営感覚を養っておくことが、新人にとって必ず役立つと信じているのです。
チームでの事業企画を通じてビジネス視点と自信を得る
フレッシャーズキャンプのプログラムには「新規事業案の計画策定」も組み込まれています。
3人1組でイチから新規事業計画をつくり、経営幹部や上司の前で発表してもらうのです。
新卒はビジネスの経験がほとんどないため、さすがに即採用できるような新規事業を仕上げることはできませんが、テーマは自由なので発想力に富んだユニークな事業案が出てきます。
ここで大事なのは、事業計画を策定していくプロセスです。
中間発表で先輩たちから「本当に利益は出るのか?」「組織編成についてはきちんと考えているのか?」など、厳しい指摘を受けながら、自分たちの頭で考えて新規事業計画書を仕上げていく。
このプロセスを経て、事業をつくることの楽しさや大変さといった感覚を体験すると同時に、ビジネスの視点や自信を深めていくのです。
こうしたフレッシャーズキャンプでの経験は、新人の成長スピードを向上させていると実感しています。
新人の直属の上司たちも「入社当時とは見違えるように変わった」「自信がついてしっかりしてきた」といった感想を漏らしています。
②教育担当(先輩)に起きる成長効果
「フレッシャーズキャンプ」は、教育を担当する先輩社員もさまざまな成長効果を得ることができます。
教えることで「自分も学ぶ」循環が生まれる
事務局のメンバーは、フレッシャーズキャンプの卒業生が中心。
したがって、入社2〜3年の若手社員が、新卒の新人にさまざまなことを教えることになります。
新人たちの発表やスピーチに対して「よくできているね」と評価したり、「この点が足りない」と指導したりと、まさに「先生」の役割を果たしているのです。
こうして若手社員に新人教育をある意味「丸投げ」することは、教える側の社員の成長スピードを加速することにもつながります。
人に何かを教えようと思えば、自分も勉強しなければいけませんし、指導したことは自分も実践しなければ示しがつきません。
このように、フレッシャーズキャンプは2〜3年目の若手社員を育てる場としても機能しているのです。
若手がリーダーとしての意識を身につける
フレッシャーズキャンプは、若手社員がリーダーとしての意識を高めるための多彩な経験を提供しています。
具体的な効果は以下の通りです。
自主性の育成:自分で考えて行動する経験により、リーダーシップを発揮する自主性と責任感が強化される
課題解決能力の向上:実務に関連する課題に取り組むことで問題解決力が磨かれ、リーダー資質が育まれる
チームワークの強化:グループ活動を通じて、他者と協力しながら目標を達成する力が身につく
経営視点の理解:企業戦略や事業計画を学ぶことで、広い視野と経営感覚が養われる
③組織全体に起きる変化と効果
研修プログラム「フレッシャーズキャンプ」は、組織全体にも多くの効果をもたらします。
社長と若手社員の距離が縮まり、風通しが良くなる
運営は社員に任せているとはいえ、私もフレッシャーズキャンプには必ず参加しています。
基調スピーチを行い、それ以外の時間は参加者の様子を見守ります。
月に一度とはいえ、新人社員と一緒の時間を過ごすことで目に見える効果がありました。
フレッシャーズキャンプを始める前は、新卒の社員とのコミュニケーションをとるのは、採用の最終面接のときくらい。
正直に言うと、社員の顔と名前が一致しないこともありました。
社員にとっても、めったに顔を合わせることのない社長ですから、コミュニケーションの取り方もよくわからなかったでしょう。
要は、社長と若手社員の間に大きな距離があったのです。
しかし、フレッシャーズキャンプを開催するようになってからは、「Aさんは、こんなキャラクターだ」「Bさんは、こんな能力を持っている」というように一人ひとりの個性や強みが見えるようになり、新人の顔と名前が一致するようになりました。
また、社員のほうからも、社内で積極的に私に話しかけてくるようになったのです。
新人との間でコミュニケーションが活性化したのも、フレッシャーズキャンプの大きな成果だと実感しています。
育成が「仕組み」として根づくことで定着率が向上
フレッシャーズキャンプは、入社後1年間にわたって定期的に実施されることで、育成が「仕組み」として組織に定着します。
継続的な学びの場があることで、社員は自身の成長を実感しやすくなり、企業への帰属意識も高まるのです。
新入社員が早期に戦力として活躍できる環境を整えることで、業務効率の向上や社員のモチベーションアップにもつながります。
また、フレッシャーズキャンプを通じて企業理念や価値観を理解することで、組織全体の一体感が醸成され、社員同士の協力関係の強化・目標達成への意識も高まります。
フレッシャーズキャンプを始めてからは、新人の定着率があきらかに向上しました。
毎月同期で集まって一緒にワークを進める過程で、絆のようなものが生まれるのでしょう。
配属の部署は違っても、LINEや飲み会などを通じて、仕事や業務の悩みを相談したり、励ましあったりしているようです。
ヤマチユナイテッドでは新入社員の早期離職を防ぐ面談制度として「フレッシャーズサポート制度」も導入しています。
詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。
新入社員の早期離職対策とは?面談制度「フレッシャーズサポート制度」を紹介
新人教育を丸投げして成功するには、新入社員研修プログラム「フレッシャーズキャンプ」の導入がおすすめ!
ノウハウや経験のある中途入社社員は、企業にとって重要な戦力です。
私たちの会社でも、新規事業の内容や業種に合わせて、経験者採用を行なっています。
しかし、私の経験からいうと、新卒社員も育成環境によって大きく成長し、将来の中核人材として活躍できるようになります。
新人教育は、新入社員が安心して業務に取り組めるようにするための大切な準備期間。
仕事に必要な知識やスキルを身につけることで、早い段階から力を発揮できるようになるでしょう。
複数の新規事業を立ち上げて多角化経営を成功させるには、責任と覚悟を持って事業を引っ張っていけるように、新入社員を教育することが欠かせません。
ヤマチユナイテッドの新人教育は「フレッシャーズキャンプ」を導入し、運営を入社2〜3年目の若手社員に丸投げしています。
フレッシャーズキャンプのプログラムは多彩な内容となっており、人前で発表やスピーチをする機会が多いため、新人社員は人前で話すことに自信がつき、成長スピードが早くなります。
また、新人のうちから経営感覚やビジネスの視点を磨くことができるのも特徴です。
さらに、若手社員が主体となって運営することで、先輩社員自身も一緒に成長していき、新規事業などを任せられる人材に育ちます。
そして、社長と社員との距離が縮まり、組織全体のコミュニケーションが活性化するなど、会社にとっても多くのプラス効果をもたらします。
こうした多面的な効果を生み出しているのが「フレッシャーズキャンプ」なのです。
会社が一定の規模になり、採用の体制を整えられるようになったら、積極的に新卒を採用し、自分たちの手で育てていくことを検討してはいかがでしょうか。
新人教育の仕組みを整えることで、いずれ強力な経営幹部が育つはずです。
ヤマチユナイテッドでは、若手社員を育てるノウハウや多角化経営に関する経営セミナーやワークショップを実施しています。
興味がある方はぜひご参加ください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。