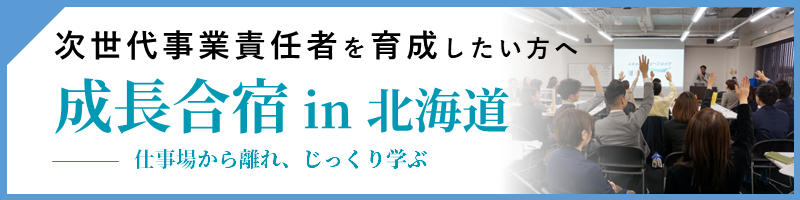幹部候補を育成するポイントとは?社員全員を幹部候補に育てる環境
採用・育成


こんにちは、ヤマチユナイテッドの石崎です。
組織が成熟して長期的な展望に目が向くようになると、会社の未来を中心となって支えてくれる若い人材の確保が必須となります。
「できるだけ早いうちから幹部候補を育てていきたい」と考える一方で、「知識も経験も浅い若手の中からどのように適任者を選べばよいのか」と悩む方も多いでしょう。
幹部候補育成に特化した研修プログラムを組む、外部研修を取り入れる、これらのいずれも、当グループで特別用意しているものはありません。
でも、すでに20代、30代の若い社員が幹部となって活躍してくれています。
みなさんの会社にも、幹部候補として育っていってくれる人材は、経営陣が考える以上に多くいるかもしれませんよ。
今回は幹部候補を育成するために理解しておきたい、幹部候補が備えるべきスキルやマインド、育成のポイントについて、詳しくお話ししていきます。
目次
- 幹部候補とは?ヤマチ流は新卒全員を幹部候補と考える
- 幹部候補の社員に求められるスキルやマインド
- 幹部候補の育成のポイントは?成長するための環境作りが重要な理由
- 幹部候補は新入社員全員!育成のカギは環境整備にあり
幹部候補とは?ヤマチ流は新卒全員を幹部候補と考える
そもそも幹部とは、会社や組織全体を広い視野でとらえてマネジメントや意思決定をする、組織の中心となる人材のこと。
幹部候補とそうではない人、私としては両者を明確に区別することは難しいと思っています。
一般的には、例えば生命保険会社なら全国の支店を回って経験を積ませる人材を「幹部候補生」と呼んで募る場合もあるでしょう。
また、飲食業界なら店長や本部スタッフとなる人材を求めて「幹部候補」という言葉を使う場合もありますよね。
ですが当グループにおいては、新卒の社員全員を「いずれ幹部になってもらいたい」という意識で採用していますし、彼ら彼女らにも実際そのように伝えています。
そうでない人がいるとすれば専門職に従事し、将来マネジメントはしないスタンスでいる人かな、という感覚です。
いずれはグループを背負って立つ人物。
そういう意味では採用した新卒者全員に幹部候補として期待をかけるというのがうちの考え方なのです。
幹部候補の社員に求められるスキルやマインド

幹部候補に求められるスキルやマインドとはどんなものでしょうか。
特に中小企業においては、営業成績の高い人が地位を上げていきやすく幹部候補になりやすいという傾向はあるでしょう。
でも、私が思うにそれだけではダメなんです。
業績以外に必要となるスキルやマインドについて見ていきましょう。
経営やマネジメントの知識
経営幹部やマネージャークラスの人間には、業績にプラスして経営についての知識やマネジメントができる能力があるかが求められます。
事業部を横断して俯瞰した目線で考え、発信することができるか。
このような能力は幹部としてのポストを与えられて急にできるようになるものではないため、若い社員でも日常の業務の中で実践できる環境を経営者が整えることが大切です。
コミュニケーション能力
幹部としては、さまざまな立場の人と目線を合わせてコミュニケーションを取り、組織力を強化できる能力が必要となります。
営業能力に長けていても、人心掌握が不得手だとか、ビジョンや方針を伝えるのが苦手な人もいるものです。
新入社員であっても積極的に意見を出して相手の意見を受け入れる環境があれば、社内外で幅広い人間関係を作ることができるようになるでしょう。
自主性・自責性
当グループでは若い社員が幹部となることも可能ですし、実際に20代、30代の幹部もいます。
決して早上がりさせているわけでも、できないのに無理やりやらせているわけでもありません。
むしろ「やらせてくれ」と言ってきたのは彼らの方。
これはやっぱり意識の問題で、組織全体に目が向いているからこそ「グループのために動きたい」と手を挙げるのです。
多少実力が伴っていない部分があっても、自主性や自責性がきちんと備わっていれば周りでフォローできるので登用しています。
会社によっては、マネジメント研修やマネージャー養成講座のように外部のプログラムを活用して幹部候補の育成を図っているところもありますね。
もちろんそれも否定しませんが、私の経験上、年次が上がった社員に行ってこいと言って参加させてもなかなか身にならないことが多かったように思います。
反対に、自分から行きたいと言って参加させた研修は身になってるように思います。
チームや会社全体を良くしたいという感覚
当グループの社員にも、はじめは目の前にある業務に日々修業のように取り組み、業績を作ることに集中する時期があります。
でも、何年か続けていくうちに自分の目の前のことだけでなくチームのこと、事業部のこと、さらに会社全体のことに視野が広がっていきます。
そうなると「自分のことだけでなく周りも良くしていきたいな」という感覚が発言や行動に表れてきます。
幹部にふさわしい人物像というと、こういうことかなと思います。
そうなるまでが遅いか早いかは個人個人の感度によりますが、うちでは社員全員にこの感覚を持ってもらえるような仕組み・仕掛けを構築しています。
会社や仲間に対する愛情
「周りも会社も良くしたい」という感覚は、会社に対して、そして仲間に対して愛を持つということです。
最終的に、幹部となるにふさわしい人物に求められるのは「愛」なんです。
会社に対する愛と、仲間に対する愛。
この2つが大事。
会社を好きじゃないとそこを見透かされて、ほかの社員がついていきませんし、より良い会社にするための行動は起こせません。
「この会社は絶対良くなる、良くする」という意志を持ち、その可能性を上の人間が信じることが重要です。
もう一つ、仲間に対する愛とは、幹部として自分のスタッフを信頼すること。
「みんな優秀なはずでみんなできる人で、今いるこのメンバーで会社を良くする」という感覚を持てるかどうか。
「うちはダメなやつばっかりだから」と他責にしてしまうのではいけないんです。
少なくともこの2つの「愛」を持っていて、かつ自ら育っていってくれる人材は、幹部となってからも組織のために大きく貢献してくれるはずです。
幹部候補の育成のポイントは?成長するための環境作りが重要な理由

前述のように当グループではどの人材も幹部候補であるという前提のもとに社員教育を行っているので、特定の社員にのみ適用される幹部候補育成プログラムなどはありません。
代わりに、社員全員に「会社全体を良くしたい」という感覚を持たせる仕組み・仕掛けを用意しています。
幹部候補の育成のポイントとして大事なのは、他者から与えられる方法論ではなく、自分で考えながら学べる環境作りをすること。
当グループで実践している環境作りの中でも特に有効な取り組みについて説明しましょう。
フレッシャーズキャンプ
入社1年目の社員を対象とした1年間の研修プログラムです。
OJTでテクニカルスキルを学ぶのとは別に、人前で話す、会社の収益構造を学ぶ、新規事業計画を立てるといったさまざまな課題を与えます。
その課題を通じて、将来事業責任者や幹部として活躍するための自覚やモチベーションを養います。
これが「自ら考え、行動する」下地を作るスタートラインとして非常に役に立っています。
詳しくは「新入社員が驚異的なスピードで成長する研修プログラムのつくり方」でご紹介しておりますので、こちらをご参考ください。
システム経営
システム経営は当グループの基本となる経営方式で、「自主計画」「自主管理」「自主分配」の三本柱から成ります。
簡単に説明すると「自分たちで経営計画を立て、自分たちで業績を管理し、その結果を受け入れて自分たちで成果分配を行う」このサイクルを繰り返す方式です。
システム経営がうまく機能するには、売上から営業利益まですべての数字がオープンでなければなりません。
「自分たち」にはトップから新卒まですべての社員が含まれます。
つまり、入社1年目の社員であっても会社の経営状況を数字で把握しているということ。
自分の働きや行動が業績にどう影響するのか?自分は業績へどう関わるか?を考えることで経営感覚が訓練されていく仕組みとなっているのです。
システム経営についてはこちらもご覧ください。
社員が経営参画できる「システム経営」とは? 《連邦・多角化経営概論》第2回
また、システム経営の3本の柱については、以下のコラムで詳しくお話しています。
社員の自主性を育てるには?システム経営・自主計画の導入方法とポイント
業績管理とは?業績と売上の違いや売上アップにつなげる方法を解説
効果的なインセンティブの決め方とは?自主分配を導入するメリットも解説
ポストや役割、会議設計が育成につながることも
ポストや役割が人材を育てることもあります。
当グループの場合、さまざまな視点から会社を活性化させる「委員会活動」でのプレリーダー体験も下地になり得ます。
各事業部のリーダーやマネージャーにとっては、他部署を含めた経営数字を扱う会議そのものが教育の場になることもあります。
そういう意味で、幹部になるまで経営に触れずに何年も過ごしてしまうのはもったいないなと感じます。
もしみなさんの会社が複数部署に分かれているのであれば縦割りにせず、横串を刺した会議設計を図りましょう。
他の部門から刺激を受けるというようなことも幹部育成には効果的だと思いますよ。
社員の育成にお悩みがあれば、こちらのコラムも参考にしてみてください。
中堅社員を幹部へと育成する方法とは?中小企業においての重要性も確認
幹部候補は新入社員全員!育成のカギは環境整備にあり
ヤマチユナイテッドにとっての幹部候補は、社員全員です。
新入社員のうちから経営やマネジメントの知識やコミュニケーション能力、自主性や自責性、社員や仲間への愛情を育てるためには、経営陣が環境を整えることが大切。
社員が幹部候補として育つために、フレッシャーズキャンプやシステム経営、普段の業務や役割の中で、自ら考える力を養い、経営感覚を身につけていける環境を用意しましょう。
その中で「周りも会社も良くしたい」と考えられる社員が幹部候補にふさわしい人材といえます。
私たちが定期的に開催する「連邦・多角化経営実践塾」では、今回お話した人材の育て方のほか、経営手法などヤマチユナイテッドのノウハウを公開しています。
もしよろしければ、こちらにも目を通してみてください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員
石崎 貴秀
1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。
連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。
入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。