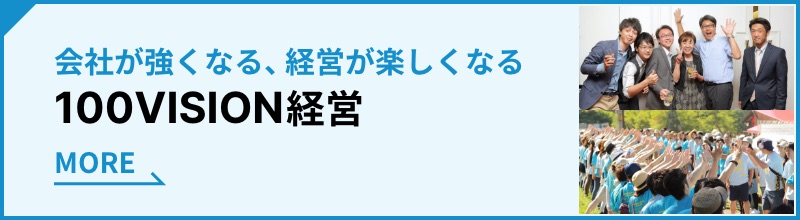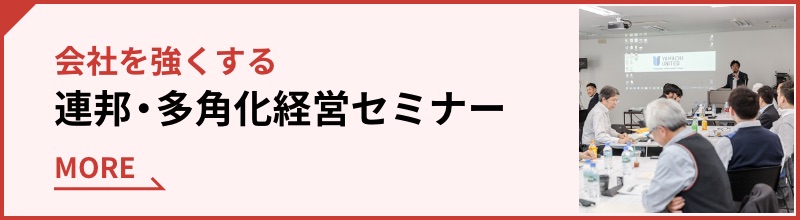会議は聞くだけOK・言いっぱなしOKで主体性が生まれる!
組織・給与制度

こんにちは、ヤマチユナイテッドの山地です。
長い会議や回数の多い会議はムダといわれます。
効率化するために、「ああしなさい」「こうしなさい」と部下に指示だけしてしまう経営者もいるでしょう。
しかし、それでは社員は育ちません。
私は「丸投げが社員を育てる」が持論ですが、今回のコラムは、会議も社員に「丸投げ」しようという提案です。
あなたの会社では議事録を作っているでしょうか。
その場で話し合って決まった決定事項はともかく、会議の場で出されたさまざまな意見やアイデアには、どのように対応していますか?
私たちの会社では、原則、会議で問題解決の方法を決定したり、スケジュールを決めたりといった対処を求めません。
会議の参加者は意見やアイデアを言いっぱなしでOK。
問題を解決すべき当事者はその意見やアイデアを聞き流してもOKです。
どうしてだと思いますか?
そのわけや、当社で行っている会議が活性化する仕組み「ワーク型経営会議」についてご紹介しましょう。
目次
- 会議で聞くだけOK・言いっぱなしOKにする理由やメリット
- 聞くだけ・言いっぱなしOKにするには「ワーク型経営会議」がおすすめ
- 聞くだけ・言いっぱなしOKの会議でグループ全体も活性化!
- 会議は聞くだけ・言いっぱなしOKで生産性の高い会議に!
会議で聞くだけOK・言いっぱなしOKにする理由やメリット
一般的な会議では参加者から意見やアイデアが出たら、決裁者が「それでいこう」とジャッジして、いつまでに誰が何をするか行動に落とし込み、進行をチェックしていきます。
そうしないと、せっかくの意見やアイデアが実行されず、言いっぱなしになってしまうことも多いからです。
ただ、決裁者である社長が一方的に「あれしろ、これしろ」と指示を出す会議をしていたら、部下は「やらされ感」を抱き、自分から行動を起こさなくなってしまいます。
一方、後ほど説明する「ワーク型経営会議」を実施すると、参加者一人ひとりが自分の頭で考えて、気づきを得て、意見を発言するようになる。
それが、社員の自主性を養うことにつながります。
さらに自主性を養い、社員主体で動いてもらうために、当社のワーク型経営会議ではあるルールを設けました。
「言いっぱなしOK・聞くだけでもOK」というルールです。
参加者から「こうしたほうがいい」「これは問題ではないか」と指摘されても、当事者は「参考になりました」といって、その場では聞き流してもいいということにしたのです。
これは、一般的には「オブザーバー」の役割にも似ています。
オブザーバーとは、発言権や決定権はないけれど、公平な第三者として俯瞰で見て、内容を把握し、意見を求められたら答えるという役割です。
言いっぱなしOK・聞くだけでOKな会議をすることで、次の4つの効果が期待できます。
効果①社員の自主性を大切にできる
当事者の心に引っかかる意見や指摘であれば、自然と「確かにそうだな。これは何とかしないといけない」と思い、対策をとるものです。
つまり、会議の場で全ての答えを出すのではなく、会議を気づきの場とすることで、社員の自主性を重んじているのです。
「どうすれば解決できるのだろう?」と自分の頭で考え、試行錯誤を繰り返すことによって、部下はビジネスに必要な思考力を鍛えることができます。
効果②当事者の「やらされ感」を排除できる
他の事業責任者から「これをやったほうがいい」と強制されたら、カチンときて「意地でもやらない」という感情になりがちです。
しかし、いったん自分の部署に持ち帰って冷静に考えて「確かに一理ある」と思う指摘があれば、必ず対策をとるでしょう。
自分で導き出した答えやアイデアであれば、主体的に行動するようになります。
これなら、「やらされ感」を排除することができるのです。
効果③現場の社員だからこその問題解決が可能に
経営者がそれぞれの事業について「こうしたほうがいい」と的確な指示ができればいいのかもしれませんが、多角化していれば、それは現実的ではありません。
経営者はスーパーマンではないので、現場をすべて把握しているわけではありませんし、すべてに適切な解を用意できるわけでもありません。
現場の社員に知恵を出し、解決してもらう必要があります。
要するに、社員に問題解決を「丸投げ」できるのです。
効果④参加者の発言へのハードルを下げられる
会議の場で意見をいう方にとっても「言いっぱなしOK、聞くだけでOK」であれば、発言する心理的ハードルは低くなります。
あとで自分の事業部について言い返されるという「仕返し」を恐れる必要もありません。
傍観者が増える場合はオブザーバーの役割を与えるのも一つ
聞きっぱなしをOKとして意見があまりに出ない場合は、ワーク型経営会議方式にする他に、先述したオブザーバーという役割をしっかり与えるのもありです。
特に新入社員は遠慮や萎縮により発言ができないという場合も多く、「いつ意見をしようか」と焦って、全体を把握する余裕がなくなってしまうこともあります。
ワーク型経営会議方式にしない場合は、オブザーバーを任せることで、全体の状況を把握することができる上、進行役から振られた時に発言ができるため、戸惑うことが少なくなります。
オブザーバーに慣れてくれば、発言の仕方やタイミングも掴むことができるようになり、そういった役割がなくても会議に積極的に参加しやすくなるでしょう。
聞くだけ・言いっぱなしOKにするには「ワーク型経営会議」がおすすめ
当社ヤマチユナイテッドの会議形式はユニークで、ワークショップスタイルの「ワーク型経営会議」を実施しています。
これは事前にまとめられた事業部の報告書に対して、会議の参加者が2人1組のペアになって意見やアイデアを出し合い、その後参加者全員で意見を出していくというもの。
会議では社長や幹部が一方的に話をするだけで終わったり、活発な意見交換がなされていなかったりと、マンネリ化しがちです。
当社もそのような状態になっていたことがありますが、「ワーク型経営会議」を実施するようになってからは会議で活発なコミュニケーションが生まれるようになりました。
自分一人の意見を大勢の前で発表するのは気力がいりますが、2人1組で一度話し合っておくことでアイデアを客観視・修正できるため、自信が生まれるのでしょう。
「ワーク型経営会議」の詳しい実施方法などについてはこちらのコラムもご覧ください。
会議で意見が出ない原因。意見を引き出す「ワーク型経営会議」とは?
聞くだけ・言いっぱなしOKの会議でグループ全体も活性化!
会議の仕組みを「ワーク型経営会議」にし、出てきた意見やアイデアは言いっぱなしOK・聞くだけでOKにすると、会議の場や問題解決時にメリットがあるだけではありません。
事業部を横断した連携が生まれてグループ全体のつながりを活かすことができるようになるため、各事業部だけでなくグループ全体に価値をもたらすのです。
詳しくご紹介していきます。
さまざまな視点からのアイデアやアドバイスが出る
言いっぱなしOKワーク型経営会議では、気軽に参加できることで積極的な意見が飛び交うようになります。
「これを言ったら反対されるかな」「反論すると反感を買うかな」などを気にせず、思ったことをただ言うだけでOK。
そして、言われた側も腑に落ちなければ「そういう意見もありますよね。参考になりました」と聞き流してOKなので、どんどん積極的に話が進んでいきます。
参加者から積極的に意見が出るようになると、自然と事業部を横断した「横」との連携もとれるようになります。
例えば、次のような議論が展開されます。
Aさん「○○事業部は、前回の会議でも同じ課題を挙げていたと思いますが...。」
Bさん「そうですね、私だったら、まずは大々的に商品PRをして損益分岐点に乗っけることを優先するかな」
Cさん「それなら、うちのマーケティングチームを貸しましょうか?」
Dさん「イベントを仕掛けたらどうでしょう。うちのイベント事業部で安くやりますよ」
Eさん「今はフェイスブック広告だよね。すごく反応が良いから、うちの成功事例を試してみたら?」
このように、さまざまな視点からアイデアが出てきますし、各事業部の強みを活かしたアドバイスもできます。
事業部ごとの縦割り組織になっていて、横の連携の意識が低いと、このような議論には発展しません。
言いっぱなし、聞きっぱなしOKの「ワーク型会議」だからこそ、こうした積極的な意見が出てくるのです。
他の事業部の成功事例を共有してグループ全体で成功できる
当社のグループ経営推進会議で議論になるのは、だいたい業績アップや人の問題などです。
これらの課題は、どんな事業部でも共通しているので、他部門の事業責任者の発想やアイデアは参考になることが多くあります。
例えば「人材募集しても人が集まらない」という悩みは、どこの事業部でも共通しています。
他の事業責任者から「○○という媒体は効果があったから、試してみたら?」といったアドバイスを共有できれば、グループ全体に価値をもたらすことになります。
それぞれの事業部が強みを生かして、他の事業部の足りないところを補い合う。
これこそ多角化の大きなメリットです。
会議は聞くだけ・言いっぱなしOKで生産性の高い会議に!
ヤマチユナイテッドの会議では、参加者全員の前で発言する前に、2人1組のペアで意見やアイデアを出し合う「ワーク型経営会議」を実施しています。
これによって参加者一人ひとりが自分の頭で考えて気づきを得て、意見をいうようになり、社員の自主性を養うことにつながります。
さらに、「言いっぱなしOK・聞くだけでもOK」というルールを設定して、問題解決も社員に「丸投げ」しています。
もし、それでも積極性に欠ける...という場合があれば、新入社員にオブザーバーの役割を与えてみるのもありでしょう。
会議において明確に方針を決めることで、社員の主体性を大切にし、当事者の「やらされ感」を排除できます。
現場の社員だからこその問題解決が可能になるでしょう。
言いっぱなしも、聞くだけで流すことも、一概に悪いことではないということをご理解いただけたでしょうか。
アイデアが行き詰まった時のように無駄だと感じる会議でも、発想の転換がより良い手法やひらめきにつながることがあるというわけです。
ヤマチユナイテッドでは会社の組織運営のノウハウや効果的な会議の導入方法などワークショップやセミナーなどのイベントを随時開催しています。
気になる方はぜひチェックしてみてください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。