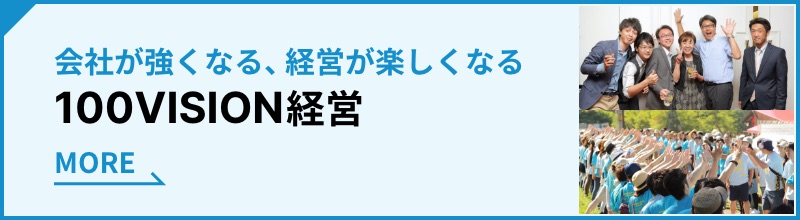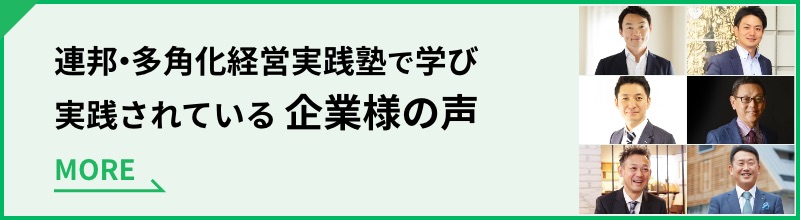新規事業を立ち上げて人材を育てる!人材育成のポイントとは?
多角化・新規事業


こんにちは、ヤマチユナイテッドの山地です。
「多角化したくても、新規事業を任せられる人材がいない」
ときどき、このように嘆く経営者とお会いします。
「新規事業は簡単に失敗できないから、半人前の従業員には任せられない」
「優秀な人材は既存事業の主力メンバーなので、新規事業にまわすわけにいかない」というわけです。
このように考えてしまう経営者は、次のように発想の転換をしてみてはいかがでしょうか。
「先に新規事業を立ち上げれば、自然と人が育っていく」と。
今回は当社の人材育成の手法をご説明しましょう。
新規事業の立ち上げプロセスの中で人材育成を行う必要性や、新規事業を任せる社員に求められるスキルをご紹介し、新規事業を進めながら人材を育てるポイントも解説します。
目次
- 新規事業を立ち上げる前に人材を育てるべきなのか?
- 新規事業の立ち上げに求められる人材スキルとは?
- 新規事業の立ち上げを進めながら人材を育てるポイント
- 新規事業の立ち上げを進めながら人材を育てるのが、中小企業の多角化のカギ!
新規事業を立ち上げる前に人材を育てるべきなのか?
多角化をできないでいる経営者は、新規事業で成功するためには、まずは十分な人材を集めてから・育成してから...など「準備万端でなければならない」と思い込みがちです。
しかし、もともと優秀な人材が限られる中小企業の場合であれば特に、人材が育つのを期待して待っていたらいつまでたっても新規事業に打って出ることはできません。
多角化を成功させて売り上げを伸ばしていく経営者を見ていると、皆さん、走りながら環境を整備していくスタイルをとっています。
つまり、人を育てる前に、まずは「これはおもしろい事業になりそうだ」というビジネスを立ち上げて、その事業を進めていくプロセスの中で人を育てています。
私の経験から言っても、「これは良い!」とひらめいたものを、あまり後先を考えず、情熱をもってスタートさせた新規事業のほうが、結果的にうまくいき、売上規模も大きくなっています。
「鉄は熱いうちに打て」といいますが、新規事業も情熱が燃え上がっているうちにさっさと始めたほうが軌道に乗りやすいのです。
心配はいりません。
新規事業を担う人材は、新規事業のプロジェクトに巻き込み、仕事を任せていくことで、どんどん成長していきます。
新規事業の責任者の選び方のポイントは下記のコラムでご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
新規事業責任者の選び方とは?向いている人・向いていない人も紹介
新規事業の立ち上げに求められる人材スキルとは?
新規事業の立ち上げのプロセスの中で人材を育成すると、社員はそれまでの既存事業では得られないスキルやマインドを得ることができます。
新規事業を進める中でどんなスキル・マインドがある人材にしていけば良いのか、具体的にご紹介しましょう。
解決策を常に考える力
新規事業では社内で初めてのことにも取り組んでいくことになるため、ノウハウがない中で立ちはだかる壁を1つ1つ乗り越えることの繰り返しです。
新規事業を任される社員は問題に向き合い、自分のアイデアや他社の事例などをヒントに、常に解決策を考えることになるでしょう。
できない理由や原因を探す「原因志向」ではなく、乗り越えるにはどうしたら良いか考える「解決志向」で思考しなければ新規事業は成功しません。
新規事業の立ち上げを成功させる人材には、この「解決志向」が必要となります。
チャレンジ精神
机に座って考えているだけでは新規事業は進みません。
とにかくまずは動く、手を動かすというチャレンジ精神やフットワークの軽さも必要となります。
1つのアイデアがうまくいかなくても、次のアイデアを出す。
それでもだめならまた別のアイデアを。
失敗を恐れず、諦めずに問題や課題にチャレンジし続けることで、状況を打破するヒントが見つかるものです。
スピード感
新規事業はスピードが成功・失敗の分かれ目になることも少なくありません。
市場や顧客のニーズは刻一刻と変化していますし、他社も同様の新規事業を進めているかもしれません。
自社が最も早く市場にサービスや製品をリリースすることが重要ですので、新規事業を任せる人材にはスピード感が必要不可欠です。
ただ、早くしようとするあまりクオリティが下がっては意味がないので、PDCAを早く回して改善を繰り返しながら進めることが欠かせません。
具体例としては、スピード感を出すために、最低限の機能を備えた試作品をユーザーに試してもらい、満足度が高かった方のサービスや製品の開発を進めるという手法が使われることもあります。
ロジカルシンキング
ロジカルシンキングは「論理的思考」とも呼ばれ、情報を順序立てて整理しながら考えたり説明したりする手法のことです。
論理的で筋が通った考え方ができるため、感情でなく事実に基づいて的確な判断をすることができます。
新規事業では行動することも大切ですが、根拠もなくただ突っ走っても意味がありません。
市場調査や他社分析を行い、大量のデータを分析して市場性を判断する必要があるのは言うまでもないことでしょう。
このように定量的に分析することによって、自社の経営陣や社員に納得感のある説明ができるようになり、成果が出なかった原因も明確にしやすくなります。
当社が考える人材育成については、こちらもご覧ください。
新規事業の立ち上げを進めながら人材を育てるポイント
多角化の成功の鍵を握るのは、部下へ「丸投げ」できるかどうかです。
社員に大胆に任せ、経営に巻き込んでいけば、おのずと人材は成長するものです。
そして、気持ちよく「丸投げ」するためにも、多角化を進めることが有効です。
ひとつしか事業がないと経営者は心配で丸投げできませんが、いくつも事業があり、次々に多角化を進めていると、忙しいので「丸投げ」せざるをえないからです。
多角化経営は、「丸投げ」しやすい環境をつくることにもなるのです。
そもそも多角化経営とはなんなのか、詳しくはこちらもご覧ください。
中小企業はなぜ多角化すべきか?ヤマチの事例に学ぶ成長戦略のヒント
事業の多角化戦略の失敗例・成功例とは?成功させる条件もご紹介
ここからは実際に新規事業を進めながら人材を育てるポイントについてご紹介します。
立ち上げ段階では「経営者の我慢」が人材を育てる
人材を育てるのに最も重要なことは何でしょうか。
それは「経営者の我慢」につきます。
事業がうまくいっている経営者で、苦労を経験していない人はいません。
私は、多くの優れた経営者と交流してきましたが、失敗や苦労を乗り越えた経験を糧に成功を手に入れた人ばかりです。
人材を本気で育てたければ、権限移譲をし、仕事を部下に任せて、どんどん失敗を経験させなければなりません。
新規事業のタネを見つけてきて芽が出るまで育てるのは、経営者の大切な仕事のひとつです。
だから、新規事業を立ち上げる段階では、ある程度、経営者がイニシアチブを握ることは重要です。
ただ、多角化をスムーズに進めるうえでのポイントは、新規事業の企画段階から部下を巻き込んでいくこと。
事業責任者を指名し、積極的に仕事を任せていくのです。
新規事業準備のステップについては「新規事業の準備をステップごとに解説!事業多角化の成功条件とは?」「新規事業立ち上げのプロセスとは?多角化を成功へ導くステップを解説」もあわせてご覧ください。
軌道に乗り出したら「あとは任せた」
事業が立ち上がり軌道に乗りそうな段階で、経営者は「あとは任せた」と新規事業の実務から身を引き、次の新規事業立ち上げに注力する。
これが理想です。
ところが、多角化がうまくいかない経営者は、部下に任せることができません。
「あれやれ」「これやれ」と指示を出してしまいがちです。
確かに経験値の高い経営者自らが手取り足取り指示を出したほうが、スピーディーに結果が出て、うまくいく可能性は高くなります。
しかし、このやり方では、部下は経営者の顔色ばかりうかがう「指示待ち人間」になってしまいます。
いつまでたっても自分で考え、判断できるようにはなりません。
中小企業の経営者は、自己主張のできる社員を育てなくてはなりません。
なぜなら、従業員にとって中小企業で働くメリットは、自分が主体性をもって判断し、仕事を進められる点にあるからです。
上司の言うことを言われたとおりにやるだけなら、大企業で働いたほうが良いと考えるでしょう。
何でも経営者が指示を出すと新規事業は一時的にうまくいくかもしれませんが、部下がなかなか成長しないので、いつまでも経営者が陣頭指揮をとる羽目になります。
そうすると、本来の経営者の仕事である多角化に費やす時間を確保できません。
口出しはせず、自ら考えさせる
私の場合、いったん新規事業を部下に任せたら、余計な口出しはしません。
もちろん、部下が180度違う方向に進もうとしていれば「本当に大丈夫か?」と、軌道修正を促すこともあります。
「自分のやり方のほうが売り上げは増える」と思っていても、口には出さずに部下のやり方に委ねてみます。
そのあと、部下が「思ったより売り上げが伸びませんでした」と報告してきたら、「どうしたらもっと伸びると思う?」と質問し、気づきを促します。
答えは与えずに、部下に考えさせるのです。
部下は悩み、苦しむかもしれませんが、そうした「濃い経験」が部下を成長させるのです。
正直言って、人材を育てるには「我慢」が必要です。
部下の仕事ぶりを見ていると、「あれやれ」「これやれ」と言いたくなる気持ちはわかります。
しかし、そこでグッとこらえる。
言いたくても我慢することが、経営者の大事な仕事といっても過言ではありません。
失敗から学ぶ機会を奪ってはならない
「それはやったらダメだ」と言うのは簡単です。
しかし、人は失敗を通じて成長していきます。
身を持って痛い目に遭うから、その経験を糧にすることができます。
たとえば、部下が電話に出るのが遅いからといって「電話は2コール以内で出なさい!会社の信用が落ちてしまうじゃないか!」と怒鳴るのはあまり効果がないでしょう。
それよりも、お客さまから直接「電話に出るのが遅い」と指摘されたほうが、学びは大きくなります。
そもそも、失敗したからといって、会社の信用が失墜するケースはごくまれです。
会社全体としてみれば、小さな損害ですし、本人が少し恥をかく程度でしょう。
それよりも、部下が失敗から学ぶ機会を失い、成長しないことのほうが、会社にとって大きな損害です。
また、「部下のやり方よりも、自分のやり方のほうがうまくいく」と経営者が思っても、実際にやってみたら、部下のやり方のほうが成果は上がるかもしれません。
若い感性や思いきりの良さに任せたほうが、うまくいくケースは案外多いのです。
責任は経営者がとる
気をつけていただきたいのは、「丸投げ」するといっても、部下に責任まで押しつけてはいけないということです。
失敗したときの責任は、「丸投げ」した経営者にあります。
「責任は俺がとるから思いっきりやれ」と、テレビドラマの俳優のようなセリフは照れくさくて言いづらいかもしれません。
ですが、いずれにしても「責任は経営陣にある」ということを部下に伝えておく必要はあります。
そうしなければ、部下は失敗を恐れて、小さくまとまってしまうでしょう。
新規事業の立ち上げを進めながら人材を育てるのが、中小企業の多角化のカギ!
「多角化したくても人材がいない」という経営者には、「多角化のプロセスで人材が育つ」とお伝えしています。
新規事業への情熱が熱いうちに立ち上げ準備を始めて走りながら人材を成長させ、環境を整備していくことで、事業規模も大きくなっていくのです。
新規事業の立ち上げを任せる人材には、解決策を常に考える力やチャレンジ精神、スピード感、ロジカルシンキングなどのスキル・マインドが必要です。
このスキル・マインドは新規事業立ち上げのプロセスの中で人材を育成することで得ることができます。
新規事業を進めながら人材を育てるポイントは、経営者があれこれ指示を出さず社員に「丸投げ」すること。
どんどん失敗させ、任せ、そして失敗した時の責任は経営者がとるとしっかり伝えておくことが大切です。
多角化と人材育成は車の両輪。
自己主張しイキイキと働く従業員を育てるためにも、積極的な多角化がおすすめです。
私たちが定期的に開催する「連邦・多角化経営実践塾」では、経営手法などヤマチユナイテッドのノウハウを公開しています。
もしよろしければ、こちらにも目を通してみてください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。