海外研修の目的とは?メリットや成功のポイントを当社の事例をもとに紹介
採用・育成

こんにちは、ヤマチユナイテッドの山﨑です。
「グローバルな視点からさまざまな可能性を探りたい」「事業拡大のヒントを得たい」などの理由から、海外研修を検討する企業が増えています。
しかし、いざ海外研修を実行するとなると、言葉や習慣の違いをはじめ、「現地での研修内容は?」「不在となる社員の業務をどうする?」など、企画段階から不安が山積みとなっていないでしょうか。
結局、計画倒れになっているなんてこともあるかもしれませんね。
ヤマチユナイテッドは2018年から海外研修を始めました。
今回は、海外研修の目的について、ヤマチユナイテッドの事例とともにご紹介します。
海外研修のメリット・デメリット、海外研修の目的を達成するための成功のポイントについてもご紹介しますので、ぜひご確認ください。
多角経営企業という会社の性質上、海外研修の目的や効果はもしかしたら他の企業さんとはちょっと違うかもしれませんが、一つでも不安を取り除けるよう参考になれば幸いです。

目次
海外研修の目的・研修の形態とは?
企業の海外研修というと、普通は関連業種の企業視察とか、語学や技術の習得が目的となるプログラムを組んでいる場合が多いでしょう。
海外で通用するリーダーの育成を目指して派遣する、ということもありますね。
海外研修の形態には、海外トレーニーとして海外現地法人に赴任したり、短期海外派遣でフィールドワークを行なったり、大学に留学したり、インターンシップに参加したりといった方法があります。
単に外国の言語を話せるようになるだけでなく、「日本にはない海外の感覚」を実地の体験から得てほしいという狙いから海外研修をする企業は多いです。
ヤマチユナイテッドの海外研修の目的は「視野を広げ異文化の感覚を取り込むこと」
当社の場合は多角経営で業種が多岐にわたっているため、グループ全体で海外研修をするとなると、どれか一つの業種に焦点を当てて視察を行うことが難しいです。
ですから、これまで各業種での海外視察は続けてきましたが、グループ全体の社員教育としての海外研修は2018年に始まりました。
その目的は、当グループ代表・山地 章夫が学生時代にアメリカやカナダを放浪して得たものに着想して会社を発展させたというルーツに関連しています。
山地は北米文化に触れたことで、仕事も人生も楽しむライフスタイルや豊かな住環境に大きな影響を受けたと言います。
それだけに、社員にもぜひそんな感覚を身につけてほしい、視野を広げていろいろな視点から業務に取り組めるようになってほしいという思いが根底にあります。
「視野を広げ異文化の感覚を取り込む」、そしてそのための機会を与えることが当社の海外研修の目的です。
参加する社員は年次や業種を問わず社内SNSで募り、希望者の中から抽選で選ぶことにしていますが、「これまで会社のお金で海外へ行ったことがない人」が条件。
HRD(Human Resource Development)が事務局として動き、抽選の際には年齢や業種に偏りが出ないよう調整も行います。
HRDについては「人材開発の役割とは?HRD部門がつくる未来の組織と手法について」でもお話していますので見てみてくださいね。
海外研修を行うメリットとデメリットとは?

海外研修には大きなメリットがあるものの、海外研修の効果が上がらないとデメリットが勝ってしまうという一面もあります。
では、海外研修には一体、どんなメリットとデメリットがあるのか見ていきましょう。
海外研修のメリット
海外研修のメリットには、以下のようなものがあります。
- 異文化での体験を通して業務の改善点を見つけられる
- 視野が広がる
- 国際的なネットワークが構築できる
- 語学力が向上する
- 社員の自立心が育まれる
海外企業の視察や異文化の体験を通して、日本での業務の改善点を見つけられるなどのメリットがあります。
グローバルな視野が身につくことで、私生活を見直すきっかけになったり、社員の自立心が育まれて成長につながったりすることも。
社員が成長することは、会社の成長にもつながります。
また、海外とのネットワークが構築できれば、ビジネスチャンスも広がっていくでしょう。
海外研修のデメリット
海外研修のデメリットには、以下のようなものがあります。
- 費用と労力がかかる
- 海外研修の効果が上がるかわからない
- 短期間では効果が出にくい場合がある
やはり気になるのは費用や労力の面でしょう。
会社のお金を使っていくわけですから、どの程度の費用対効果があるかも気になるところですが、実際にそれが数字として表れにくいため「せっかく海外研修をしたのに」と感じてしまう経営者も少なくありません。
短期間の研修だと、現地の感覚まで得ることが難しいというケースもあります。
ヤマチの事例をご紹介!行ってみて実感する海外研修のメリット
当社では、2018年、2019年と過去2回の海外研修で、いずれもアメリカのポートランドとシアトルを訪問しました。
ポートランドは札幌の姉妹都市でもあり、アットホームな雰囲気で、歩いて回れる小規模の街です。
これまで研修に参加した人は、学校などでの留学や海外旅行の経験がなく、海外へ行くこと自体初めての人がほとんどです。
そのような意味でも大きなカルチャーショックを受けた人が多くいました。
特に2018年の海外研修では、Amazonやスターバックスのように世界を代表する大企業を視察し、その仕組みを見て圧倒されたようです。
しかし、当社の視察先はそんな大企業ばかりではありません。
うちと同じくらいの規模・従業員数でやっている設計事務の会社を訪ねたときのことです。
当グループのハウスメーカー「ジョンソンホームズ」と似たような業種でありながら、取り組み方がまったく違っていました。
会議の進め方、仕事以外の部分でのライフスタイルなどにも気づきがあったりして、すごく有意義な時間を過ごしたと聞いています。
日本企業の組織の構造はトップダウンが主流だと思います。
海外で衝撃を受けたのは、社員が「どうやったら自分たちが楽しく働けるか」「どうすればお客さんに喜んでもらえるか」と自発的に考えて働いているところ。
あえて、そのような姿勢を海外研修参加者には見せたいという思いもあって、団長として一行を率いる社員と社長の海外ネットワークも使いながら、条件に合いそうな視察先を選定しています。
また、アメリカには建材の輸入でお付き合いの長い会社さんがあります。
定期的に情報交換して「最近アメリカではこんなのが流行っている」とか「その目的なら絶対この会社に行ったほうが良いよ」と教えてもらっています。
取引先の方が1週間つきっきりで案内してくれて、「こういうのも体験したら」とライブハウスへ連れて行ってもらったこともありました。
Amazonやスターバックスは予約をすれば誰でも視察できますが、私たちの働き方、暮らし方の参考になる中小企業さんに関しては、そういったパイプがないとなかなか難しいのです。
海外研修参加者は目の色が変わって帰国してくるので、事務局としてもやりがいがあったのではないでしょうか。
企業視察ばかりでなく、現地の文化に触れたことも良い刺激になるはず。
海外研修では体験したさまざまな出来事を通じて、人間的に成長したり自信がついたりする人も多いです。
現地の人と交流する機会があれば人脈が広がるメリットもあるという点では、ほかの企業さんにおいても同じことが言えると思います。
海外研修先の選定には、自社のブランディングに生かせるかという視点も大切です。
中小企業のブランディングについては「中小企業こそブランディングに力を入れるべき理由とは?」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
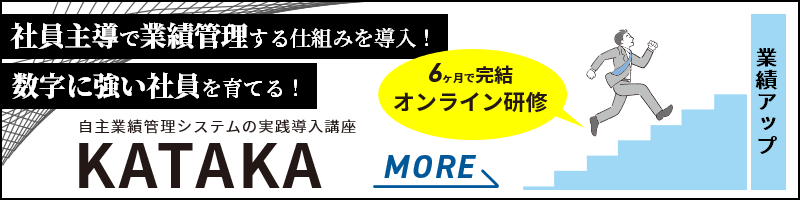
海外研修の目的を達成するための成功のポイント

「海外研修が成功した」と言えるのは、想定していた目的を達成できたときではないでしょうか。
海外研修を成功させるためのポイントを紹介します。
海外研修の社内準備は入念に行う
海外研修には事前にしっかりと準備することが欠かせません。
スケジュール調整はもちろん、海外が初めての人にはパスポートや持ち物の準備も一苦労です。
当社の場合は、一行を率いる団長(社長や社員)が海外経験豊富なこと、また、アメリカの取引先様が情報提供してくれることが有利に働いていますが、それでもスケジューリングには毎回非常に苦労しています。
例えば、企業視察を申し込むにしても日本とは感覚が違います。
日本の企業ならコンタクトが早ければ早いほど良いといった傾向があり、場合によっては1年前から交渉することもありますが、アメリカは逆で、早すぎるとダメなんです。
彼らは重要な仕事とプライベートの合間の時間で「ここはいけるぞ」と思ったらそこへ視察の予定を差し込むので、3カ月前や1カ月前ではまだ早いかなという感覚です。
Amazonやスターバックスは一般見学も受け入れているので3カ月前に予約しても問題ありませんが、NIKEの視察の際には前日になってようやく決まったこともあるのでハラハラしました。
このほかの事前準備としては、研修参加者が海外に行ったことのない人ばかりならパスポート発行の方法や、アメリカの場合は電子申請によるビザ取得の仕方などを事務局でわかりやすくまとめておくとスムーズです。
海外研修担当者は海外経験豊富な人に任せる
細かいことですが、大きなキャリーケースに身の回りのものを詰められるだけ詰めて持っていこうとする人もいるため、「洗濯機があるから荷物は少なくても大丈夫」などという、生活していく上での情報提供も意外と必要だなと思います。
こういったことを考えると、海外研修を仕切る担当者は海外経験のある人が望ましいでしょう。
言葉が通じないことを心配する人もたくさんいますが、実際に行った社員によれば「行ってしまえば割となんとかなった」という声がほとんど。
むしろしゃべれない人のほうがサバイバル力が身につくようです。
現地の通訳を雇うのもアリですが、こちらがどういう目的で行くのか、どういうルールで研修を進めるかをきちんと伝えた上で綿密に打ち合わせをする必要があります。
そこがうまくいっていないと、意思疎通が難しいことがあるので注意してください。
社内周知をし、バックアップ体制を整えておく
海外研修が内輪だけのもので終わってしまわないようにという意味でも、社内周知は必須です。
うちの場合は企画に着手した時点から募集、出発、帰国まで「今どんなことが行われているか」を社内SNSで発信していくことで会社全体のバックアップ体制が整っていくよう働きかけます。
参加者は平均して1週間程度不在となり、その間は通常の業務に一切手を付けられないので各事業部にバックアップしてもらわないと成り立たないという側面もあります。
間接的なやり方ですが、なかなか重要なポイントだと思っています。
海外研修中は研修に注力させる
研修中は普段の業務から離れて海外体験に没頭してほしいので、通常の業務は一切禁止。
参加者にはパソコンも持参させません。
代わりに現地では何事にも積極的に取り組んでもらうよう促し、過去にはハロウィンシーズンに合わせて仮装している地元の人と写真を撮るミッションを課したこともありました。
これも、日本ではなかなかできない体験から何かを学んでほしいと考えたことです。
このような状態にもっていくためにも、社内で業務をカバーできる体制づくりは必須なのです。
海外研修の目的の設定を行う
社内のバックアップ体制を整えることに並行して、企画の段階ごとに事前オリエンテーションの機会を設けると良いでしょう。
自分で目的を見つける研修であることを参加者に伝える場でもあり、参加者同士が事前に交流する機会にもなります。
そこから自分たちで現地情報を調べつつ旅程の詳細を詰めていく流れになるので、きっかけ作りは事務局側でしっかりとサポートしていく必要があります。
あえて海外で研修をする目的をしっかりと自覚してもらい、何か一つでも将来につながる学びを自ら得てほしいと考えます。
海外研修の振り返りをする
研修終了後にかっちりしたレポートを求めることはありませんが、写真メインで良いので、参加していない人に何をしたかがわかるレポートを提出してほしいというお願いはしています。
SNSでもこういった写真を上げることで、翌年の新卒採用の応募が増えることを期待しています。
海外研修に行ったからといってすぐに実績が上がるなどの効果は期待していませんが、「海外研修に行っただけ」にならないよう、振り返りをしてもらうことは大切だと考えています。
海外研修の目的に即効性はなくても良い!「将来役に立つ」研修を
海外研修は目的を見失うとただの企業見学ツアーになる恐れを含んでいます。
だからこそ、何のために海外研修を実施するのかを参加者それぞれが自覚することが重要です。
海外事情をよく知っている人が海外研修担当者になること、さらにこちらと連携して現地で動いてくれる人が加わると成功率がアップします。
その点で言えば、海外と取引した経験がない企業さんだと自社だけで海外研修を行うのはちょっと難しいかもしれませんね。
当社の海外研修では、すぐに成果が出るようなことはなかなかできません。
その代わり「何か一つは学んでこようと心の中で思いながら行ってね」という気持ちで送り出しています。
学んだ「何か」は、すぐには業務に反映されないかもしれません。
しかし、将来役職に就いたときや業務を任されたときに生きてくる研修なのではと思っています。
ヤマチユナイテッドでは、社員教育に関してさまざまな角度からの取り組みや経営セミナー・イベントをご紹介しています。
スケジュールはホームページでチェックしてみてくださいね。

SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|経営支援事業部|カンパニー長
山﨑 舞
人材総合サービス会社の営業部勤務を経て2018年(株)ヤマチマネジメントへ入社。前職では採用広告サービスの販売営業部で戦略スタッフとして企画・販促・アシスタント業務を担当。その際、元々取引先だったヤマチユナイテッドの社風やミッションに惚れ込み、転職を決意。現在は経営支援事業部で企画・運営を担当しつつ、営業推進チームリーダー兼人財開発コンサルタントとして活動。企業の新卒採用・育成を支援している。
