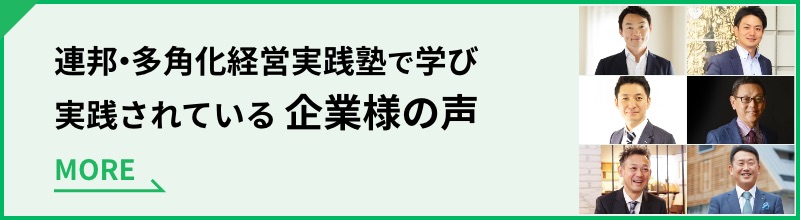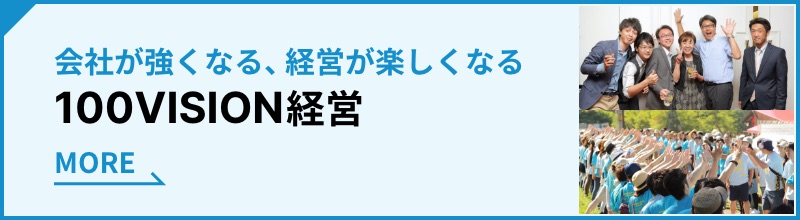中小企業こそブランディングに力を入れるべき理由とは?
ブランディング


こんにちは、ヤマチユナイテッドの山地です。
「ブランディングは大企業が取り組むべきもの」
「経営に余裕ができたら、ブランディングについても考えよう」
中小企業の経営者の中には、このように考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
ブランディングといえば、新聞やテレビにドーンと派手な広告を打つ印象が強いため、そう思ってしまうのも当然かもしれません。
しかし、中小企業こそブランド化が大切です。
特に多角化に取り組む中小企業ほど、ブランディングを強く意識すべき理由があります。
今回は、中小企業の「ブランディング」について考えていきましょう。
目次
- 中小企業におけるブランディングの目的とは?
- 中小企業こそブランディングに取り組むべき理由
- 中小企業のブランディングは既存事業のブランド化から進めよう
- 中小企業でもブランディングは難しくない!既存事業のブランド化からはじめよう
中小企業におけるブランディングの目的とは?
ブランディングの目的は、自社ならではの価値を正しく顧客に伝え、自社のサービスを選んでもらうことです。
同じような商品やサービスでも、ライバル会社のものは売れていないのに、自分の会社のものが売れている場合、その理由は「ブランドが立っている」からだといえます。
そもそもブランドという言葉は、自分の家畜と他人の家畜を間違えないように焼き印を押して区別していたことに由来するそうです。
つまり、競合との違いをシンプルに表現するのが「ブランド」なのです。
具体的にいえば、会社の理念や社風などが、商品やサービスなどと一貫性を持ってつながっていることがお客さまに伝わること。
お客さまはその企業のマークやロゴデザインを見た瞬間に、安心して購入・利用できます。
そうした状態をつくり上げ、維持・進化させていくのがブランディングだといえるでしょう。
中小企業こそブランディングに取り組むべき理由

似たような商品やサービスを扱っているライバル企業がいる場合、お客さまに選んでいただくためには、ブランディングで競合との差別化を図る必要があります。
「ブランディングは余裕のある企業がやるもの」というイメージを持っている方が多いかもしれませんが、十分な資金がなくてもブランディングは行えます。
むしろ、お金のない中小企業こそブランディングに力を入れるべきなのです。
インターネットのない時代はともかく、今では中小企業でもホームページを使って気軽にブランドイメージをつくれます。
ブランディングは、極端なことをいえば名刺1枚からでもはじめられるのです。
会社の理念を決めて、事業のロゴをつくり、名刺やホームページを整備した上で事業活動を続けていれば、「その会社らしさ」がブランドになっていきます。
ブランディングを意識しながら事業を立ち上げていくと、それなりにエッジが立って、ブランドイメージが浸透していくものです。
しかも、中小企業は社員が少ないので、社内にブランドが浸透しやすいというメリットがあります。
これが大企業なら、ブランディングに取り組もうと思っても、簡単にはできません。
広告代理店などに大金を払って大々的にやらなければ、社外はおろか、社内にさえなかなか浸透しないでしょう。
社内にブランドを浸透させることの効果については「ブランディングの効果とは?目的や定義、成功させるポイントを解説!」や「インナーブランディングとは?ミッション浸透の効果や進め方を解説!」で詳しくお話しています。
中小企業のブランディングは既存事業のブランド化から進めよう
新規事業を立ち上げるときも、経営計画と一緒にブランド化について熟考することが大切です。
それ以前に、もし既存のビジネス事業のブランディングができていないのであれば、そこからはじめる必要があります。
既存事業のブランドが明確になっていなければ、新規事業のブランディングもうまくいくわけがありません。
まずは、自社のブランドが現在ユーザーにどのように認知されているかを把握しましょう。
ブランディングの進め方
ブランディングは進め方が重要です。
ブランドを立ち上げる際は、次の順番で進めていきましょう。
- 環境・市場分析
- ブランド戦略の設定
- アウトプットの実施
- ブランド施策の効果測定
それぞれ解説していきます。
①環境・市場分析
ブランディングの基本ステップとして、競合分析や顧客ニーズの把握は欠かせません。
既存のビジネスを分析する方法として、以下のようなものがあります。
- 3C分析:市場環境、競合、自社の領域を分析する
- 4P分析:商品、価格、流通、販売促進の領域を分析する
- SWOT分析:自社製品の強み、弱み、自社にとってのプラスの外的要因、マイナスの外的要因を分析する
これらの分析によって、自社や競合のポジション、自社の強みや弱み、差別化の方向性などを検証できるのです。
ブランディングは「どんなお客さまに売りたいのか」を明確にし、顧客を絞り込む作業でもあります。
②ブランド戦略の設定
市場分析や顧客把握の結果をもとに、競合他社と何を差別化するか、どの顧客をターゲットにするかなどの戦略を練っていきます。
また、ブランドの目指すイメージや、方針などを決定します。
③アウトプットの実施
設定したブランド戦略をもとに、ブランドを表現するのがアウトプットです。
ブランドを表すメッセージや、ロゴのデザイン、フォントなどのビジュアルを策定します。
商品やデザインが決まったら、広告手法や媒体を選定し、情報発信していきます。
④ブランド施策の効果測定
ブランドを立ち上げたら、必ず効果測定を実施します。
当初想定した顧客に届いているか、目標としている売り上げに対してどうかなど検証することが大切です。
さらにSNSでの口コミを確認するほか、専門の調査会社に依頼するなどして客観的な分析を行います。
効果測定の結果をもとにして、ブランドの方向性を変えていくことも必要です。
既存ビジネス事業のブランド化を煮詰めていくと、顧客が絞られることによって事業が研ぎ澄まされ、ブランドが2つ、3つに分かれることもあります。
例えば、当社の住宅会社「ジョンソンホームズ」は、もともと1つのブランドでした。
しかし、お客さまをライフスタイル別、嗜好別に切り分けていった結果、新築住宅事業のブランドが増えていきました。
このように、まったく違う新築住宅ブランドが5つも出来上がり、それぞれが順調に売り上げを伸ばしています。
※2024年5月時点
既存事業をブランディングし直すことで、業績が改善される可能性も高まるはず。
ブランド化の作業は、すなわち多角化を推進する作業でもあるのです。
企業のブランディングについてもっと詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
企業ブランディングの目的とは?連邦・多角化経営との関係も確認
中小企業でもブランディングは難しくない!既存事業のブランド化からはじめよう
ブランディングは、資金に余裕のある大企業が行うものと思われがちですが、中小企業ほどブランディングが大切です。
インターネットが発達した現代では、ホームページやSNSを使って手軽にブランディングができます。
ブランディングの目的は、自社ならではの価値を正しく顧客に伝え、自社のサービスを選んでもらうことです。
中小企業のブランディングは、とてつもなく難しいことのように感じますが、理念やビジョン、顧客層が明確になっていれば、困難なことではありません。
まずは既存事業をブランド化し、社内に浸透させることからはじめてみませんか。
ブランディングについては他にもさまざまな視点からコラムを書いております。
ぜひこちらもあわせてご覧ください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。