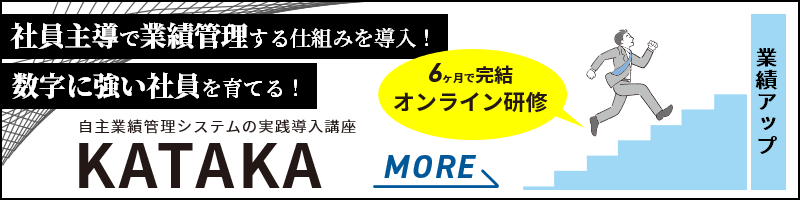良い社風とは?メリットや作り方を解説!「社風経営」で多角化経営の加速化を
多角化・新規事業

こんにちは、ヤマチユナイテッド代表の山地です。
私が考える企業の成功の秘訣として、「多角化」×「システム経営」×「社風経営」という方程式があります。
たとえ優れたビジネスモデルがあったとしても、優秀な人材が揃っていたとしても、社員が楽しく働けない会社が長く続くとは思えません。
経営学者ピーター・F・ドラッカーも「卓越した企業文化は戦略に勝る」という言葉を残しています。
多角化がうまくいくのは、仕事も遊びも楽しむようなポジティブな雰囲気が会社にあればこそ。
今回は、良い社風とはどのような特徴があるのか、良い社風を作るメリットについてお話します。
成功へ導く3つの「良い社風の作り方」についてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

目次
そもそも「良い社風」とは?
社風とは、会社の中で社員が働くなかで作り出す雰囲気のこと。
ただし、そこで働く人の性格や人柄だけが社風を作り上げるわけではなく、ほかにも、その会社の理念や経営者の方針、歴史や文化、会社の評価方式などさまざまな要素が色濃く反映されて、会社の社風ができていきます。
では「良い社風」とは、一体どんなものが挙げられるでしょうか?
当社の場合だと、取引先の方から「ヤマチさんのところは社風が良い」との、評価をいただくことが多くあり、このことは私の自慢の一つになっています。
会社の視察に来られた方からは、「活気がある」「明るい」「社員がのびのび仕事をしている」といった感想をいただくことがあります。
良い社風とは、一般的に「社員同士のコミュニケーションが活発」「不条理な上下関係がない」「社員が意見を言いやすい」といったことが挙げられます。
もし、失敗をひどく叱責するような社風なら、社員は新しいことに挑戦したいと思うでしょうか?
若手社員が上司にモノを言えないような社風なら、提案やアイデアは生まれるでしょうか?
良い社風がある会社は、社員がいきいきとしていて、会社全体が活気に満ち溢れています。
社風を考える上では、ブランディングも大切です。
「中小企業こそブランディングに力を入れるべき理由とは?」では、中小企業で大切にしたいブランディングの考え方と実践方法をご紹介しています。
良い社風を作るメリット
良い社風を作ることは、会社にとってどのようなメリットをもたらすのでしょうか。
良い社風を作るメリットには、以下のようなものがあります。
-
離職率が下がる
-
仕事の生産性が上がる
良い社風であるということは「会社の雰囲気が良く、仕事が気持ち良くできる」ということです。
社員が持てる力を十分に発揮できる環境であれば結果も出やすく、仕事へのやりがいも感じやすいでしょう。
仕事へのやりがいがモチベーションとなれば、前向きな考えを持つ社員によってさまざまなアイデアが出ることも少なくありません。
会社全体が良いサイクルで業務を進めていけるようになり、仕事の生産性が上がりやすくなります。
仕事の結果が出やすくやりがいを感じやすい職場なら「ここでもっと頑張るぞ」という気持ちになりやすく、長く働いてくれるようになるでしょう。
「楽しくなければ、うまくいかない」という考え方が良い社風へつながる
私は、経営(仕事)は「楽しくすればうまくいく」とは限らないが「楽しくなければ、うまくいかない」と考えています。
これが一番の基盤となり、良い社風へつながると信じています。
仕事や職場が楽しければ、社員のモチベーションは向上し、おのずと生産性が上がります。
社員がポジティブになれば、新しいアイデアやチャレンジもどんどん湧いてくるでしょう。
反対に、失敗を恐れるようなネガティブな職場なら、新規事業を立ち上げるのは困難です。
経営者が軽視しがちな「社風」こそが、成功するための重要なファクターなのです。
こちらのコラムもあわせてご覧ください。
理念経営とは?「楽しく儲かる社風」をつくるヤマチユナイテッドの事例
仕事と人生を楽しむためのヒント!経営がうまくいかないときの楽しみ方
成功へ導く3つの「良い社風の作り方」

成功へ導く「良い社風の作り方」は、大きく分けて3つのポイントがあります。
①経営者自身が明るく楽しい雰囲気を演出する
良い社風を作る最低条件は、まず経営者が明るく楽しそうにしていることです。
「社風」とは、一言で説明するなら会社の空気です。
誰かの発する雰囲気がほかの者へと伝播し、いつのまにか空気が形成され、それが定着して社風となります。
経営者がいつも難しい顔をしていたら、ピリピリとした雰囲気が蔓延して、まわりの社員も笑顔になれません。
社員が自由に発言したり、提案したり、新しい発想を生み出すことも、もしかしたらなくなってしまうかもしれません。
まずは、トップ自ら楽しそうに仕事をすることから始めてください。
形だけでも良いので「楽しい」というキーワードを口に出すように決断・行動してほしいのです。
例えば、朝礼では小言をやめ、笑顔でポジティブな発言をすることをおすすめします。
私の場合だと、会議でダメ出しをするときも「その経営計画は楽しくないな」「もっと楽しくなるように考え直してよ」と言います。
「良い・悪い」といった尺度ではなく、「楽しいか・楽しくないか」でモノを見てみることがポイントです。
社風を一朝一夕に変えるのは容易ではありませんが、少なくともトップが上機嫌でいれば、その姿勢は経営幹部へ、そして現場の社員へと次第に伝播していくはずです。
②コミュニケーションは「ほめる」が基本
「楽しそうに仕事をする」といっても、部下の失敗は放っておけません。
部下をガミガミと叱ってしまう方もいるでしょう。
でも、叱ってばかりだと部下が萎縮して、新しいことにチャレンジする気は失せてしまいます。
ときには厳しく叱るのも愛情ですが、私はコミュニケーションの基本を「ほめる」ことに置いています。
ほめるには、相手を普段から知り、良いところにフォーカスする必要があります。
良い面を見ようと心掛けると、物事を前向きにとらえるクセがつき、社員との向き合い方もポジティブに変わるのです。
当社には、部下をむやみに叱りつける上司はほとんどいません。
のびのび仕事ができれば、社員も明るく積極的になります。
部下に「失敗しました!」と笑顔で報告されると、内心は穏やかではありませんが、顔に出すことなく「ナイス、失敗!」「一緒に取り返そう!」と言えるくらいになれれば理想的です。
ほめることにコストはかかりません。
良い社風を作りたいなら、「ほめる」をコミュニケーションの基本に位置づけることをおすすめします。
③「社風改革」として組織全体で取り組む
当社では、社員の側からも社風改革として、組織全体で社風作りに関わってもらいます。
中心になっているのは「社風向上委員会」です。
仲間をほめること、笑顔でいることの大切さを啓発するポスターを作って社内に掲示する活動を行なっています。
折に触れて目にすることで、日頃のコミュニケーションを意識するきっかけになっているのではないでしょうか。
また、業務を1日休んで行う運動会などといった社内行事や、「グッド&ニュー」をテーマにした朝礼での社員スピーチなども、良い社風作りに一役かっています。
こうして社内に根付いた良い文化は、お客さまや取引先にも伝わります。
何度も言うように、社風は空気です。
社員があちこちへ運ぶことでどんどん伝わり、広まっていきます。
良い社風が定着すれば、社員の定着率が高まります。
明るく前向きな社風に惹かれて、似たような雰囲気の人材が集まってくるので、採用力もアップするでしょう。
事業や会社によって社風に大きな差がなくなれば、グループとしての一体感も高まるはずです。
私が成功の方程式に位置づけている「システム経営」×「多角化経営」×「社風経営」。
そのうち、前者の2つはあくまでも仕組みですが、最後の「社風経営」は仕組みであると同時に社員の精神であり、会社の精神となりうるものです。
仕組みを駆動していく際に欠かせない「エンジン」だと考えています。
良い社風とは、社員がいきいきしていて会社全体が活気に満ち溢れていること
社風とは、会社が持つ独自の雰囲気のこと。
社風は長い時間をかけて醸成されるため、一朝一夕では変えられません。
良い社風の会社は、社員がいきいきとしていて、やりがいに満ち溢れています。
良い社風が作られていれば、社員が定着し、離職率の低下につながります。
また、社員のモチベーションが上がるので、会社全体の生産性もアップするといったメリットもあります。
良い社風を作るためには、まずは経営者自身が明るく楽しい雰囲気を演出しましょう。
楽しいからといって必ずしもうまくいくわけではありませんが、楽しくなければうまくいくことはありません。
コミュニケーションの基本はほめることに徹し、社内の雰囲気を良くすることに重点を置きましょう。
そして、「社風を変えよう」「社風を良くしよう」と会社全体で取り組むことも大切ですよ。
良い社風は社内外に伝播し、多角化経営にも良い効果をもたらすでしょう。
ヤマチユナイテッドでは、当グループの経営ノウハウを詰め込んだ経営セミナー・イベントを開催しております。
興味があるイベントがありましたら、ぜひご参加ください!
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。