人材定着につながる施策とは?成功事例に学ぶ「会社を好きになれる経営」
採用・育成


こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。
「評価制度も面談制度も整えた。福利厚生も充実させている。なのに、なぜ社員は辞めてしまうのか?」
これは、多くの経営者が抱える共通の悩みではないでしょうか。
人材獲得競争が激化する中、コストをかけて採用した優秀な人材が定着しないことに頭を悩ませている企業は少なくありません。
待遇や制度を整備すれば人材定着につながると考えがちですが、制度を生かすも殺すも、その背景にある「経営の姿勢」や「会社の価値観」次第なのです。
今回のコラムでは、制度の背景にある人材定着の本質と、社員が「この会社で働き続けたい」と思える環境作りの基本的な考え方を、実際の事例とともにご紹介します。
読み進めていただくことで、「制度はあるのに人の心が離れている」状態から脱却し、社員が「この会社で働き続けたい」と思える組織づくりのヒントが見つかるはずです。
目次
- 制度は整えた。でも、人は辞める...その違和感の正体とは?
- 人材定着を高めるための施策とは?制度だけでは定着しない理由も
- 【ヤマチの人材定着の事例】制度×想い=社員が残りたくなる会社
- 制度と経営姿勢の融合で人材定着を解決!ヤマチの成功事例を参考に
制度は整えた。でも、人は辞める...その違和感の正体とは?
多くの企業が人材定着に向けてさまざまな取り組みを行なっています。
しかし、評価制度の整備、社員調査の実施、定期的な個別面談、キャリア支援制度の充実など、「従業員を大切にする制度」を導入しているにも関わらず、離職率が改善されないと頭を悩ませている企業も少なくありません。
制度を整えているのに人が辞めてしまう。
その背景には、制度と人の心がつながっていないという根本的な問題があります。
制度は社員を大切にしたいという想いの表れであり、キャリアを真剣に考えるために設けられているものです。
さらに、会社にはビジョンや理念、目指している目標があり、それを補完するための各種制度であるはずです。
しかし、ここがつながっていない、もしくはそもそもの理念やビジョン、目的が明確でないと「何のための制度なのか」という制度の軸がない状態になってしまいます。
会社との共感、「この会社はこうなりたくて、そのための制度である」というつながりが見えなければ、制度がいくらあっても満足度は高まりません。
制度と人の心をつなぐためには、会社のビジョンや方向性との一貫性が不可欠なのです。
制度があれば必ず人材が定着するというわけではありません。
制度が最大の魅力なのであれば、もっと良い制度を持つ会社に人材が流れてしまう可能性もあります。
また、他社で良いと想われた制度を導入したとしても、それが自社に適合するかは別問題です。
人材定着を高めるための施策とは?制度だけでは定着しない理由も

人材定着を高めるための一般的な施策として多くの企業が取り入れている制度には、主に以下のようなものが挙げられます。
- 賃金制度の拡充:基本給の見直しや賞与制度の充実
- 福利厚生の充実:健康保険、住宅手当、食事補助など
- 1on1面談:上司と部下の定期的な個別面談
- キャリア支援:資格取得手当、研修制度、資格取得補助
- 従業員満足度調査:定期的なアンケート調査の実施
- 評価制度:明確な評価基準と昇進・昇格の仕組み など
これらは確かに重要な制度であり、ヤマチユナイテッドでも積極的に取り入れています。
しかし、制度を整えただけでは期待した効果を得られないのが現実です。
その理由は、制度だけがあって目的や方向性につながっていないケースが多いからだと考えられます。
制度はあくまでもツールに過ぎません。
道具を生かすのは「会社の姿勢」、つまり何に向かっているのか、どのような価値観を共有しているのかという部分です。
経営者の想いや姿勢が明確に伝わらない限り、社員の心は動きません。
社員が「何に向かって頑張ればいいのか」「会社は自分たちのことをどう考えているのか」を理解できて初めて、制度が生きた仕組みとして機能し始めるのです。
人材定着を高めるための施策について詳しく知りたい方は、こちらのコラムもぜひご覧ください。
中小企業における昇進・昇給(賃上げ)のタイミングは?人材定着に結びつける方法も確認
従業員満足度(ES)向上のための取り組み事例やメリットを紹介!
従業員満足度(ES)調査の目的とは?質問項目や分析方法を解説
【ヤマチの人材定着の事例】制度×想い=社員が残りたくなる会社
そもそも、「制度があるから辞めない」のではありません。
「自分の仕事に意味を感じられるから残る」のです。
人材定着を実現している企業の社員は、報酬や待遇よりも、会社における「自分の居場所」や「会社への信頼」を重視している傾向があります。
特に中小企業では、一人ひとりの影響力が大きいため、制度や仕組みを通して自己重要感や自己肯定感を感じやすい環境を作っていく必要があるでしょう。
中小企業が報酬や待遇で大企業に勝つのはなかなか難しいため、それ以外の価値観を醸成していくことが重要です。
また、制度や仕組みの整備と並行して、以下の要素も人材定着に直結します。
- 経営理念の浸透:会社の考え方や取り組みへの共感
- 経営層の言葉や態度:一貫性のある行動と発言
- 部門長の関係構築力:スタッフとのコミュニケーションと方針の共有
制度が機能するのは、会社の考え方や取り組みに対する共感が生まれてからです。
そのため、経営層は継続的に理念の浸透やビジョンの共有に取り組み、自らの態度や姿勢、コミュニケーションを通じて、社員との信頼関係を構築していく必要があります。
「この会社で一緒に未来をつくっていきたい」と思わせられるかどうかが経営の真の力量なのです。
人材定着に貢献するヤマチの具体事例
ヤマチユナイテッドで実際に効果を上げている具体的な制度の事例をご紹介します
事例①:チャレンジを支える評価制度
ヤマチユナイテッドでは、新規事業や新規プロジェクトに挑戦して結果的に失敗に終わっても、「ナイスチャレンジ! ナイストライ!」という評価を受けます。
失敗そのものがマイナスの評価になることは一切なく、人事や給与面での不利益も発生しません。
新規事業が赤字でスタートすることや、市場環境の変化で撤退や中止を余儀なくされることもありますが、チャレンジした社員が責任を追及されることはありません。
この評価制度の背景にあるのは、ヤマチユナイテッドの「THE100VISION」=「100の事業を作る」という大きなビジョンとの一貫性です。
この目標を実現するためには、チャレンジを評価し、失敗を恐れずに挑戦できる環境の整備が不可欠なのです
もし「新規事業を増やしたい」と掲げながら、新規事業で失敗した社員の評価を下げるような制度だったら、誰もチャレンジしなくなってしまいます。
言葉と行動、制度と会社の方針の一貫性こそが、社員の積極的な行動を促す原動力となっているのです。
実際に、この制度により社員の新規事業提案が活発化し、現場からのアイデアが次々と新しいプロジェクトとして実現されています。
事例②:経営参加としてのモラルサーベイ
ヤマチユナイテッドでは、モラルサーベイ(従業員満足度調査)を単なるアンケートではなく、「経営参加の一つ」として位置づけています。
最も特徴的なのは、あえて記名式で実施している点で、これは「責任を持って意見を発信してほしい」という前提があるからです。
記名式にすることで、発信する側(社員)も責任を持って意見を述べ、受け取る側(経営陣)も真剣に受け止めるという、相互に責任ある関係が構築されています。
サーベイを通じた意見参加により、社員の当事者意識を育てるとともに、出てきた声には必ず真摯に対応します。
調査結果は幹部層で共有され、全体会議や経営会議で詳細に協議されます。
サーベイで明らかになった課題を現状認識として全社で共有し、具体的な社員満足対策や制度改善に活用しているのです。
もちろん、時として経営陣にとって耳の痛い声が上がることもあります。
実際に、上司との関係性に問題があるという指摘が複数寄せられた際には、詳細な調査の上で、上司を交代させたケースもありました。
また、情報共有や伝達方法に課題があると判断した場合には、該当する上司に対して教育的指導を実施するなど、具体的な改善策を講じています。
このように、モラルサーベイを形式的なアンケートで終わらせるのではなく、会社をより良くするための実効性のある経営参加の仕組みとして機能させています。
業績情報のオープン化とあわせて、現場からの意見が新しいプロジェクトとして実現される環境を整えることで、社員の経営参加意識を高めているのです。
制度の本質は関係性の構築
これらの制度に共通する本質的な目的は「関係性の構築」であり、「会社に対する信頼と愛着」そして「当事者意識」を育てることです。
意思表示や意見参加を通じて、社員が組織やチームに対して実際に影響力を発揮できる仕組みを作り上げています。
重要なのは、形だけの制度運用では意味がないということ。
明確な方針があり、その背景に具体的な目的やビジョンがあって、それに則った制度設計がなされて初めて、制度は本来の機能を発揮します。
社員が会社に「誇り」を持てるようになると、制度の枠を超えた自発的な定着が起きます。
これこそが、真の人材定着の本質といえるでしょう。
単に「辞めない」のではなく、「この会社でもっと貢献したい」「この会社と一緒に成長したい」と心から思える状態を創り出すことが、持続可能な人材定着戦略なのです。
社員の本音を引き出し、真摯に向き合う姿勢については「「本音を言わない部下」の本当の理由は?会社が強くなるには聞く器が重要」でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
【資料プレゼント】ヤマチユナイテッドが実際に使用している「自己申告書」フォーマットをぜひご活用ください!
人材定着の取り組みをさらに具体化したい方は、自己申告書をご活用ください。
ヤマチユナイテッドの自己申告書フォーマットは、こちらからダウンロード可能です。
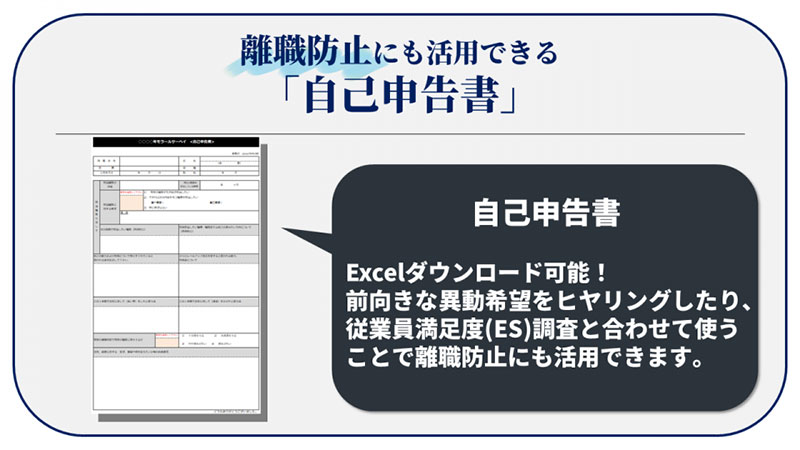
従業員満足度(ES)調査とあわせて使うことで、社員の気持ちを把握していくことができます。
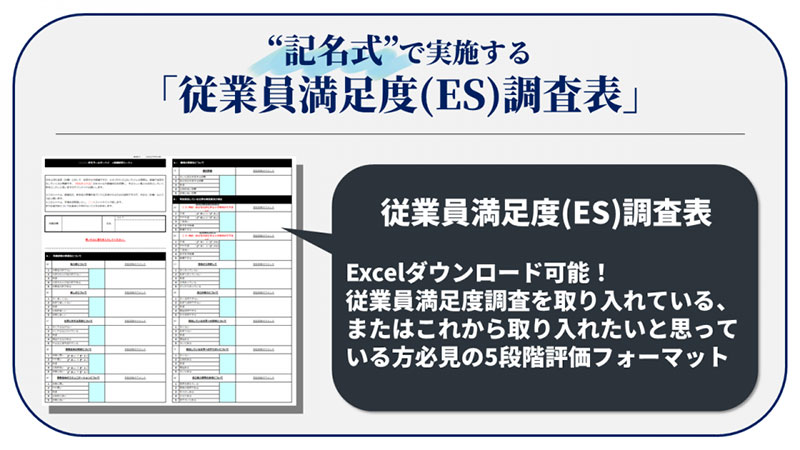
"記名式"で実施する「従業員満足度(ES)調査表」フォーマット
制度と経営姿勢の融合で人材定着を解決!ヤマチの成功事例を参考に
人材定着を実現するには、制度の整備だけでは不十分です。
制度と経営の想い、そして会社のビジョンが一体となったときに、社員が「この会社で働き続けたい」と心から思える環境が生まれます。
制度はあくまでもツールであり、それを生かすのは経営者の姿勢と一貫した行動です。
社員が自分の仕事に深い意味を感じ、会社への信頼と愛着を持てるような組織作りこそが、持続可能な人材定着を実現する唯一の道なのです。
ヤマチユナイテッドで取り入れている制度は、全て会社のビジョンや理念と一貫した設計がなされています。
経営陣が社員の声に真摯に向き合い、制度を関係性構築と信頼醸成の手段として活用することで、社員の当事者意識と会社への誇りを育んでいます。
人材定着の課題を抱える企業においては、まず自社のビジョンや理念を明確化し、それと既存制度の一貫性を徹底的に見直すことから始めることをおすすめします。
そして何より重要なのは、経営者自身が制度の背景にある想いを、日々の言動を通じて社員に伝え続けることです。
人材定着の課題を抱える企業は、まず自社のビジョンや理念を明確にし、それと制度の一貫性を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。
制度と経営姿勢が融合したとき、人材定着という課題は解決に向かうはずです。
ヤマチユナイテッドでは、離職防止にも活用できる「自己申告書」フォーマットを公開しています。
こちらのページからダウンロードしていただき、ご活用ください。
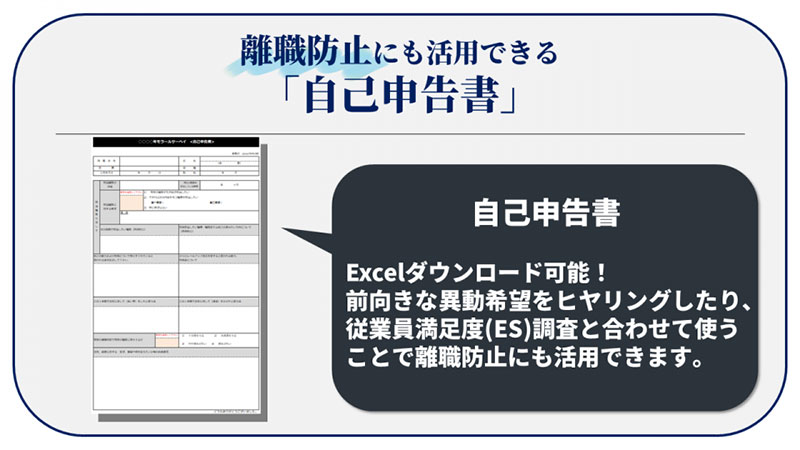
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員
石崎 貴秀
1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。
連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。
入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。

