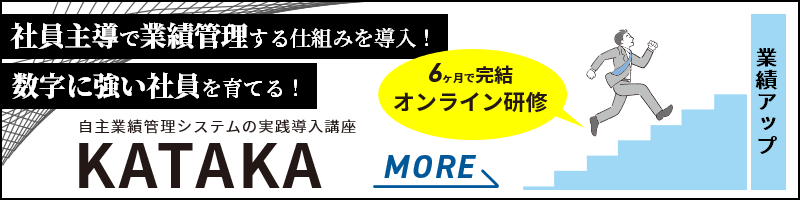業績を上げる組織に不可欠な「型化」とは?自律的に成長する企業の作り方も
業績管理・経営計画


こんにちは。ヤマチユナイテッドの山﨑です。
「業績が伸びない」「伸びても持続しない」「社員が指示待ちで、自発的に業績を作る動きが生まれない」
経営幹部として、これらの悩みを抱えている方は非常に多いのではないでしょうか。
特に中小・中堅企業においては、限られた人員の中で業務の属人化が目立ち、「業績を上げられる人と上げられない人との間に差がついてしまう」という話をよく耳にします。
そこで、業務の標準化を図りたいところですが、仕組みづくりにどこから手をつけたら良いか分からず、つい先延ばしになっている方もいらっしゃるかもしれません。
経営者が関与しなくても、社員が自ら業績を上げ続けられる組織を目指すなら、今回のコラムでご紹介する「型化」をぜひ取り入れてみてください。
目次
- なぜ業績が安定しないのか?組織の共通課題から確認
- 継続的に業績を上げる組織に不可欠な3つの「型化」
- 社員が自ら業績を上げるには?自律的に成長する企業に変えるステップ
- 社員自ら業績を上げる組織に成長するには「型化」の導入がおすすめ!
なぜ業績が安定しないのか?組織の共通課題から確認
業績が安定しない組織には、いくつかの共通課題があると思います
トップダウン依存の組織になっている
私たちがコンサルティングしている企業様のお話を伺うと、ある程度のビジネスモデルは確立されているケースが多くあります。
しかし一方で、業績を作っていくための戦略立てや、PDCAを回して対策を打つという業績管理の実行を、現場の社員が自律的に行う体制になっていない状況が見受けられます。
これらの業績づくりを誰が担っているかというと、経営者、あるいは常務、専務といったトップ層が自ら業績を作る役割を担っていたり、実際の戦略立てから業績管理、さらには対策の実行までを一手に引き受けていらっしゃる場合があります。
これが、いわゆる「トップダウン依存の組織になっている」状態です。
その結果、次のような課題が生じます。
-
経営者が指示を出さないと社員が動かない
-
戦略立案や業績管理が社長任せになっている
幹部や現場の社員は経営者が指示を出さないと動けず、戦略立案も業績管理も社長任せ。
単一事業ならまだしも、事業が多角化している企業では、経営者がこれらの役割を一手に引き受けるのであれば、対応が追いつかないこともあるのではないでしょうか。
そうすると、戦略が現場に浸透して実行されるまでにタイムラグが発生して、スピード感を持った経営が難しくなってしまいます。
戦略が現場に浸透しない・社員に伝わらない理由
現場の社員は上から降ろされてくる戦略を受け身で待っているだけになりがちです。
そのため、経営者の考えに対する理解度にばらつきが生じ、戦略が浸透しづらい問題も発生します。
経営者の皆さまとしては、考え抜いた結果立てていらっしゃる戦略のはずです。
その戦略には納得度、重要性、取り組むスピード感も意識されているでしょう。
しかし、待ちの姿勢が体質化している社員には戦略の背景が伝わらず、感度が磨かれていない状況です。
スピード感も濃度も高く、かつ責任感を持って実行できる社員がそもそも少ない状態なので、業績が安定しないのも当然だと考えられます。
こちらのコラムもご確認ください。
経営層と現場でなぜギャップが生まれる?戦略をやり切るためのポイント
進捗管理や業績管理の仕組みがない(または属人的)
売れている企業でも進捗管理や業績管理の仕組みを持たない企業は意外と多く、逆に言うと、売れているからこそ、そのような仕組みにまだ必要性を感じていらっしゃらないのではないでしょうか。
仕組みがないと、次のような課題が生じます。
-
数字の結果だけを見て、プロセスの管理が弱い
-
PDCAが機能していない
この背景には、主に2つの原因があります。
①管理を受け持っているのが経営者自身である
②戦略立てと方針策定はできても、現場の行動管理まで手が回っていない
「数値で会話できるか」がカギ
進捗管理、業績管理で最も重要なのは、数値で会話ができるかどうかです。
当グループでは、数値で見て、数値で分析し、数値に沿った対策立案をすることを数年前から実践しています。
同じ「数値で見る」のでも、「数字の結果」だけを見ていてはいけません。
プロセスを数値で管理することが重要なのです。
一般的には、経験値の高いベテラン社員ほど、この部分を数値ではなく感覚で判断する傾向があるかもしれませんね。
これまでの実績があるだけに、主観や感情に基づいて「今までの感じでいけば、これで結果を出せるだろう」と考えてしまうのです。
こうなるとプロセス管理はかなり属人的になってしまいます。
仮にうまくいったとしても、その手法に再現性もなければ、案外根拠が不明確なことも少なくありません。
管理の仕組みがなければ、トップ層が担うしかない
プロセス管理においては、実行と振り返りの仕組み、もっと言うと会議や打ち合わせ、ミーティングと紐付けることが重要で、そこに注力すべきです。
ところが、そもそも管理の仕組みがないために社員に任せられず、経営者、常務、専務といったトップ層が全部担っていて、結果的に改善が遅れてしまう環境になっていないでしょうか。
「社員に任せられない」のは、経営者が事業計画や戦略に込めた思いに対して社員の感度が上がっていない、だから「自分たちでやるしかない」となってしまうのだと思います。
他社の経営幹部の方々からよくお聞きするのが、「僕は言っているんだけどね」という言葉。
それなのに「社員が動いてくれない」「動きが遅い」とお困りなのですが、社員の感度が低い以上、感度の高いトップ層が属人的な管理を担うしかないのが実情です。
業務フロー・プロセスが標準化されていない
先ほどの例より少し進んだ会社なら、週次とまでいかずとも、月次の業績を出す体制はできているでしょう。
しかし、思うように伸びてこないとなると、次のような原因が考えられます。
-
成功パターンが属人的で、共有されていない
-
ミスや非効率が繰り返される
業績管理の精度をより高め、生産性を上げて「業績をアップさせよう」とブラッシュアップを図るのであれば、次は誰でも同じように実績を残せるようなフロー作り、プロセス作りに臨むべきです。
重要なのは、成功パターンを「型化」する、いわゆる標準化すること。
そして、成功事例のいち早い情報共有が非常に大事になってきます。
「売れる人だけが売れる」状態から抜け出せない
成功事例が現場でブラックボックス化されている状況では、「一部の人は売れているけれど、一部の人は売れない」のも仕方ないでしょう。
しかも、売れている人は営業スタッフの中でも一握り。
間接部門でも同様で、ハイパフォーマーが1人か2人いるだけ、というケースが多いですよね。
他のメンバーもハイパフォーマーの6割〜7割の力が付いてくれば、組織全体の生産性は上がるはずです。
しかし、フローやプロセスが標準化されていないがゆえに、いつまでもハイパフォーマーに頼ってしまってはいないでしょうか?
ハイパフォーマー依存は、会社にとって非常にリスキーですよね。
ハイパフォーマーが明日にでも辞めてしまうかもしれないし、そうでなくとも、病気や家庭の事情などでやむを得ず休職するケースも実際によくお聞きします。
場合によっては引き継ぎもままならず、残されたメンバーが「あの人はどうしていたんだろう」「あの人のノウハウって何だったんだ」と、右往左往することにもなるでしょう。
その方の能力やセンスが高ければ高いほどダメージは大きいですし、もしかすると会社の存続に関わるくらいの影響もあるかもしれません。
さらに、そのノウハウは急に誰もができるものでもなく、その方が何十年もかけて構築したものも多いです。
つまり、残された人が実質的に同じことができるような形で会社に残していくためには、また数年、数十年かかる可能性もあるのです。
「標準化したい」はずなのに、動き出せない現実
「業務の標準化をするべき」ということは誰しも分かっているはずですが、なかなか踏み出せないのも事実。
でも、有事に直面してから慌てるのでは遅いのです。
有事でなくとも、業務が標準化されていなければ、日々の中でミスや非効率が繰り返し発生する不具合が想定されます。
そもそも、成功パターンのロジックが明確になっていないから、ミスや非効率がなぜ発生するかわからない。
だから、また繰り返してしまうのです。
こうなると、経営層が対策を打って問題を潰していかなければなりません。
あっちの事業部が一段落したら、次はこっちの部門...と、モグラ叩きのような状態になるのは目に見えています。
この状況では、経営層が本来取り組むべきレベルの高い業務になかなか着手できず、場当たり的になってしまうのではないでしょうか。
そして、やはり最終的には業績が上がらないことになってしまうのです。
共通の課題を解決するには?
業績が伸び悩んでいるとお悩みの皆さんには、共通の課題にいくつか思い当たる点があったのではないでしょうか。
こうした課題を解決するには、組織内のメンバーの誰もが同じレベルで業務をできる状態をつくることが重要となります。
そのために欠かせないのが、業務フローやプロセスを統一する「業務標準化」です。
業務標準化のメリットについては、こちらのコラムで解説しています。
業務標準化のメリットとは?個人的なスキルに頼らない仕組みづくり
「では、今から業務標準化に取り組みましょう!」ということで、ヤマチユナイテッドが実践してきた業務の「型化」について、次の項目でご紹介したいと思います。
継続的に業績を上げる組織に不可欠な3つの「型化」

業績を上げる方法の一つとして、例えば、業績管理が得意な人や戦略立案のセンスがある人をヘッドハンティングしてくる手段もあるでしょう。
しかし、いかに優秀であろうと、1人や2人でできることは限られてきます。
また、ハイパフォーマーがいかに優れた戦略を立てたとしても、その意図を現場が同等あるいは近いレベルで理解し、実行に移せないのであれば、戦略を生かしきることができません。
ネット上でどんどん売れ続けるような事業であれば問題ないかもしれません。
しかし、有人で売っている商品・サービスであれば、戦略に対する現場の理解度・納得度を高めることが不可欠です。
どんなに良い人材を採用しても、すばらしいコンサルタントを入れても、現場に再現性のある仕組みがなければ大きな効果は望めません。
そこで、業務標準化=業務の「型化」に着手していただきたいのです。
「型化」によって、誰でもできる、かつ効果の高い方法で業績を上げていくことが可能となります。
業務の「型化」は、大きく3つに分けて考えましょう。
- ①業績管理の型化
- ②進捗チェックの型化
- ③業務フロー・プロセスの型化
ただ業績が上がるのでなく、組織として成長し続け、社員が自分たちで継続的に業績を上げていく組織になるためには、これら3つの「型化」が欠かせません。
①「業績管理の型化」で、目標を確実に達成する
<POINT>
- 「数値 × 行動」で業績を管理する
- KPIを明確にし、業績向上の再現性を高める
- 定期的なレビューで、数字の根拠を理解し、戦略を修正する
業績管理はKPI設定から始める
業績管理の型化を進めるにあたって、幹部層の皆さんにお願いしたいのは、業績を出すために社員に取り組んでもらうことを決めるところからスタートすることです。
業績管理は、「数値 × 行動」によるKPIの設定が効果的です。
KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要達成指標(重要業績評価指標)」などと表現されます。
ここで最も重要なのは、現場の社員に自分たちでKPIを設定させる点です。
KPIという言葉を使うと「レベルが高く難しいことをしなければならないのではないか」「うちの社員には難しい」「任せられない」と尻込みする方もいらっしゃるかもしれませんが、何も難しいことはありません。
KPIは「年間目標を達成するために中間目標として設定された具体的な数字」と言い換えることもできます。
皆さんの会社でも、年間の営業利益目標を設定し、半期・四半期で達成率をチェックするなど、目標達成のため日々努力されていると思います。
そのチェックの頻度を増やして精度を高め、より確実に目標達成へ向かっていくための手がかりとして、KPIを使っていただきたいのです。
「数値 × 行動」のイメージ
仮に飲食業で年間の営業利益目標を立てたとしましょう。
それを達成するためのKPIは、例えば以下のように、具体的な数字を設定します。
- 客単価:〇円
- 予約件数:〇件/月
- FL比率(売り上げに対する食材費と人件費の割合):〇%
これが「数値✕行動」の「数値」の部分です。
「行動」は、KPIを達成するために業務内ですべきことを具体的に挙げて実行することを指します。
例えば、客単価を目標値まで引き上げるためには、以下のような具体策になります。
- 新メニューを月に◯品増やす
- 顧客アンケートの分析を月に◯件行う
「型化」を効率的に進めるためには?
「型化」を効率的に進めるためには、書類のフォーマットなども全社共通で用意しましょう。
ヤマチユナイテッドでは、業績管理において「部門方針書」を活用しています。
「部門方針書」は、A4用紙1枚のシンプルな作りですが、次の項目が一目でわかるようになっています。
- 年間の営業利益目標に対して設置したKPI
- 現状、課題、対策
まずはこれに沿って、週次で進捗管理を行うのです。
「部門方針書」の作り方・使い方はこちらのコラムでご紹介しています。
部門方針書とは?例文とともに作り方や効果的な活用方法を解説!
社員に任せる・考えさせることが成長につながる
KPI達成のための行動設定には、少し時間がかかると思います。
社員に任せるとなると、経営層の方々から見て「いやちょっと違うな」と思う内容も出てくるでしょう。
でも、最初から正解パターンを与えるのと、自分たちで考えさせるのとでは、効果やその後の成長度合いに雲泥の差が付きます。
最初から精度の高い内容にするのは難しくて当然です。
ただ、やることは明確で、まずは部門方針書を埋めてもらう。
そしてそれに沿って、デイリー、ウィークリーで「どこのお客様に◯件、このような活動をした」と、KPIの数値を毎日自分たちで拾いながら管理してもらう。
そうすると、社員同士がもう数字で会話できるようになります
幹部層の役割とは?
幹部層の皆さんにおいては、部門方針書の他に、管理帳票も共通のものを作るなど、枠組みを整備・用意することをおすすめします。
それによって「部門方針書を埋める」→「KPI達成のための行動を実行する」→「毎週数字を拾って年間目標達成に向けて微調整する」という「業務管理の型」が確立し、社員だけでも実行可能となるはずです。
②「進捗チェックの型化」で、計画の実行度を上げる
<POINT>
- 「計画→実行→結果→改善」のサイクルを高速で回す
- 進捗を定期的に可視化し、問題を早期発見・修正する
- 計画と実行のズレを早い段階で修正し、確実に目標達成へ導く
「PDCA」のサイクルを高速で回す
「計画→実行→結果→改善」は、いわゆる「PDCA(Plan・Do・Check・Action)」と呼ばれるフレームワークですね。
進捗チェックは、ただやれば良いものではありません。
チェックした結果を共有し、定期的に可視化することが問題の早期発見と早期解決につながります。
また、計画と実行とのズレが小さいうちに対策を打てるので、目標達成の確実性が高まります。
会議の精度を向上させるには?進行方法も確認
計画の実行度を上げるために重要なのが、会議です。
当グループのコンサルティングのお客様からよく出てくるのが「現場の社員が会議で出してくる対策が良くない」という声です。
「会議の時間が長い割に、上がってくる報告は数字だけ言って終わり。その数字も悪いのに対策がブラッシュアップされない」という不満もよく聞かれます。
そう思ってしまうのは、会議の精度がまだ低いのが原因ではないでしょうか。
つまり、会議の場で聞く、発表する、思考するといった「中身」を充実させる必要があり、もっと言えば、「進捗チェック」と「会議」とを掛け合わせて設計する必要があると思うのです。
となると、アジェンダにこだわるしかありません。
会議の場で何を聞くのかを精査し、資料を配布するなら会議の前に用意して、各自で目を通しておいてもらうようにすることで、会議の間延びを防げます。
報告者に対して求めるべき内容は、現状はどうか、目標値に対して数字が足りているのか・いないのか、足りていないなら原因は何か、どのような対策を打ってみようとしているかという報告です。
「一発で当たる対策を持ってこなきゃならない」と考えるとなかなか難しいので、トライ&エラーで良いのです。
会議を改善する意識は、長い目で見るつもりで進めよう
中小・中堅企業においてはリソースも限られ、日々の業務にも追われがちで、いきなり「完璧な会議」の設計ができるところは少ないでしょう。
私たちの業務管理もそうですが、「やりながら良くしていこう」「精度を高めていこう」という意識で進めていって問題ないと思います。
特に当グループでは、自分たちで考えさせることが幹部候補の育成にもつながっているので、長い目で見るつもりで取り組んでいます。
進捗チェックの頻度
進捗チェックの頻度としては、週次がベストです。
私たちの場合は、週次、月次、クォーターと、それぞれのタイミングで振り返りを行なっています。
③「業務フロー・プロセスの型化」で、再現性のある成果を生む
<POINT>
- 業務プロセスを可視化・標準化し、誰でも成果が出せる状態を作る
- PDCAを回しながら業務を進化させ、組織全体の生産性を向上させる
業務フロー・プロセスの型化
業務フローやプロセスに関しては、マニュアルを作っている会社もあると思います。
しかし、時間とともに内容が古くなりますし、「誰が作るの?」「誰が修正するの?」という点でつまずいてしまうケースも多々あるようです。
確かに、業務のフロー・プロセスは一度決めて終わりではないですよね。
産みの苦しみだけで済むなら「ここだけ頑張ろう」と思いますが、マンパワーや時間を割いて取り組んでも、その後ずっと通用するわけではありません。
継続的に見直しをかけるとなると、さらに面倒になるのもわかります。
ですから、経営者がやらず、現場の社員に任せることがおすすめなのです。
「業務フロー・プロセスの型化」においては、まず皆さんで話し合う機会を設けましょう。
プロセスに関して、業績を上げている人が普通に取り組んでいることが、他の人にとって「あ、そんなことやってるんだ」という発見や気付きになることは案外多いです。
しかも、それが明日から誰でも真似できることだったりするんです。
業務フローやプロセスをしっかりと共有し、「誰でもできるね」と意識することが大事なポイント。
このプロセスを「型」にして、ブラッシュアップしていくのです。
再現性のある「型」を進化させる
「型」を一度経験すれば、環境が変われど、お客様が変われど、売るものが変われど「できる」ようになります。
ですから、「型」をどんどん進化させて再現性のあるものにしていくことで業務の標準化が進みます。
逆に言えば、ここで「標準化していこう」という意識にならず、「時間がないから一旦各々でやってみて」としてしまう会社なら、標準化、型化にはおそらくずっと取り組めません。
現場の社員による情報共有により、経験の浅い社員が学べる環境を作る
「型化」のヒントは日々の業務の中にあるわけですから、現場の社員は常に「これを共有してみよう」と思うことをメモに残したり、録音したりして、材料集めをしておくことが重要です。
「ジョンソンホームズ」のチームミーティングの事例
最近、私はグループ内で住宅販売を手がける「ジョンソンホームズ」のチームミーティングに出席しましたが、発言の際に「自分はこんなことに取り組んでいます」と、ノウハウの共有を意識して話す姿勢が見て取れたのに手前味噌ながら感心しました。
特に経験の浅い若手にとって、先輩から「何でも聞いてね」と言われても、そもそも何を聞いて良いかわからないことがよくあるのではないでしょうか。
だからこそ現場の社員には「自分の売上だけ伸ばせば良い」のではなく、チーム全体、会社全体の業績を伸ばす意識を持ち、「自分のノウハウがもしかしたら他の人の役に立つかも」と、皆で知識と経験を共有することを習慣化してほしいですね。
「業務フロー・プロセスの型化」自体も義務的に「型」にするのが重要なのではなく、「会社として利益を上げるため」という目的をきちんと伝え、理解してもらった上で進めていくようにしていただきたいと思っています。
社員が自ら業績を上げるには?自律的に成長する企業に変えるステップ
業務の「型化」は、社員が自ら考えて動く自律的な組織づくりに有効です。
しかし、そもそも社員の意識を「会社の業績が上がらない(だから待遇が悪い)」という状態から「会社の業績は自分たちで上げるものである(業績を上げることによって待遇が改善される)」という意識に変えるためには、4つのステップがあります。
いずれも幹部主導にはなりますが、中心となって動いてもらうのは現場の社員の皆さんです。
中には「うちの社員には無理だ」と感じる方もいらっしゃいますよね。
また、経営者自身が「よし、やろう」と決心しても、経営幹部から反対意見が出てくるケースはよくあります。
しかし「会社全体で売れないとダメだよね」というマインドチェンジができないうちは、自律的な組織づくりへの一歩が踏み出せません。
そこで、一つずつ段階を踏んで徐々に取り組んでいただきたいと思っています。
①現状把握を行い、課題を明確にする
- 「業績管理の型化」「進捗チェックの型化」「業務フローの型化」の現状を診断
- 課題を特定し、優先的に取り組む領域を決める
現在、何ができていて何ができていないかをしっかり把握しましょう。
いくつか課題が出てくると思いますが、一度にすべてを解消するのは無理ですから、優先的に取り組む領域を決めてください。
②自分たちで戦略を構築し、理解を深める
- 「なぜこの戦略なのか?」を幹部・社員と共に考える
- 経営と現場のズレをなくし、実行精度を高める
戦略の構築も社員に任せますが、幹部の方々から見て拙いと感じられても、構築する過程で理解を深めていって、納得度を高めていくように進めます。
「まだまだ」と思っても、一旦「ここを直してみたら」とヒントを与える形で、愛を持ってやり直しを促してください。
時間はかかるものの、現場の社員はこういうやり取りを通じて、経営層の利益感覚や戦略構築のセンスに触れ、ギャップが徐々に埋まっていくのです。
そうすると報告の精度も求められている情報に対する感度も上がってくるので、「今ほしい報告内容はそれじゃない」という不満も減ってくると思います。
③行動計画の実行度を高め、業績を作る
- KPI・マイルストーンを明確化し、責任の所在を明確にする
- 定期的な進捗チェックで、計画の実行度を維持する
ここで誤解していただきたくないのは、「責任の所在を明確に」というところ。
できなかったことに対して「あなたの責任だ」と追及するのではなく、「自分たちで作った目標なのだから、やりきりましょうね」という意識を持つことが重要です。
進捗チェックは、先ほどもご説明したように週次がベスト。
チェックがないとダレてきてしまいますから、やはり会議のアジェンダとして、進捗報告を必ず入れるのがおすすめです。
私たちも同じように取り組んできた実感として、現場側は初めのうち「面倒だ」と感じるものですが、取り組むうちに慣れて、当たり前になっていきます。
毎回報告することが頭に入ってくるし、ブラッシュアップもできるし、PDCAサイクルが早くなるし...と、こうして細かく取り組んでいることが、のちのち効いてくるのです。
チェックの頻度が少ないと、気づいたときには大きなズレが生じているため、大幅な戦略変更を強いられるケースもあると思いますが、「細かくチェックすることで微調整で済んだ」という経験を何度も経験しています。
時間にして、1日5分の振り返りで良いはずです。
逆にこの1日5分の時間を取らず、週次のチェック直前にまとめてやろうとすると、5日分で25分かかる計算になります。
時間が経てば経つほどやることが多くなり、記憶も薄れますから、やはりこまめな振り返りは毎日の業務に組み込んでいただきたいです。
④早期に対策を立案し、高速でPDCAを回す
- 問題が発生したら、すぐに対策を考え、実行・改善を進める
- スピーディーにPDCAを回すことで、業績を積み上げる習慣をつける
毎日5分の振り返りをしながら、週次で進捗チェックを行い、対策を立てて次につなげる。
これが自律的組織づくりのためのPDCAです。
振り返りが習慣化することによって問題発生時の対応もスムーズになり、早期の解決が見込めます。
そして、このPDCAをスピーディーに回すことにより、業績を積み上げることも習慣となります。
以上、4つのステップを積み重ねていくことによって、時間はかかっても、皆さんの会社も自律的に成長する企業へと変われるはずです。
自主自律型の経営については「ヤマチの連邦多角化経営と自主自律型の経営はいつから始まった?」も、あわせてぜひご覧ください!
社員自ら業績を上げる組織に成長するには「型化」の導入がおすすめ!
「社員が自発的に動いてくれない」というお悩みはよく聞きますが、企業の成長にとって、自律的な組織づくり、社員自ら業績を上げる組織づくりは絶対に必要です。
「業績管理の型化」「進捗チェックの型化」「業務フローの型化」の3つを整えれば、社員自らが業績を作る組織へと進化し、持続的な成長が可能になるはずです。
多角化している、あるいは今後多角化を考えている状況であれば、経営者だけ、幹部層だけで業績管理を行おうとすると手に余るのは目に見えています。
社員を信じて取り組んでみると、案外3ヶ月くらいで慣れて、自分たちで回していくようになってくれるものです。
「KPI」「PDCA」といった言葉になじみのない方でも、「型化」を実践してみれば、これらが社内の共通言語になっていきますし、難しいことは何もありません。
3つの「型化」をぜひ取り入れて、これから起こり得る環境や市場の変化に左右されず、自律的に成長する企業を目指していきましょう。
ヤマチユナイテッドでは、今回ご紹介した内容を含め、業務改善のノウハウを詰め込んだ「KATAKA -型化-」という実践型オンライン研修をご用意しています。
1社8名様まで同時受講可能ですので、社員に任せることに対して幹部層で賛否が分かれるといった場合でも、この研修を通じて思いを一つにして取り組んでいただけるようになると思います。
もし興味をお持ちでしたら、ぜひ受講をご検討ください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|経営支援事業部|カンパニー長
山﨑 舞
人材総合サービス会社の営業部勤務を経て2018年(株)ヤマチマネジメントへ入社。前職では採用広告サービスの販売営業部で戦略スタッフとして企画・販促・アシスタント業務を担当。その際、元々取引先だったヤマチユナイテッドの社風やミッションに惚れ込み、転職を決意。現在は経営支援事業部で企画・運営を担当しつつ、営業推進チームリーダー兼人財開発コンサルタントとして活動。企業の新卒採用・育成を支援している。