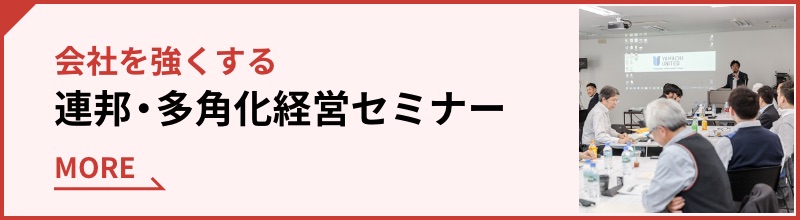顧客ロイヤリティとは?向上させる方法やメリットも解説
ブランディング


こんにちは、ヤマチユナイテッドの山地です。
「ブランディングが大切」といわれても、よくわからないと思う人が多いのかもしれません。
トヨタやホンダのようなメーカーもブランド、プリウスやフィットのような商品もブランド。
私たちのように、多角化を目指す中小企業の経営者がブランディングを進めるためには、何から取り組んで、どこを目指せば良いのでしょうか。
今回は、ブランド戦略のカギとなるマーケティング手法「顧客ロイヤリティ」を向上させる方法について解説。
顧客ロイヤリティを高めるメリットや、ヤマチユナイテッドの事例もご紹介します。
目次
顧客ロイヤリティとは?
顧客ロイヤリティとは、企業や商品のブランドに対して、顧客が抱く愛着や信頼のことを指します。
顧客ロイヤリティの英訳は、「Customer Loyalty」で「Loyalty」は忠誠や忠義などの意味です。
顧客がブランドや商品に対して忠誠心を持つということから、愛着や信頼を抱いていることを表しています。
ブランドには「企業ブランド」や「商品・サービスブランド」があります。
それぞれ簡単に用語の説明をすると、以下のようになります。
-
企業ブランド:ソニーやANAなど、社名そのものがブランドになっているケース。当社でいえば「ヤマチユナイテッド」や「ジョンソンホームズ」
-
商品・サービスブランド:iPhone(社名:Apple Inc.(アップル))、ユニクロ(社名:ファーストリテイリング)など。当社の例でいえば、機能訓練専門デイサービス「きたえるーむ」、ジョンソンホームズのコンパクト規格住宅「COZY」など
企業ブランドや商品・サービスブランドに対する愛着や信頼を高めることで、ブランドの価値を向上させることができます。
まずは顧客ロイヤリティを理解するための分類とその測り方について見ていきましょう。
顧客ロイヤリティの分類
顧客ロイヤリティには、「心理ロイヤリティ」と「行動ロイヤリティ」に分けられます。
心理ロイヤリティ
心理ロイヤリティは、顧客のブランドに対する愛着や信頼など、好意的な感情を指します。
心理ロイヤリティは、そのブランドを使っていない人でも高まる感情です。
例えば、まだブランドは使っていないけど、憧れのブランドだから使ってみたい!という感情も心理ロイヤリティの一つといえます。
行動ロイヤリティ
一方で、行動ロイヤリティとは、その企業やブランドに対しての実際の行動です。
口コミでブランドを広げる、そのブランドの商品を継続的に購入する、他社製品やサービスへの乗り換えをためらうなども、行動ロイヤリティといえます。
心理ロイヤリティは、行動ロイヤリティに大きく影響し、一般的には心理ロイヤリティが高まると行動ロイヤリティにつながりやすくなるとされています。
例えば、アメリカのオートバイメーカー「ハーレーダビッドソン」。
会社の名前であり、商品の名前でもありますが、愛好家によって組織された「ハーレーダビッドソンクラブ」には熱烈なファンが集まっています。
同じく自動車のミニクーパーも、世界中に愛好家によるクラブが組織され、さまざまなファンイベントが開催され、多くのファンが参加しています。
このようなファンクラブへの入会やファンイベントへの参加も、そのブランドへの心理的なロイヤリティがあるからこそ発生する行動ロイヤリティの一つといえるでしょう。
中小企業がブランドに力を入れるべき理由について、こちらのコラムで紹介しています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
多角化経営での新規事業立ち上げについては「新規事業立ち上げのプロセスとは?多角化を成功へ導くステップを解説」をご参考ください。
顧客ロイヤリティの測り方
顧客ロイヤリティを測る指標として導入されているのが「NPS」です。
「NPS」は、「ネット・プロモーター・スコア」の略で顧客ロイヤリティを数値化する指標です。
顧客に対して「この製品を家族や友人に勧める可能性はどのくらいあるか」という質問でアンケート調査を行い、その答えを集計・分析して数値化します。
製品やアプリなどのレビューで、このような問いかけを見たことがあるという方も多いのではないでしょうか?
問いかけに対しては0から10までの11段階で答えてもらい、9以上の高い評価をした人を推奨者、7から8を中立者、6以下の低い評価をした人を批判者とします。
推奨者の割合から、批判者の割合を引いた数字がNPSです。
計測方法が簡単なことや、スコアの出し方が共通で競合他社との比較が可能というメリットもあり、多くの企業で活用されています。
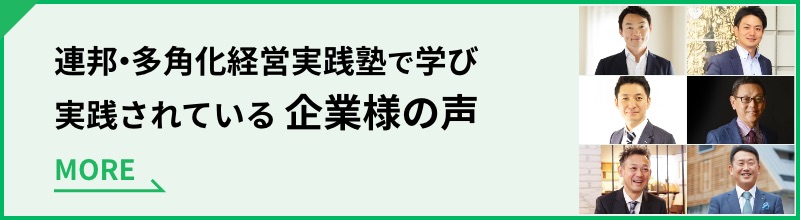
顧客ロイヤリティを高めるメリット

顧客ロイヤリティを高めると、次のようなメリットが期待できます。
リピート率の向上
お客さまがブランドに愛着や信頼を抱くと、新しい商品やサービスを高頻度で購入してくださいます。
製品に愛着を抱いていれば、他社の製品やサービスに乗り換えることをためらい、継続してそのブランドを購入したり、利用したりしてくださるのです。
逆にブランドの方向性が変わりそうなタイミングでは「高くても私たちが買うから今のままでいて欲しい」とブランドを応援してくださることもあります。
顧客単価のアップ
ブランドを気に入ってもらえれば「このブランドのほかの製品も買ってみようかな?」「今まで他のサービスも使っていたけど、こっちだけにしようかな」という行動に移行することが考えられます。
結果的に、顧客一人あたりが使ってくださる金額が大きくなり、売上アップが期待できます。
また、企業そのものに対しても好意的な感情を抱いていることが多いため、企業の新製品などにも興味を持ってもらえる可能性が高くなるでしょう。
顧客ロイヤリティ向上が生む口コミによる集客力のアップ
顧客が企業ブランドや商品ブランドに対して信頼を抱いていると、SNSの口コミなどで良い評価を拡散してくださることがあります。
実際に使っている人の口コミや親しい人からの口コミは、まだそのブランドを使っていない人への検討材料として大きな役割を果たします。
既存顧客のリピート率の向上だけでなく、コストをかけずに新規顧客の獲得を目指せる手法です。
顧客ロイヤリティを向上させるには?

顧客ロイヤリティを高めるには、具体的にどのような手法が用いられるのでしょうか?
ここでは3つの取り組み方法を紹介します。
①顧客の声に耳を傾ける
顧客の声に耳を傾け、顧客のニーズやウォンツを探ることは、顧客ロイヤリティを高めるという点でとても重要です。
先ほど紹介した「NPS」のほかにも、独自のアンケートを実施するなどして、ブランドや商品についての意見を集めましょう。
また、顧客情報から、年齢や購入履歴などの重要なデータを得ることもできます。
SNSの口コミなども参考にできる情報ですが、少数の意見をもとに戦略を練ると方向がずれる場合もありますので、注意が必要です。
顧客の声にしっかりと耳を傾け商品の改善や開発に取り組むことは、正しく顧客の求めるものを提供するためには必要なことです。
何よりその姿勢は顧客の信頼を得ることにつながりますし、顧客も自分の欲しいものを提供してくれるブランドからは離れようとはしません。
アップルコンピュータにしても無印良品にしてもそうですが、お客さまを大切にすることで強烈なブランドになり、強固な事業を築けます。
②顧客ロイヤリティの把握と目標設定をする
顧客の声を集めたら、それを分析し、何が課題かを把握し、目標設定までつなげることが重要です。
「NPS」などの指標をもとに現状の課題を切り分けてブランドごと、商品ごとに取り組み目標を設定していきましょう。
具体的には、そのブランドがターゲットとしている層の顧客ロイヤリティがきちんと上がっているかや、競合他社のブランドと比較して顧客ロイヤリティが勝っているかなどを分析します。
ターゲット層に対してあまり響いていないようであれば、ブランドイメージと顧客層の価値観がずれているのかもしれません。
価格帯やデザインなどを見直す必要があります。
分析した内容から導き出せる施策を考え目標設定し、再度調査をするといった流れを続けることが大切です。
③カスタマーサービスの質を向上させる
顧客ロイヤリティを高めるためには、カスタマーサービスで顧客満足度を高めることも大切です。
商品を買うまでのカスタマーサービスの質を高めることはもちろん、買ったあとのサポートも顧客の心理ロイヤリティに大きく影響します。
当社でいえば、中高級路線のインテリアショップ「インゾーネ・ウィズ・アクタス」が、ファンに支えられているブランドの一つです。
「インゾーネの商品だから買う」「あの店員さんだから買う」と言ってくださるお客さまが少なくありません。
インゾーネの店舗をパーティー会場にして、商品を購入してくださった顧客の皆さんを無料で招待する「インゾーネナイト」というイベントを開催したときは、多くのファンの方々が集まってくださいました。
また、2007年9月にオープンした「インゾーネ・ウィズ・アクタス 宮の森店」が、2017年9月に10周年を迎えリニューアルオープンしたときも、10年前にオープンしたときからお越しいただいているお客さまが駆けつけてくださるなど、長く顧客との関係が続いています。
当社の住宅会社「ジョンソンホームズ」でも、住宅を新築されたお客さまやリフォームをしていただいたお客さまを対象に、毎年夏祭りを開催。
社員が企画して、無料で焼き肉などを振る舞ったり、縁日を開いたりと盛りだくさんの内容で、数千人ものお客さまが一堂に会します。
このような体験を通じて「ジョンソンホームズって良いよね」というお客さまがコミュニティをつくり、口コミや紹介で新たなお客さまを連れてきてくださるのです。
これも顧客ロイヤリティの向上が成功している一例と言えるでしょう。
顧客がブランドのコミュニティに参加したり、口コミで良い評価を拡散したりという行動は、ブランドへの信頼や愛着を獲得し、顧客ロイヤリティが高まった証拠でもあるのです。
イベントなどの開催は、買ってからのお客さまだけでなく、買う前のお客さまに対しても「そこのコミュニティに入りたいから買うのを検討しようかな」という行動を起こさせるきっかけにもなります。
顧客ロイヤリティを高めてさらに価値のあるブランドへ!
これからは顧客ロイヤリティを高めて、ブランドを伸ばしていく時代です。
顧客ロイヤリティを高めていくことで、リピーターや新規顧客の増加で利益向上が期待できたり、口コミで良い評価をしてくださったりと大きなメリットが生まれます。
顧客ロイヤリティの向上を実現するには、顧客の意見をしっかり聞くことや、イベントなどの体験などを通して顧客の満足度を高めることが大切です。
もちろん、顧客ロイヤリティの向上は、すべての業種に有効な方法ではないかもしれません。
ですが「B to C(一般消費者向け)」のビジネスをしている会社のブランド戦略としては、おすすめの方法といえるでしょう。
自社ブランドのさらなる成長戦略として「顧客ロイヤリティ」の向上も検討してみてください。
ヤマチユナイテッドでは、ブランド戦略や多角化経営など、みなさまの経営に役立つセミナーも開催しております。
興味があるイベントがありましたら、ぜひご参加ください!
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。