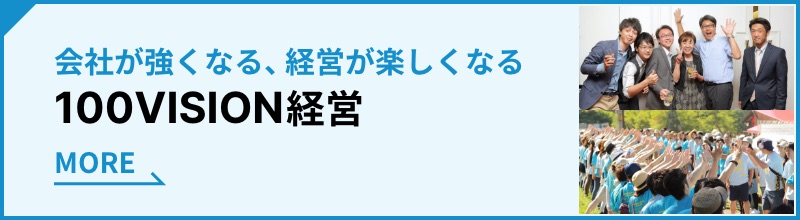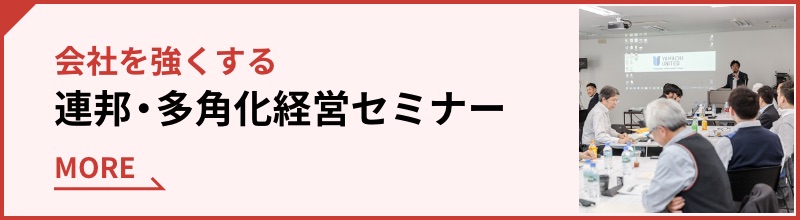インナーブランディングの進め方を実例で紹介!目的や効果も確認
ブランディング

こんにちは、ヤマチユナイテッドの山地です。
連邦・多角化経営において、グループ全体でどのように一貫性を出すかは、経営者の腕の見せどころです。
すでに複数の事業をもっているなら、それらをうまくブランドでくくり、つなぐ作業が必要になります。
まだ事業が少なければ、一貫性を考えながら新規事業を立ち上げていく意識を持つことが大事です。
「これはうちでは異質だね」という事業があると、あとで苦しくなってしまうかもしれません。
そうした事態を避けるには「インナーブランディング」が大切。
今回は、インナーブランディングを行う目的や効果、進め方のポイントなどを当社における実例とともにご紹介します。
事業を多角化する際に欠かすことのできない「インナーブランディング」と「理念」について、ブランディングとの関係を考えながらお話していきますので、ぜひご参考ください
目次
- インナーブランディングとは?行う目的も確認
- インナーブランディングの効果とメリット
- インナーブランディングの進め方のポイント
- インナーブランディングの進め方の注意点
- インナーブランディングの進め方を知ってブランドを育てよう
インナーブランディングとは?行う目的も確認
インナーブランディングとは、企業の理念(バリューやパーパス、ミッション)を社員に浸透させるための、社員に対するブランディング活動を指します。
一方、社外(顧客)に対して行うブランディング活動は「アウターブランディング(エクスターナルブランディング)」とよびます。
事業のブランディングを構成する要素としては、社名、ロゴ、ビジョン、理念、コーポレートメッセージ(キャッチフレーズ、ストーリー)などが考えられます。
なかでも、私が特に重要視しているのが理念(バリューやパーパス、ミッション)です。
理念を社員に浸透させることが、ブランドの価値を高めるためにはとても重要です。
当社のように、多角化で多数の事業を展開する場合には、各事業、各社員が、企業の軸となる理念から外れないよう、インナーブランディングに力を入れる必要があります。
多角化を進める経営者にとって、ブランド全体をコントロールするのは重要な仕事の一つです。
グループの理念の下に数多くの事業をくくる技術が必要になりますし、理念を何度も言い続けてグループ内に浸透させなければなりません。
中小企業にこそ重要なブランディングについては、「中小企業こそブランディングに力を入れるべき理由とは?」で紹介していますので、あわせてご参考ください。
インナーブランディングの効果とメリット
インナーブランディングを行うことで、どのような効果やメリットが得られるのでしょうか?
社員の方向性が揃い、ブランドを確立しやすい
インナーブランディングで企業の理念を浸透させることで、社員が同じ方向を向くことができます。
当社の住宅会社である「ジョンソンホームズ」のミッションは、「いつまでも続く自分らしい幸せな暮らし」というものです。
つまり、家を販売するだけでなく「家に住んでからの幸せを届ける」ということをミッションに掲げています。
このミッションをしっかりと理解することこそが、社員の行動の指針となり、目先の売り上げのためだけに家を売ろうと考えることはなくなります。
そして、家を買ってもらったあとのアフターサービスに力を入れようといった発想に変わります。
このミッションが浸透していなければ、「家を売るまでが大事」と考える社員や、「家の完成までのスピードが大事」と考える社員もいるでしょう。
それでは、ブランドとしてのイメージがお客様には伝わりません。
こうしたミッションのもとで働く社員が、会社の商品やサービス、社風などのイメージと連動することによって、ブランドが構築されていくのです。
社員の満足度やモチベーションが向上する
インナーブランディングは、社員の満足度やモチベーションの向上にも貢献します。
理念が分からないまま働くということは、「何のためにこの商品を売っているのか」「何のためにこんなルールがあるのか」、そんな想いを抱きながら働くことです。
そんな状態では、仕事のやりがいも感じにくいでしょう。
理念を明確にし、それをしっかり社員に浸透させることができれば、仕事に対する満足度やモチベーションのアップにつながります。
より社風にあった人材の確保ができる
社員全員に理念が浸透し、誇りや使命を持って働く環境が実現できれば、社員はいきいきと働くことができます。
インナーブランディングがきちんとできることで、会社の進むべき方向が明確になり、より自社にマッチした人材を採用しやすくなります。
企業の理念に共感して入社した新入社員には早期退職のリスクも少なく、モチベーションが高い状態で仕事をしてくれることが期待できます。
顧客満足度が向上する
社員が誇りや使命感を持って働くことで、お客様に対しても質の高いサービスを提供できるようになり、顧客満足度の向上につながるということも考えられます。
顧客満足度が向上することで企業の評判が良くなり、結果として売り上げにつながることが期待できます。
インナーブランディングの進め方のポイント
インナーブランディングを実際に行う際の進め方のポイントについて見ていきましょう。
進め方①理念の策定
社内でインナーブランディングを行う前に、浸透させる理念の策定をする必要があります。
「理念」は企業経営の根幹であり、すべてを支えるもの。会社が事業を行う上で、成し遂げたいことや目的を示したもので、会社経営の基礎となる重要な考え方になります。
インナーブランディングは、社員に浸透させる理念があってこそ。
そもそもみなさんの会社では、しっかり理念を持っているでしょうか?
理念策定のポイント
自社ではっきりとした理念を社員に提示していないのなら、なるべく早くとりまとめ、発表したほうが良いでしょう。
ただし、その際は、トップダウンではなく、幹部や社員を巻き込んで、「自分たちでつくった」という形にすることが重要です。
理念が単なるお飾りにならずに、血の通った言葉となるはずです。
グループ全体の理念(パーパス)は、「北海道から色んな世界を変えていく」のように、やや抽象的な表現で、間口を広げるのがコツ。
「住宅業界を変える」といった限定的で狭いコンセプトだと、整合性のとれない事業が出てきます。
各事業のブランドは尖る必要がありますが、グループ全体としては大きな網をかけるような理念(パーパス)にすると良いでしょう。
グループ理念は、新規事業の提案が上がってきたときに、ブランディングの観点から「うちにはふさわしくないからやめよう」と判断する材料になります。
例えば、M&Aの案件が持ち込まれることがありますが、どんなに収益性が良い事業であっても、「グループ全体の中で違和感がないか」ということを真っ先に考えます。
いくら儲かっても、グループの理念(バリューやパーパス、ミッション等)にそぐわない事業であれば、いずれ行き詰まる可能性が高いですし、他の事業に悪影響を及ぼすおそれもあります。
理念はいわば、事業を成功へと導く道標のようなもの。
事業を始めるときは、個別のブランドばかりに注目せず、それがグループ全体のブランドや理念に沿っているか意識することが大切です。
理念については以下のコラムでも詳しく紹介していますので、こちらも参考にしてみてくださいね。
経営者の孤独の原因とは?社員が自発的に動き出す組織になるまで
ヤマチユナイテッドの実例
多角化経営を進める中で、グループ理念からどのように新規事業を広げていくのか、考え方のポイントをヤマチユナイテッドの「理念(パーパス)」を例にご紹介しましょう。
当社では50以上の事業を展開しています。
それらは「ライフスタイル事業」(一般消費者向け事業)と「プロフェッショナル事業」(企業向け営業)のどちらかに分けることができます。
「ライフスタイル事業」では、住宅やインテリアショップ、デイサービスなどを展開。
「プロフェッショナル事業」ではイベント企画・施工、建築資材の卸売、住宅フランチャイズ、デイサービスフランチャイズなどを行なっています。
住宅、イベント、デイサービスなど、一見関連のない事業を展開しているように感じるかもしれません。
ですが、いずれの事業も「北海道から色んな世界を変えていく」というグループ全体のパーパス(理念)のもとに事業を行い、ブランディングしています。
進め方②理念の浸透
理念をつくったら勝手に組織に浸透していくというわけではありません。
理念を浸透させていく作業が必要になります。
理念に共感してもらい浸透させるための方法には、このようなものがあります。
- 社内向けWebサイトなどで情報共有
- 理念に沿った行動で成果を上げた社員への表彰制度
- クレド(企業の信条・行動指針)を印字したものを配布する
- 理念について理解を深める機会をつくる
進め方③効果測定
インナーブランディングは効果が出るのに時間がかかることも多く、また、効果を測定するのが難しい傾向があります。
ですが、効果を確認して必要に応じて改善していくことも重要なポイントとなります。
インナーブランディングの効果を測定する方法としては、社員へのアンケート調査や面談といったものがあります。
また、従業員ロイヤリティ(職場に対する愛着・信頼の度合い)を測るためには「eNPS(Employee Net Promoter Score)」も効果的でしょう。
自社の製品やサービスを他人におすすめしたいかどうかを数値化することができるため、インナーブランディングの到達度を客観的に分析することができます。
インナーブランディングの進め方の注意点
インナーブランディングでよくある失敗例は、理念の浸透のために、デザイナーやコンサルタントにかっこいいロゴや理念をつくってもらうケース。
このようなケースは、会社の周年記念のときに大々的に発表したりしても、形だけの理念なので、いずれ忘れ去られてしまいます。
また、朝礼で立派な理念を唱和するけれど、イヤイヤ言わされているので誰も覚えていない、ということもよくあります。
形だけだったり、社員がイヤイヤやらされる理念の共有では、インナーブランディングは失敗に終わってしまいます。
社員が自発的に理念を深掘りし、理念を体現する機会や雰囲気を整えましょう。
インナーブランディングの進め方を知ってブランドを育てよう
社外に対してのブランディングを成功させるには、まず社内のブランディングが大切。
インナーブランディングは、企業の理念を社内で浸透させるための、社員に対するブランディング活動のことです。
インナーブランディングを行うことで、社員の向かう方向を定めてブランドを確立し、社員のモチベーションの維持や定着を図ることができます。
社風に合った人材を確保しやすくなるというメリットもあります。
インナーブランディングを進めるには、まず理念を策定しましょう。
特に多角的に事業を展開している企業では、グループ理念で一つの軸を定める必要があります。
パーパス(理念)は狭めすぎず、ある程度間口を広げることも大切ですよ。
理念はつくって終わりにせず、定期的なミーティングなどを活用して社員の理解を深めることも忘れずに。
インナーブランディングの効果測定と改善も行いましょう。
社員に理念を浸透させる「インナーブランディング」こそが、ブランドを育てることにつながっているといえるでしょう。
ブランディングについては他にもさまざまな視点からコラムを書いておりますので、ぜひご参考ください。
また、ヤマチユナイテッドでは多角化戦略や人材育成など、多岐にわたるテーマについての経営セミナー・イベントを開催しています。
中小企業の経営課題のヒントになるコンテンツをご用意していますので、ぜひご参加ください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。