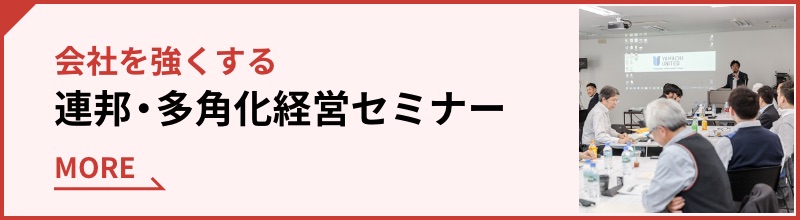ブランディングの効果とは?目的や定義、成功させるポイントを解説!
ブランディング

こんにちは、ヤマチユナイテッドの山地です。
ブランディングの取り組みを、カッコいいロゴやマーク、おしゃれな商品パッケージをつくることだと勘違いしている方はいないでしょうか。
ブランディングとは、単なるデザインワークではありません。
確かに、目に見えるのはロゴやマークだけかもしれませんが、目には見えない大きな効果があるのです。
当社では、ブランド力を高める・浸透させる活動こそが「ブランディング」であると考えています。
そこで今回は、ブランディングの目的や効果、ブランディングを成功させるポイントや進め方について、ご説明しましょう。
また、「連邦・多角化経営」を実践している当社では、企業の多角化で大切なことはグループ全体のブランドの統一だと考えています。
ブランド統一のために重要視していることについてもご紹介します。
目次
- 「ブランディング」の目的とは?当社が考える「ブランド力」の定義
- ブランディングの効果とは?
- ブランディングを成功させて効果を得るための進め方のポイント
- ブランディングの効果は「企業理念の浸透」にあり!
「ブランディング」の目的とは?当社が考える「ブランド力」の定義
一般的に「ブランディング」というと、顧客や社員に共通のイメージを持ってもらうための取り組みのことを指します。
ブランディングの目的は、ブランドの価値を高めることで競合他社や競合商品との差別化を図り、自社の商品やサービスの優位性を明確にして顧客から選ばれることなどが挙げられます。
ブランディングの効果を上げるには「ブランド力」の定義を知ろう
企業によってブランディングの定義や考え方はさまざまです。
当社では、「ブランディング=ブランド力を高めること」だと考えています。
では、ブランディングのカギとなる「ブランド力」とは一体どのようなものを指すのでしょうか?
当社では、以下の5つの条件をもって「ブランド力」を定義しています。
1.求心力が働いていること
会社や商品にブランド力がついてくると求心力が働きます。
例えば、集客コストが小さく済む、大きな広告戦略を打たなくても人材が集まる、値引き交渉がなく価格が通る(顧客が喜んで購入してくれる)、情報が集まってくるなど、さまざまなプラスの要素が自然と引き寄せられてくるのです。
2.ポジショニングがとても良いこと
ここでのポジショニングとは会社の位置づけのことをいいます。
同業他社と比較することで、自社がどの位置にいるのかをより具体的に知ることができます。
自社のポジショニングが明確になると、競合相手がいない、空白ゾーンが存在するなど、いわゆるブルーオーシャンと呼ばれる場所で戦えるようになります。
つまり、トップ、チャレンジャー、フォロアー、ニッチャーなど、良いポジショニングを取ることができるようになるのです。
3.価値観やデザイン、事業に「一貫性」があること
マークやロゴなどのデザインを含め、その裏にある会社の理念(バリューやパーパス、ミッション)や社風などが、商品・サービスなどと一貫性を持ってつながっていることもブランド力の一つです。
その会社の「らしさ」の統一感があることで、スタッフ・顧客を含めた関係者が誇りに思う会社イメージを作り上げることが可能になります。
4.名前を聞いただけで「安心感」があること
ブランド力が高い会社は名前を聞いただけで「安心感」があります。
その会社の商品・サービスなら吟味しなくても品質が担保されている、適正価格で販売されている安心感がある、信頼感が買う決め手になっているなど、会社名で消費行動を決める方は少なくありません。
「その会社に任せていれば大丈夫」と思わせるブランド力は大きな強みになります。
5.他社との「差別化」ができていること
当社ではいつも新規事業をやるとき、戦略を練る際には必ず「差別化できているか」というフィルターを掛けるようにしています。
フィルターを掛けることで、商品・サービスにおいて、他社とは違う品質、デザイン、価格、ストーリーを提示できるようになるからです。
当社では、これらのブランド力を高める・浸透させる活動こそが「ブランディング」であると考えています。
企業ブランディングを行う目的について詳しくは「企業ブランディングの目的とは?連邦・多角化経営との関係も確認」でご紹介しています。
当社の考えるブランディングについては「中小企業こそブランディングに力を入れるべき理由とは?」でもお話しているので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。
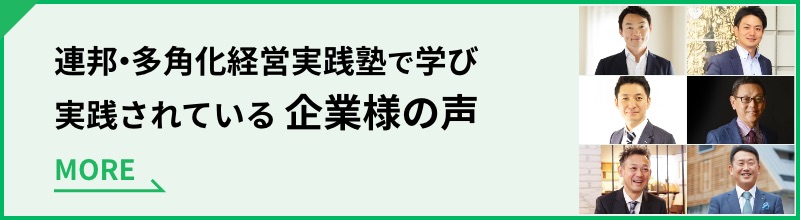
ブランディングの効果とは?
当社はさまざまな事業を展開しています。
それぞれの事業には、その事業ごとのブランドがあります。
私は、企業の多角化で大切なのは、グループ全体のブランドの統一だと考えています。
そのブランド統一のために重要視しているのが、理念(バリューやパーパス、ミッション)です。
それぞれの事業が明確な理念を持つことで、ブランドが立ち、成功する可能性が高くなります。
「それぞれの事業がうまくいっているのなら、それで十分ではないか」
「わざわざ費用と時間をかけて、グループのブランドイメージを統一する必要があるのか」
そう考える方もいるかもしれませんが、私はグループ全体のブランドを統一する効果として、大きく次の3つがあると考えています。
- 顧客創造
- 雇用強化
- 組織強化
順番に、くわしく説明していきましょう。
ブランディングの効果①顧客創造
グループ全体のブランドイメージが一貫していると、お客さまが増えて、売り上げアップが期待できます。
顧客に「このブランドなら安心して購入できる」「お付き合いできる」という印象を与えることができるからです。
当社の場合、各事業がそれぞれ「理念(バリューやパーパス、ミッションなど)」を持っています。
例えば、機能訓練専門デイサービス「きたえるーむ」は「すべてのお客さまのクオリティ・オブ・ライフ=生活の質の向上に貢献する」という理念を掲げています。
他の事業の理念にも、「お客さまの豊かな生活(ライフスタイル)を支援する」というコンセプトが通底しています。
その上で、それぞれの事業を束ねる「ヤマチユナイテッド」では、下記の3つをあわせてグループビジョンとしました。
- 2024年度から新たに「北海道から色んな世界を変えていく」というパーパス
- パーパスを実現するための「THE 100VISION」というミッション
- 行動指針となる14項目のコアバリュー
※「THE 100VISION」とは?
ヤマチユナイテッドでは、パーパスを実現する100の事業を創出し、魅力あふれる100人の経営者を育て、100事業×利益1億円=100億円の高収益を上げる企業になり、そして100年続く持続可能な良い会社を創る、というミッションを掲げています。
「ヤマチユナイテッド100VISION 経営=連邦・多角化経営」であることを社内外にアピールし、グループ全体のブランドイメージにこだわっているので、会社間の取り引きにおいても、安心して新規の取り引きを始めていただいております。
「一貫性があって将来性もある企業グループだ」「数多くの事業を展開しているので経営的に安定しているだろう」という印象を持っていただけるようです。
ブランディングの効果②雇用強化
ブランディングは雇用の面でも効果があります。
大きくて有名な会社であれば、優秀な人を採用するのは難しくありませんが、私たちのような中堅・中小クラスの企業だとそうはいきません。
しかし、ブランドがしっかり立っていて「こんな理念のもとで世の中を変えようとしている」ということが伝われば、企業規模の大小や有名無名を問わず、同じような志を持つ人が応募してきてくれます。
当社の場合は「THE 100VISION」を前面に打ち出しています。
そのため、「新しいことにチャレンジできる会社だ」「自分も事業責任者になれるかもしれない」「活躍の場がたくさんありそう」といったイメージに惹かれて入社してくる人がいます。
また、多角化した事業の中に特定の層にアピールできる事業があれば、それをきっかけに採用を有利に進めることもできます。
当社の事業のひとつに、若者を中心に人気を集めるインテリアショップ「インゾーネ・ウィズ・アクタス」があるのですが、「あのオシャレなインテリアショップを経営している会社なら働いてみたい」と、応募してくれる人がたくさんいるのです。
また、「M+(エムプラス)」というマンションリノベーションの事業に興味を持って、この仕事に就きたいと応募してくる人もいます。
当社の会社説明会では、採用のターゲット層から注目を集めそうな事業の例を中心に、多角化のストーリーを披露するという作戦をとることができます。
ちなみに採用情報サイト(採用ページ)は、グループのサイトと一貫性のある理念(バリューやパーパス、ミッション)やビジョンを伝えることが大切です。
見た目のデザインをかっこよくしただけでは「上辺だけだな」と見抜かれてしまうこともあります。
会社の理念やビジョンをはじめ、経営者のライフスタイルや価値観をも伝えることが必要でしょう。
社風も企業のブランドイメージに直結するので、採用ページには社員の笑顔やイキイキと働いている写真を使うこともポイントです。
応募者に近い将来の自分をイメージさせることができれば、親近感を抱いてもらえます。
当社が北海道で人気就職先ランキングの上位にランクインできたのは、このようにブランディングを意識しながら事業多角化を進めた結果だと思います。
ブランディングの効果③組織強化
ブランディングは、組織を強くする効果もあります。
理念(バリューやパーパス、ミッション)やビジョンがなく、ブランドが確立されていない会社だと、社員は些細なことで「うちの会社は何を考えているかわからない!」といった不満を抱き、辞めてしまうでしょう。
しかし、自社のブランドが明確になっていれば、会社で働くことを誇りに思い、ロイヤルティも高まります。
例えば、少し仕事が大変でも「この目標を達成するために、この会社に入ったんだ」と思い直してくれます。
当社の住宅会社「ジョンソンホームズ」には「いつまでも続く自分らしい幸せな暮らし」という理念が浸透しています。
家を建てて終わりではなく「住んでからの幸せ」を提供するのが目的なので、社員はブレることがありません。
「お客さまのために尽くす」という思考が、当たり前になっているのです。
同じような価値観や志を持つ仲間が集まって、「お客さまに喜んでもらうにはどうすれば良いか」を考えながらチームワークよく行動するので、自然と業績もアップしていきます。
これもブランディングの効果といえるでしょう。
また、多角化を進めると、いつのまにか事業部ごとの縦割り組織になってしまいがちです。
大切なのは、それらの縦割り組織に横串を刺すこと。
当社では「経営推進会議」や「委員会」といった横の連携を強化する制度を導入して、グループ全体を大きな1つの会社のように運営しています。
そのときに肝となるのが、すべての事業をひっくるめたビジョンや企業理念です。
多角化の効果を高めるには、抽象性が高い言葉で自分たちの使命をまとめ、一貫性のあるブランディングで一体感を醸成しておくことがポイントとなります。
そうでなければ、それぞれの事業が資本関係でつながるだけになり、多角化の効果が薄れてしまうでしょう。
ブランディングを成功させて効果を得るための進め方のポイント
ブランディングの一般的な進め方は以下のとおりです。
- 自社の現状の分析・把握
- ブランドの定義(ブランドコンセプト)を設定
- 理念(バリューやパーパス、ミッション)を浸透させるための施策を実施
- ブランディングの効果検証
ブランディングは商品・サービスを売り込む顧客を絞り込む作業でもあります。
まずは自社のブランドが現在どのように認知されているか、「3C分析」「4P分析」「SWOT分析」などを用いて現状を把握しましょう。
分析することで、自社や競合他社のポジション、自社の強みや弱み、差別化の方向性などを検証することができます。
ブランドを浸透させるための施策には、社外に向けたブランディング戦略(アウターブランディング)と社内に向けた戦略(インナーブランディング)の2種類があります。
アウターブランディングでは、広報活動や情報発信、イベントの開催などを行うことも多いでしょう。
インナーブランディングでは、社員総会やミーティングなどを通して社員に自社の理念(バリューやパーパス、ミッション)を浸透させることがポイントとなります。
インナーブランディングについては「インナーブランディングの進め方を実例で紹介!目的や効果も確認」もあわせてご覧ください。
ブランディングの効果が発揮されたかどうかは検証してみないとわかりません。
アンケート調査などで定期的に検証しましょう。
ブランディングの効果が不十分だと感じられるなら、広報活動の内容を変更するなど、方向性を調整してリブランディングをしていくのが重要です。
ブランディングの効果は「企業理念の浸透」にあり!
ブランディングとはブランドの価値を高めて競合との差別化を図り、顧客から選ばれることを目的とするものです。
ブランディングの効果とは、決してロゴやマークなど目に見える差別化だけではありません。
顧客を引き込んで売上をアップさせ、雇用を強化し、組織力も強化するといった効果が期待できます。
複数の事業を多角的に経営されている会社も、全事業で統一したブランディングをすることが効果的です。
全体の統一感を持ったブランディングのためには、企業の理念(バリューやパーパス、ミッション)を明確にしましょう。
ブランディングの進め方としては、自社の現状の把握、ブランドの定義の設定、理念を浸透させる施策の実施、ブランディングの効果検証といったステップに沿って行うのも良いでしょう。
ブランディングについては他にも多様な視点からコラムを書いております。
ぜひこちらもあわせてご覧ください。
また、ヤマチユナイテッドではさまざまな経営セミナー・イベントを開催しておりますので、こちらもぜひご覧ください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。