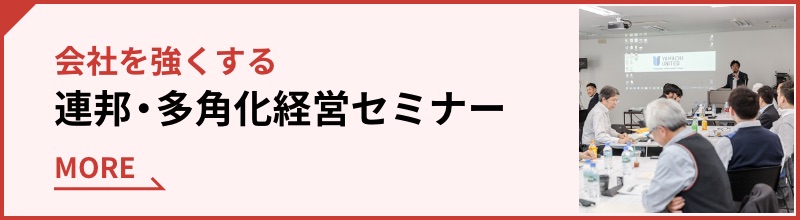全員参加型経営に必須の「オープン経営」のメリットと導入のコツ 〜全員参加型経営の基礎:後編〜
業績管理・経営計画

ヤマチマネジメントの石崎です。
当社では全員参加型経営(当社では「システム経営」と呼んでいます。)を導入することで、社員の自主性を育て、会社の業績アップにつなげています。
全員参加型経営をうまく機能させるための前提条件となるのが「管理会計」と「オープン経営」。
あなたがもしトップダウンの経営に限界を感じているのなら、まずは管理会計とオープン経営の導入から着手してみてください。
特にオープン経営は一人ひとりの自主性を促し、主体性を持って自分で判断できる、頼もしい社員を育ててくれるはずです。
今回は全員参加型経営のメリットとともに「オープン経営」の内容や導入のコツについて解説していきます。
目次
- 全員参加型経営とは?どんなメリットがある?
- 全員参加型経営の土台となる「オープン経営」とは?導入のメリット
- オープン経営を導入して全員参加型経営を成功させるコツ
- 全員参加型経営の土台であるオープン経営のメリットを知って導入を
1.全員参加型経営とは?どんなメリットがある?
まずは、全員参加型経営がどんなものなのか、どんなメリットがあるのか解説していきましょう。
全員参加型経営とは?
全員参加型経営とは、経営に必要な項目を細分化し、幹部や社員に分担してもらう経営の仕組みのこと。
目的やビジョンを共有した上で、社員たちが自ら経営計画を作成し、自分たちで業績進捗管理をし、最終的に自分たちで業績評価、人事評価を実施します。
経営の一部を任される幹部や社員は、高いやりがいと経営意識を持つことで急速に成長するため、企業の収益性と体質が劇的に変わります。
全員参加型経営のメリット
全員参加型経営のメリットは、経営をシステム化し任せることで、経営者の負担を減らすことができ、自主自律の企業風土が出来上がることです。
トップダウンの「ワンマン経営」はスピード感があって非常に効率的ですが、社員が一定数を超えるとトップダウン型マネジメントだけでは限界が生じてきます。
そこで、トップダウンとボトムアップをミックスさせ、社員全員の「知恵」と「創意工夫」、そして「やる気」を引き出す仕組みづくりが重要になってくるのです。
例えば、当社ではリーダーになると経営計画をつくるようになります。
自分のチームの人件費、原価率、粗利益率などを把握した上で、チーム全体でいくらの利益を出したいかを話し合い、そこから逆算して目標を決めます。
トップから「これだけ売れ」と割り当てられる数字と、チームでちゃんとすりあわせして、納得の上で決めた数字では、まったく意味合いが違います。
このように「自分たちのことは自分たちで考え、決める」ことで自主自律の企業風土が出来上がり、個人の成長だけでなく、企業としての成長も見込めるのが全員参加型経営の最大のメリットなのです。
2.全員参加型経営の土台となる「オープン経営」とは?導入のメリット
全員参加型経営である「システム経営」を機能させるためには、「管理会計」と「オープン経営」という2つの土台が必要になります。
ここではオープン経営について、詳しく確認していきましょう。
オープン経営とは?
オープン経営に明確な定義はありません。
管理会計を導入した上で、経営数値を社員に開示し、共有することだと理解してください。
ただし、なんでもかんでもいきなりオープンにするのではなく、ちゃんと順を追って段階的に開示していく必要があります。
ポイントは、社員教育です。
まずは幹部の集まる経営会議で全員参加型経営や管理会計などについての勉強会をして、部下に説明できるレベルになるまで理解を深めましょう。
部下に説明できるほど幹部に浸透したら、部門ごとの営業会議で経営数値を開示する、というように慎重に進めないと、余計な誤解を生じる可能性もあります。
なにをどこまでオープンにするかというのは、会社によって違っていて構いません。
基本的には上の役職から順番に下ろしていくのが良いでしょう。
なぜオープン経営をするのか?
社員は会社の実情や経営の仕組みのことを、意外とわかっていないことが多いです。
経営状況が分からないまま、上司から「〜をして欲しい」といわれても、なぜそれをする必要があるのかきちんと把握できていないため、やらされ感が生まれてしまうかもしれません。
オープン経営では、少なくとも決算書をオープンにします。
情報の透過性が求められる時代だからこそ、社員の知りたい情報や知るべき会社の状況を公開することで、社内で生まれる見当違いを防ぐことができます。
社員全員が会社の経営状況を把握していれば「〜を改善するにはどうしたら良いか?」と、当事者意識が生まれ、行動が変わります。
結果、生産性が上がらないと給与も上がらないという理屈を理解し「自分たちの会社は自分たちで良くしていくんだ!」という当事者意識が芽生えてくるのです。
オープン経営のメリット
経営数値をオープンにするメリットは、社員に「自主性」や「経営者感覚」が芽生えることです。
具体的な例として、1997年に北海道拓殖銀行が倒産したときの私自身の話をご紹介します。
その当時、会社で部門別に開示される業績はどこも、赤字、赤字、赤字...という状況でした。
当時は私も若手でしたが「これはまずいのではないか」「給料カットか」と、ハラハラしました。
こういう経験をすると、自分なりにこの状況をどうしたら打開できるのかを真剣に考えるようになります。
つまり、社員に危機感が共有されます。
社員も俗にいう経営者感覚を身に付けざるを得なくなるのです。
反対に、業績が良いときには、もう少し利益を出せば決算ボーナスが増えると分かるので、自主的にもうひと踏ん張りできるようになります。
どうやって利益を確保するか真剣に考えるから、主体性が高まる。
結果、業績もアップするという好循環が生まれるのです。
3.オープン経営を導入して全員参加型経営を成功させるコツ
オープン経営を上手く導入するためには、いくつかコツがあるのでご紹介しましょう。
経営数字の開示の前に社員教育をする
公開された経営数字をどう読み取れば良いか、どこまで達成できれば自分にどれくらい還元されるのかを理解するために、社員教育は必須です。
当社では、新人研修の段階で損益計算書の簡単な見方や収益構造について教えます。
売り上げから仕入れ原価や工事原価を引いて粗利益が出て、さらに人件費などいろんな経費を引いた数字が「営業利益」だと習うわけです。
そのうえで一人当たりの営業利益目標を100万円に設定しています。
ですから200人の社員がいたら最低でも2億円の利益は出しましょう、と伝えているのです。
そこから超えた超過利益は、会社に残すもの、税金として払うもの、社員に還元するものに分け、その割合をあらかじめ決めています。
社員に還元する率も、役職ごとに決まっています。
社員は所属する部門の営業利益が大きければ大きいほど賞与が増えるので、おのずとモチベーションがアップするというわけです。
すべての業績数字を共有する
全員参加型経営のポイントは、社長と社員の情報量を近づけること。
経営判断に必要な情報をすべて社員に公開し、経営陣も社員も同じ土俵で話ができるようにすることが必要となります。
当社では、全社の業績を社員が誰でも見られるよう、社内ネットワーク上に業績速報として公開しています。
事業責任者クラスには損益の状況、経費の内訳など詳細まで配信されます。
社員が納得できるよう説明する
経営数値を社員にオープンにするのは抵抗がある、という経営者も少なくありません。
社長の報酬や交際費を知られたくない、とか、内部留保の額まで開示する必要があるのか、という声もよく聞きます。
でも、そこを社員にしっかりと説明し、納得させなければ、いつまでも旧態依然の主従関係から抜け出せません。
たとえば、当社のような住宅会社は、良い商品や良いサービスを提供するだけでは不十分。
アフターケアまで責任を持つためには、多少不景気になっても経営を続けるだけの体力が重要で、そのためには会社にある程度の内部留保が欠かせないことを社員に説明しています。
それに、新規事業に投資するためにも自己資金は欠かせません。
当社では100の事業を立ち上げ、100人の事業責任者を創出する「THE100VISION」をミッションに掲げ、それに共鳴した社員が入社しています。
そのこともあって、利益を新規事業への投資に充てることに不満の声はあがりません。
社長の給与や交際費にしても、社長は融資を受ける際に個人保証もしているわけですから、リスクに備える必要があると説明すれば、理解してくれるはずです。
部署間の数字の分配方法にも配慮する
オープン経営は社内やグループ全体の戦略を練るのにも有効です。
好調な部門があれば、苦戦している部門から人員を移して、経営資源を集中させることもできます。
このとき気をつけなければならないのは、赤字部門の社員のモチベーション、いわゆるメンタル面です。
たとえば、一生懸命やっているけれどトントンの部門がある一方で、始めたばかりなのに高利益を出している部門があるとします。
これをオープンにしたら、儲けのない部門の社員は一気にやる気をなくしてしまうかもしれません。
そんなときは経費の分配を調整してから開示する方法もあれば、反対にそのまま公表して利益率の差を経営課題として捉えて正面から取り組む方法もとれます。
新規事業もちょっとした工夫が必要です。
先行投資であれば利益が出ないのは当たり前ですから、1〜2年は赤字計画にしてゲタをはかせてあげると良いでしょう。
また、単体では利益が出ないけれど相乗効果が期待できる部署にも配慮が必要です。
当社の場合、インテリアショップ単体での利益はたかが知れていますが、ショップを通じて住宅の契約に結びつくケースも少なくありません。
そういうときは利益が出ている部門から負担金をもらい、経費のマイナスを埋めるようにしています。
4.全員参加型経営の土台であるオープン経営のメリットを知って導入を
全員参加型経営とは、その名の通り社員全員で会社経営を行う仕組み。
経営計画の作成、業務管理、評価や成果分配なども自分たちでルールを決めて実施します。
全員参加型経営が社内にうまく浸透すれば、社員全員が主体性を持って業務にあたるようになり、会社の業績アップに直接つながります。
この全員参加型経営を導入する際に必須となるのが「オープン経営」。
経営数字を社員に公開することで、社員の経営者感覚を育てることができます。
オープン経営を導入する際は、ただ数字を公開すれば良いというわけではありません。
公開された数字をどのように理解するか社員に教育してから、経営判断に必要な数字をすべて共有しましょう。
社長の報酬や交際費、内部留保などについては、なぜその項目にその金額が必要なのかを社員が納得できるよう説明することも必要です。
また、利益が出ていない部署や新規事業部署、単体で大きな利益を生み出すのが難しい部署に所属する社員がやる気をなくさないよう、公開する数字の分配にも配慮すると良いでしょう。
これまで経営数値を開示してなかった会社が、オープン経営に踏み切るには相当な覚悟が必要かもしれません。
ですが、経営判断に必要な情報を隠しておいて、社員に「経営者感覚を持て」といっても、それは無理な話。
共通言語があって初めて、経営陣も社員も同じ土俵で話ができるようになるのです。
社員を信じて、まずは経営幹部から情報開示を始めてみませんか。
近い将来、きっとあなたの予想を上回る大きな成果が現れると思います。
当社では業績アップに関するノウハウや多角化事業に関するセミナーやワークショップを実施しています。
興味がある方はぜひご参加ください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員
石崎 貴秀
1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。
連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。
入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。