実例に学ぶ!決裁が早まる新規事業計画書の作り方・テンプレートをご紹介
多角化・新規事業

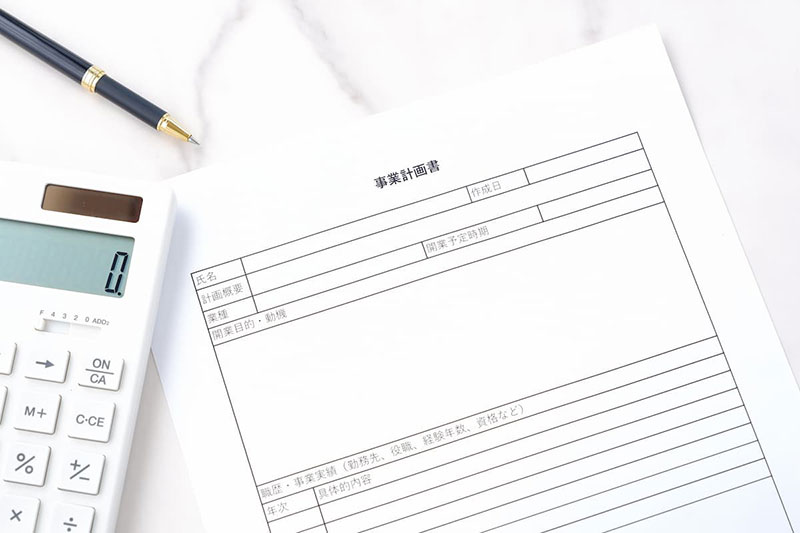
こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。
「現場から新規事業のアイデアは出てくるが、計画書の精度が低く判断に困っている」
「どの項目を整えれば、決裁を早められるのだろうか」
そんな悩みを持つ経営者の方は少なくありません。
一方、現場からは「どの程度の粒度で新規事業計画書を書けば良いかわからない」「提案しても通らない」という声もよく聞かれます。
そこで今回は、経営者が迅速に判断を下せる計画書の作り方について、実例をもとに必要な条件をご紹介。
ヤマチユナイテッドで実際に活用している新規事業計画書のテンプレート&フォーマット構成例や、決裁をスピードアップさせる具体的なポイントを解説します。
現場の熱意を経営判断につなげ、組織全体の挑戦機会を広げるための実践的なヒントになれば幸いです。
目次
- なぜ新規事業計画書が「通らない」のか?まずは原因分析から
- 経営者が一目で判断できる新規事業計画書の条件とは
- 【ヤマチの実例】スピード決裁を生む!新規事業計画書の作り方~テンプレート&フォーマット構成例~
- 新規事業計画書で現場の創造力と経営判断をつなぐ「仕組み」を整えよう
- ヤマチの新規事業計画書の実例とテンプレート&フォーマット構成例を参考に、決裁スピードを改善!
なぜ新規事業計画書が「通らない」のか?まずは原因分析から
新規事業への挑戦意欲がありながら、なぜ多くの新規事業計画書が通らないのでしょうか。
この問題を解決するには、現場と経営層の視点の違いを理解することから始める必要があります。
現場と経営層、それぞれの視点から見る課題
新規事業計画書が通らない原因を整理すると、現場側と経営層側で異なる課題が浮き彫りになります。
現場側の新規事業計画書の課題
「やりたい」という気持ちが先行しがちで、計画の裏付けが不足している状況が多く見られます。
市場調査が甘く、売上予測の根拠が曖昧、成功前提でしか計画を立てておらずリスクを想定していないといったケースが典型例です。
また、「計画書に落とし込む際に、どの程度の粒度で情報を整理すべきかがわからない」という声もあります。
経営層が新規事業計画書に求める情報
一方、経営層が求めるのは、投資対効果、撤退条件、責任体制など、判断に必要な具体的な情報です。
これらが不十分だと「面白そうだが判断できない」「今回は保留に」となり、結果的に提案は却下されます。
こうしたすれ違いによって提案が通らない状況が続けば、新規事業が生まれないのはもちろん、結果として現場の熱が冷め、組織全体の成長機会を逸失する可能性もあります。
特に新規事業の推進を謳って採用した人材にとっては、会社の方針への疑問や不満につながることもあります。
提案プロセスの課題と改善の必要性
特に問題となるのは、決裁に必要な判断材料が不足している状況です。
「この数字の根拠は何か」「本当にこれだけ売れるのか」といった疑問に、根拠を持って答えられなければ、経営層は決裁を下すことができません。
ただし、多くの場合、現場担当者は通常業務と並行して新規事業の検討を行なっているため、最初から全ての情報を網羅した完璧な新規事業計画書を作成することは現実的ではないでしょう。
簡易プレゼンの仕組みが整備されていない組織では、最初から完璧な新規事業計画書を求められたり、どの程度まで精査されていれば足りるのかが不透明だったりすることで、結果として情報が不足してしまうこともあります。
アイデアレベルから段階的にチェックや検討を深めていく仕組みがないと、「新規事業をやってみたい」という熱意があっても形にすることはなかなか難しいでしょう。
そして、「新規事業計画書を出しても通らない」という経験が何度も重なり、現場が次第に提案することをやめてしまうことで、組織全体のイノベーション創出力が低下してしまう危険性があるのです。
経営者が一目で判断できる新規事業計画書の条件とは
それでは、どのような計画書であれば、経営者は迅速に判断を下せるのでしょうか。
ヤマチユナイテッドの実例をもとに、決裁を早める新規事業計画書に必要な条件を整理しましょう。
短時間で全体像がつかめることが最重要
経営者が新規事業計画書を評価する際に最も重視するのは「短時間で全体像がつかめる」ことです。
経営者が知りたい核心的な情報は、以下の通りです。
- 何をやるのか(目的・狙い・解決する課題)
- 会社のビジョンとの整合性
- 投資規模(人・金・時間)の妥当性
- 収益性の見通し(黒字化のタイミング、成長余地)
- 推進体制(責任者・実行メンバー・覚悟)
- 撤退リスク(最悪の損失規模と会社への影響)
会社のビジョンとの一貫性も含めて、なぜ当社がこの事業に取り組むべきなのかを明確に示しましょう。
これらを明確な数字と責任分担を添えて示すことで、経営者は新規事業に安心して「GO」を出せるのです。
【ヤマチの実例】スピード決裁を生む!新規事業計画書の作り方~テンプレート&フォーマット構成例~
ヤマチユナイテッドが実際に使用している新規事業計画書の構成例をご紹介します。
- 【①背景と狙い】どんな課題に対して、なぜこの事業をやるのか?
- 【②ターゲットと提供価値】誰にどんな価値を届けるのか?
- 【③マーケティング・販促計画】どのように認知・集客するのか?
- 【④収益モデルと初期投資】売上・利益・採算のシミュレーション
- 【⑤体制とスケジュール】誰がどのタイミングで動くのか?
- 【⑥リスクと撤退基準】どこで判断を下すのか?
この6つの構成要素に従って計画書を編成することで、決裁に必要な情報を漏れなく整理し、経営判断を加速することができるでしょう。
【①背景と狙い】どんな課題に対して、なぜこの事業をやるのか?
新規事業計画書の第一項目では、単なる売上増加ではなく「なぜ当社がこの事業に取り組むべきなのか」を明確に示す必要があります。
- 会社のパーパス・ビジョンとの関連性
- 解決したい課題の明確化
- この事業を通じて実現したい価値
ヤマチユナイテッドは「北海道からいろんな世界を変えていく」というパーパスを掲げており、新規事業はこのパーパスとの整合性を必ずチェックしています。
新規事業が単なる売上拡大ではなく、会社の理念実現の手段として位置付けられていることが重要です。
例えば、「警備事業」の提案であれば、「警備事業の3Kイメージを変え、かっこいい警備会社を生み出す」といった、会社の価値観と合致するものであれば、取り組む価値のある新規事業として評価されるでしょう。
【②ターゲットと提供価値】誰にどんな価値を届けるのか?
この項目では、感覚的な予測ではなく具体的な調査結果に基づいた裏付けを示すことが重要です。
- ターゲット顧客像
- 提供するサービスや価値
- 市場調査・リサーチ結果
- 競合との違い
- 自社の強みと勝てる理由
売上数字の根拠が最も問われる部分です。
「同エリアでも実績があり、これだけ販売できている」「他県での成功実績がある」など、具体的な成功事例も含めて、市場性を証明しましょう。
【③マーケティング・販促計画】どのように認知・集客するのか?
ターゲット設定と収益計画をつなぐ重要な要素として、マーケティング戦略の具体化が求められます。
- 立ち上げ時の告知・認知施策
- 集客手法選択(SNS、チラシ、DMなど)と予算配分
- 販促活動のスケジュール
- 集客目標とKPI設定
「いつ、どんな手法で、いくらかけるのか」を具体化することで、売上予測の信頼性が増します。
【④収益モデルと初期投資】売上・利益・採算のシミュレーション
収益構造の設計では、単体での収益性だけでなく他事業への波及効果も含めて評価されます。
- ビジネスモデルの詳細設計
- 収益構造(単価×数量の根拠)
- 初期投資額の内訳
- 投資回収計画
- 3年間の売上・利益予測
特に「誰に、何を、いくらで販売して、どれだけ売り上げるのか」という基本的なビジネスモデルと、「コスト構造(仕入れ原価、外注費、人件費、広告費)」を明確にすることが求められます。
相乗効果(シナジー)の観点も重要で、他事業につながっていく可能性や既存顧客への紹介効果なども評価されます。
例えば、「インテリアショップ」を想定した新規事業計画の場合、インテリアショップ単体の収益性は限定的で、そこまで高くはありません。
しかし、そのブランドを活用して住宅ブランドを展開すれば10億円規模の売上を生み出せる、といった組み合わせ効果まで設計・提案できれば、「規模の大きな事業になる」という判断につながります。
投資回収計画について詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。
投資回収計画とは?収支計画との違いや計画を立てる際のポイントも
【⑤体制とスケジュール】誰がどのタイミングで動くのか?
経営者が最も重視するのは「誰が責任を持って動くのか」という点です。
- 立ち上げ時の組織体制
- 責任者と管理体制の明確化
- 将来の組織図(スケール時)
- 事業化までのロードマップ
- 人員計画と採用方針
「責任者は誰か」「どのような体制で推進するのか」は必ず確認される項目です。
立ち上げ当初の組織体制だけでなく、「最初は兼任だが、最終的に責任者を配置して多店舗化していく」といった、将来の組織ビジョンまで含めて示すことが求められます。
【⑥リスクと撤退基準】どこで判断を下すのか?
成功前提だけでなく、うまくいかなかった場合には撤退の想定も必要です。
- 想定されるリスクと対策
- 80%達成・50%達成時のシナリオ
- 最悪のケースでの損失予測
- 撤退を検討する条件
- 他事業への影響度
現場は成功前提で計画を立てることがほとんどですが、経営者は「最悪の場合、どれだけの損失が発生するのか」「会社にどのような影響を与えることになるのか」を事前に把握しておく必要があります。
「最悪でもこの程度の損失に収まる」という安心材料があれば決断しやすいでしょう。
新規事業の撤退基準、判断軸について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。
企業の成長を促進させるための新規事業、うまくいかなかった時の撤退基準、判断軸とは?
経営者・決裁側がチェックすべき追加の視点
経営者・決裁者が注意すべき補足視点も知っておきましょう。
財務的な視点
新規事業が会社全体の財務状況に与える影響を慎重に評価する必要があります。
資金調達方法の選択、バランスシートへの影響度、資金繰りへのインパクトなどを確認します。
管理体制の視点
既存事業と異なる勤務形態を伴う事業の場合、労務規定の変更や分社化の検討も必要になるケースがあります。
管理部門のチェックを経ることで、実行段階でのトラブルを未然に防げます。
新規事業計画の立て方・作り方については、以下のコラムでも解説していますので、あわせてご確認ください。
事業計画の立て方・作り方を解説!ヤマチの事例と重要なポイントも紹介
新規事業計画書で現場の創造力と経営判断をつなぐ「仕組み」を整えよう

新規事業計画書を適切にチェック・検討・進行する仕組みを整備することで、現場のアイデアを経営判断につなげ、組織全体の挑戦機会を最大化することができます。
新規事業計画書のテンプレートで完成度をアップし、判断スピードを向上
新規事業計画書の完成度が高まることは、「判断の速さ=挑戦機会の数」を飛躍的に増加させます。
テンプレート・フォーマット構成例などを活用し、必要な項目を網羅した新規事業計画書が作成できるようになれば、経営者は迷うことなく判断を下せます。
これにより、より多くのアイデアが実現される機会が生まれ、組織全体の成長につながります。
段階的な挑戦プロセスの構築と可視化
一度で完璧な計画書を求めるのではなく、段階的にチェックを深めていく仕組みが重要です。
ヤマチユナイテッドでは、以下の段階的なプロセスを設けています。
- 事業部内での仮プレゼン
- 全社経営会議での本プレゼン
- 管理部との調整
- 最終決裁
このような仕組みがあることで、最初から全ての情報を完璧に揃える必要がなく、段階的に精度を高めていけます。
さらに、新規事業の検討・立ち上げプロセス、進捗状況を適切に共有することで、組織全体で挑戦を応援する機運も高まるでしょう。
ヤマチユナイテッドでは新規事業の提案状況を、月1回のオンライン朝会で「アイデアベース112案、仮プレゼン通過3案、事業化2案」といった具体的な数字で全社員に共有しています。
このような透明性により、却下される不採用のケースも含めて採用確率がわかり、モチベーションを下げずに新規事業提案に取り組むことができるのです。
明確な仕組みが整備されることで、経営者は「失敗を恐れずチャレンジしてほしい」と現場に伝えることができ、組織全体が挑戦を歓迎する空気に変わっていきます。
なお、新規事業を含め、社員が自ら事業計画を立てる、ひいては経営に参加していくことは、会社が成長していく上で欠かせません。
社員に権限を委譲して自主的に回してもらう仕組みがあれば、経営者も安心して仕事を任せることができます。
ヤマチユナイテッドでは、この全員参加型経営をヤマチ流にシステム化し、「システム経営」と名付けています。
詳しくは、「社員が経営参画できる「システム経営」とは? 《連邦・多角化経営概論》第2回」もぜひご覧ください。
ヤマチの新規事業計画書の実例とテンプレート&フォーマット構成例を参考に、決裁スピードを改善!
新規事業計画書が通らない最大の原因は、経営層が求める判断材料と現場が提供する情報のミスマッチにあります。
ヤマチユナイテッドが実際に使用している新規事業計画書の構成例で示した6つの構成要素を活用することで、経営者が短時間で的確な判断を下せる計画書を作成できます。
- 背景と狙い
- ターゲットと提供価値
- マーケティング・販促計画
- 収益モデルと初期投資
- 体制とスケジュール
- リスクと撤退基準
重要なのは、成功前提だけでなく、リスクシナリオも含めて検討し、会社のビジョンとの一貫性を明確に示すことです。
適切なテンプレートと段階的な承認プロセスを整備することで、現場の創造力を経営判断につなげ、組織全体の挑戦機会を最大化できるでしょう。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員
石崎 貴秀
1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。
連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。
入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。

