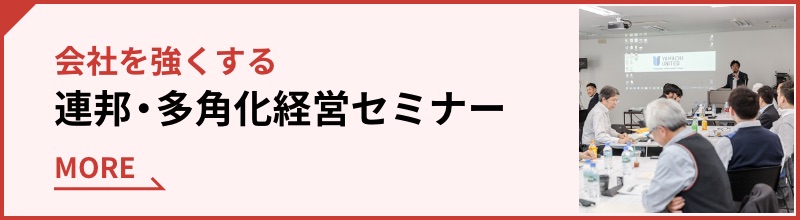モラールとは?モラールサーベイのメリットや活用方法も解説!
理念・社風


こんにちは、ヤマチユナイテッドの山地です。
「楽しそうに働いた社員が、突然辞表を出してきた」
「経営者として努力しているつもりだが、一向に社員がやる気をもって働いてくれない」
こんな悩みを抱えている経営者は少なくありません。
その原因は、社員の本音を経営者が把握していないことにあります。
多角化経営が進めば進むほど、従業員が増えて接点も少なくなっていくので、社員の本音は見えづらくなっていくものです。
そこでおすすめしたいのが「モラールサーベイ」です。
今回は、モラールの意味やモラールサーベイの重要性・メリット、モラールサーベイの活用方法や実施する際の心構えなどについてご紹介しましょう。
目次
- モラールとは?モラル・モチベーションとの違い
- モラールサーベイとは?そのメリットも解説!
- モラールを高めるモラールサーベイの活用方法
- モラールサーベイを導入する際の心構え
- モラールとは組織の士気のこと!モラールサーベイで社員の不満を受け止めよう
モラールとは?モラル・モチベーションとの違い
モラールサーベイについて説明する前に、まずはモラールから説明していきましょう。
モラールとは組織の「士気」のことで、特に会社では「勤労意欲」という意味合いで使われます。
一般的にモラールが高い組織には、メンバーが集団に対して帰属意識や忠誠心があり、熱意を持って集団の目標達成を目指しているなどの特徴があります。
そのためには共通の目標があること、良いリーダーがいること、情報共有が十分にされていること、評価や報酬の決定方法が公平であることなどが必要といえるでしょう。
モラールに近い言葉に従業員満足度(ES)がありますが、それについては「従業員満足度(ES)向上のための取り組み事例やメリットを紹介!」もあわせてご覧ください。
「モラル」との違いとは?
モラール(morale)とモラル(moral)はよく似た発音の言葉ですが、意味が異なります。
モラルとは道徳や倫理という意味で、会社が社会的に守るべき道徳のことを指します。
問題があればただちに対応する体制を整え、責任所在を明確にしておくなど、相手先の都合を最優先にできるのが企業モラルに優れた企業だといえます。
モラールが集団的な意識や感情に対する概念であるのに対して、モラルはクライアントや社会に対する企業の態度や体制のことを指すことが多いです。
「モチベーション」との違い
モラールが組織や集団としての士気や意欲を指す言葉なのに対して、モチベーションは個人の意欲に関する概念です。
モラールは集団に対する充足感や一体感なども含めた概念で、モチベーションは目標達成に向かう個人のエネルギーに焦点をあてた言葉という点で異なります。
モラールサーベイとは?そのメリットも解説!
モラールサーベイとは、簡単に言うと社員のモラールを測定するための意識調査であり、企業の組織、職場管理に対して従業員がどういう点にどの程度満足し、どんな問題意識をもっているかを科学的に調査分析する手法です。
一般的には「従業員意識調査」と呼ばれることもあります。
モラールサーベイを行うことで、組織の課題を把握・分析し、改善につなげ、組織の結束力を高める目的があります。
当社では、毎年一度、全社員を対象にモラールサーベイを実施し、その結果や推移を分析して、経営に活かしています。
中小企業でモラールサーベイを実施している会社はあまり多くないと思います。
私のまわりでもあまり聞きません。
しかし個人的には、10人以上社員がいるのであれば、モラールサーベイをしたほうがいいと思っています。
モラールサーベイを行うべき、4つのメリットも確認しましょう。
メリット①社員1人1人の改善点を指導できる
モラールサーベイをすると「コミュニケーションがうまくいかない」「○○のスキルが低い」といった個人の改善点が浮かび上がってきます。
直属の上司について「意見を聞いてくれない」「どう評価されているかわからない」「コミュニケーションがない」といった不満をストレートに書いてくる人もいるのです。
中には用紙の裏までびっしりと不満を書いてぶつけてくる人もいます。
社員1人1人の改善点を人事に活用するのはもちろんのこと、日々の指導にも反映させることができます。
一人ひとりが自分の足りないところを解消することができるので、人材育成につなげることが可能です。
モラールサーベイの平均点を上げていくことによって、組織力もアップしていきます。
メリット②社員の本音を把握・改善して組織力アップ
モラールサーベイの重要なメリットは、社員の不平不満や不安などの本音を把握できる点です。
モラールサーベイには自由意見を書く欄もあるので、会社にとって辛辣な意見や不満が書かれていることがあります。
実際、当社でも、匿名でないにもかかわらず、カチンとくるようなことを書いてくる社員は少なくありません。
社員から出た不満の声を読んでいると、「なぜこんなレベルが低いことを言うのか」「なぜ会社に感謝してくれないんだと」と、腹が立つかもしれません。
ですが、それが現実なのです。
モラールサーベイは経営に対する一種の成績表です。
結果を分析すると、社員のやる気がアップしない、会社が成長しない理由が見えてきます。
それらをいったん受け止めて、必要であれば経営計画に課題として落とし込んでいく。
そうすることによって、社員のやる気がアップし、会社も成長していきます。
メリット③大きい組織でも社員とコミュニケーションが取れる
社員の不満が解消されると満足度が上がり、新規事業を作って会社を拡大する「連邦・多角化経営」もうまくいきます。
多角化経営を進めると会社の規模も大きくなり、社員数も増えていきますが、こうなると社員1人ひとりと十分なコミュニケーションを取るのが難しくなってきます。
社員数がまだ少なくて、経営者が毎日社員とコミュニケーションをとれている会社であれば、モラールサーベイの必要はないでしょう。
しかし数十人、数百人と会社の規模が大きくなっていくと、経営者は社員が不満をため込んでいることを知らないままになっている可能性もあります。
そのままにしておくと早期離職につながる可能性もあるため、社員の本音を知って改善することは必須といえるでしょう。
物理的に可能であれば、1年に一度、面談をして社員一人ひとりの話を聞く機会を設けると良いでしょう。
社員の本音を知る絶好の機会となります。
しかし、会社の規模がそれなりに大きくなれば、社員一人ひとりに会社の課題を聞いてまわるわけにはいきません。
経営課題を発見するには、モラールサーベイのようなアンケート形式の仕組みを導入するのが合理的です。
早期離職への対策についてはこちらもご覧ください。
新入社員の早期離職対策とは?面談制度「フレッシャーズサポート制度」を紹介
従業員満足度(ES)向上のための取り組み事例やメリットを紹介!
メリット④社員に経営への参加意識を持たせられる
モラールサーベイを実施したうえで連邦・多角化経営を進めることは、社員に「会社はこれから良い方向に変わるのだな」という印象を持ってもらえる効果もあります。
会社が社員の意見を吸い上げて、その課題を解決しようという姿勢を見せているわけですから、社員は経営への参加意識を持ち、改革にも協力的になってくれます。
経営者と幹部が変えるのではなく、自分たちも経営に参加して一緒に変えていくんだという雰囲気をつくることができる、というわけです。
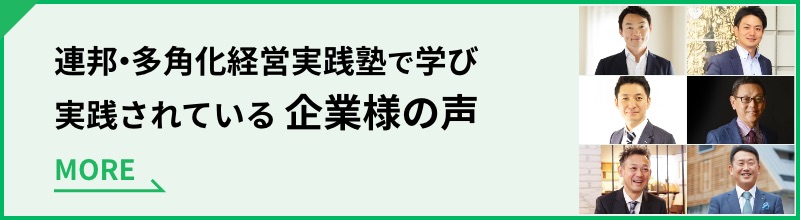
モラールを高めるモラールサーベイの活用方法
モラールサーベイを実施することは、経営改革を進める上でも役立ちます。
結果を分析することによって、経営課題や改善テーマが浮かび上がってくるからです。
当社で実際に行なっているモラールサーベイの活用方法をご紹介しましょう。
モラールサーベイ実施の目的やルールを宣言する
当社の「連邦・多角化経営実践塾」では、これから連邦・多角化経営を採り入れようとしている参加者の皆さんに対して、まずは社内でモラールサーベイを実施してもらっています。
その際は必ず、「連邦・多角化経営を採り入れるから社員のみんなにも経営に参加してほしい」と社内で宣言してから、モラールサーベイを実施してもらいます。
その際に、不平や不満を書いてきたからといって、評価や給料が下がったり、待遇が不利になったりすることはないと社員に約束することもポイントです。
すると、社員から「こうしてほしい」「このままの状態では連邦・多角化経営などできない」といった声が出てくるので、それらを課題として設定し、改善していくのです。
解決すべき経営課題を明確にする
連邦・多角化経営を実践する前に、経営者や幹部が社員の不満を知ることによって、解決すべき課題やテーマがはっきりします。
実践塾に参加し、モラールサーベイを実施した企業の皆さんからは、「社員がこんなふうに思っているとは、まったく気づかなかった。」という感想を聞くことが少なくありません。
社員の本音を知ることができて良かったと思うと同時に、調査の点数が経営者が予想していたよりも低くてがっかりすることも多いでしょう。
「5点満点中3点なのはなぜか。もっと社員は満足してくれていると思っていたのに...」と。
しかし、ここで浮かび上がった課題を解決して、社員の満足度を上げることによって、連邦・多角化経営もうまくいきます。
つまり、モラールサーベイは、経営課題と向き合うことに直結するのです。
社内改革の根拠にする
例えば、モラールサーベイによって「会社の雰囲気が悪い」という課題が浮き彫りになったとします。
そんなときは、経営者は社員の前でこう言います。
「モラールサーベイによると『会社の雰囲気が暗い』『挨拶が少ない』『社員同士のコミュニケーションが不足している』という声が多かった。会社の課題はいまの社内の雰囲気を改善することだと、皆さんに気づかせてもらった。だから、まずは挨拶運動から始めよう」
この場合、社長が思いつきで「挨拶運動を始めよう」と宣言したわけではないという印象を持たせることができます。
「社員みんなが社内の雰囲気について問題意識をもっているのだから、みんなで解決していこう」という論理に落とし込むことで、自然と社員の参加意識を高められるのです。
また、モラールサーベイで「給料が低い」という不満が多かったとすれば、このような言い方ができます。
「なぜ給料が少ないかというと、生産性が低いからです。これからみんなで生産性を上げられるよう工夫していこう」
つまりは、モラールサーベイの結果は、改革や改善のための根拠にもなるのです。
一般的に社員は「社長がなんとかうまくやってくれるのではないか」という甘い考えをもっているものです。
しかし、このように社員の声を吸い上げたという格好をとれば、社員が自ら動かざるを得ません。
連邦・多角化経営は、全社員の経営参加が原則です。
社員の意見を聞いて経営への参加意識を高めることは、多角化経営の実践に必要不可欠なスタンスだといえるでしょう。
役員全員で調査結果に対応する
実務的なことをいえば、モラールサーベイは社長一人だけでなく、役員全員で対応するのが原則となります。
後で詳しく解説しますが、モラールサーベイで出てきた社員の声にはすべてリアクションを返す必要があります。
複数の役員で分担することで役員全員に会社の課題を共有できるだけでなく、社長の負担を減らすこともできます。
「役員がモラールサーベイの結果を見るとなると、本音で書いてくる人が少なくなる」と心配する人もいるようです。
ですが、「役員以上が見ます」と事前に断っておけば、社員も見られる前提で書いてきますし、ストレートに厳しい意見を言ってくるものです。
モラールサーベイを導入する際の心構え
モラールサーベイを導入するメリットや活用方法を見ると、「ぜひ導入してみたい」と考える方もいらっしゃると思います。
しかし、残念ながらモラールサーベイを導入しただけで簡単にメリットを得られるわけではありません。
導入する際には次のような心構えが大切です。
経営者は社員の不満を受け止める覚悟を持つこと
モラールサーベイを導入すると決めたら、経営者には社員の不満をしっかりと受け止める覚悟が必要になります。
なかには、耳の痛いことやカチンとくるようなことを書いてくる者もいます。
「何を勝手なことを言っているんだ!」と怒鳴りたくなる衝動にかられるかもしれませんが、こちらの説明が足りないだけかもしれません。
コミュニケーションが足りなくて、勘違いをしているケースも往々にしてあります。
とにかく社員が不満をため込んでいる状態が一番良くありません。
社員の不満は経営の課題ととらえる必要があるでしょう。
例えば、当社のモラールサーベイには「待遇についてどう思いますか?」という設問があり、必ず給与などの不満を書いてくる人がいます。
こうした「待遇が悪い」という不満に対しては、ケースごとに個別に検討することになります。
工事部門の社員が「自分の車を使って工事現場を毎日のようにまわっているのに、そのわりには車両手当てやガソリン手当が少ない」という不満を書いてきたとします。
事実と照らし合わせて正当な主張であることが分かれば、手当を増やす方向で対応すると良いでしょう。
また、中途採用で入社してきた社員が「他の社員に比べて給与ベースが低い」という不満を書いてくる場合もあります。
もちろん、根拠もなく「給料が低い」と言ってきた場合には対応できません。
何と比べて低いと言っているのかによって話は違ってきます。
隣で働いている人と比べてなのか、友人なのか、他の会社の人なのか...。
その人の今の働きに給与が見合っているかどうかという視点をもって面談したり、事実関係を調べたりして、主張が正当であると判断できれば、ベースアップするなど調整します。
社員の声にはすべてリアクションすること
モラールサーベイの結果を受けて、このように個別対応するパターンは結構あります。
会社側が社員の声を素直に聞き入れる気持ちがないと、モラールサーベイはうまくいかないでしょう。
社員のわがままや理不尽な要求まで聞き入れるわけにはいきませんが、基本的に、社員の声には全て対応するという前提で臨むことが大切です。
「何回も書いているのに、会社は何も対応してくれない」と不満をためることになれば、社員は本音を書いてくれなくなってしまいます。
そうなれば、せっかくのモラールサーベイも宝の持ち腐れです。
社員の不満を実際に解消できるかどうかは別として、なんらかのリアクションを返して、「キミの声は届いている」というメッセージを示す必要があります。
意外と「不満を聞いてもらえた」というだけで満足する人は少なくありません。
モラールとは組織の士気のこと!モラールサーベイで社員の不満を受け止めよう
モラールとは組織の「士気」や「勤労意欲」のことで、道徳・倫理という意味のモラルや個人のやる気を指すモチベーションとは異なります。
会社の組織や職場管理についての従業員の満足度を調査するモラールサーベイを実施することで、社員が持つ問題意識や不満などを知って改善につなげることができます。
モラールサーベイのメリットには、社員一人ひとりの改善点を見つけ、組織に対する不満などの本音を把握して組織力を向上させられること。
また、組織が大きくなっても社員とコミュニケーションを取るツールにすることができ、社員に経営への参加意識を持たせることもできます。
「社員の気持ちはよくわかっている」と言う経営者ほど、実はまわりがよく見えていないものです。
社員の本音を吸い上げるモラールサーベイのような仕組みを導入して、今まで気づかなかった課題を明確にし、社内改革の根拠にすることで、組織力をアップさせましょう。
一つひとつの意見に対応したり、会社の経営課題として解決に取り組むのは、面倒なことかもしれませんが、それと引き替えに社員の経営への参加意識が高まるはずです。
あなたもぜひ、モラールサーベイの導入を検討してみてください。
当社では、良い社風をつくるノウハウや多角化事業に関するセミナーやワークショップを実施しています。
興味がある方はぜひご参加ください。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。