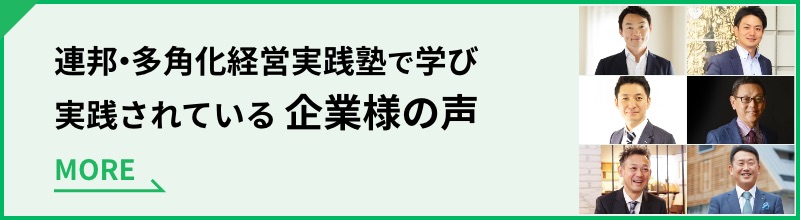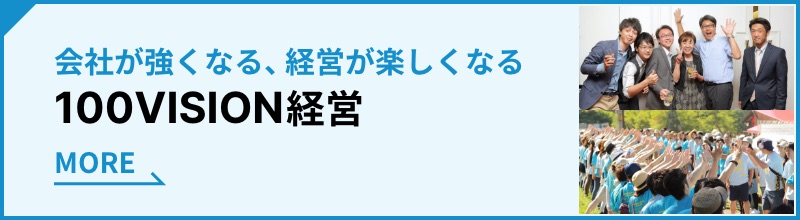組織を育てる社長の特徴は?これからのリーダーの役割は「支援者」
組織・給与制度

こんにちは、山地です。
経営者の中で「自分はワンマン経営ではない」と言い切れる方はいるでしょうか?
中小企業の場合、もしかしたら意外に少ないのではないでしょうか。
確かに、トップダウンの経営は効率的かつスピーディーです。
けれども私は、数人で運営している会社や創業時ならともかく、社員が20名以上になったら、組織による経営をするべきだと考えています。
カリスマ社長頼みの経営では、遅かれ早かれ会社はダメになってしまうでしょう。
組織を育てるための経営者の役目とはどういうものなのか、知っておかなければなりません。
今回は、組織を育てるリーダーシップについてお話しします。
経営者に必要な役割や、組織を育てるポイントとはどのようなものなのでしょうか。
目次
1.組織を育てる社長の役割は「支援者」であること
組織を育てるためには、社員を育てることが欠かせません。
人が育つと組織力が高まり、社内のコミュニケーションが活発になったり社員のモチベーションがアップするといったメリットが生まれます。
私が目指しているのは、トップが指示して部下に思い通りのパフォーマンスを出してもらうトップダウン経営ではなく、幹部中心にいろいろ相談して運営していく経営です。
これは、自律型社員を育てる経営でもあります。
この場合、社長に必要なのは「支援者」のスタンスです。
20年ほど前にそれに気づいて以来、私は経営がとっても楽になりました。
『リーダーシップ3.0 ―カリスマから支援者へ』(小杉俊哉、祥伝社新書)の中でも、社員を支援する新しい経営者像が紹介されています。
この書籍の主張も参考にしながら、組織を育てるリーダーの役割や実際の経営事例などについて、さらにお伝えしていきましょう。
組織を育てる経営者に必要なもの
本書の中では、リーダーシップを3つの段階で説明しています。
旧来の中央集権型の「リーダーシップ1.0」。
スティーブ・ジョブズのような変革型の「リーダーシップ2.0」。
そして現在、必要とされている支援型の「リーダーシップ3.0」。
従来のリーダーは、一般的に決断力があって、メンバーを1人でぐいぐい引っ張っていく強さが必要だと考えられてきました。
しかし、「リーダーシップ3.0」では、リーダーがチームのメンバーを支援することを重視すると述べられています。
さまざまな能力や可能性を持ったメンバーが十分に力を発揮できる環境を整えることで、チーム全体の能力を上げていく。
それがリーダーの大切な役割だというのです。
「セムコ」社の例から見る、組織を育てる新しい経営の仕組み
本書では「リーダーシップ3.0」の例として、元サッカー日本女子代表監督の佐々木則夫氏や、スターバックスコーヒー、ザ・リッツ・カールトンなどの企業が挙げられています。
なかでもブラジルの「セムコ」という企業は、究極の「リーダーシップ3.0」を実現していると言います。
「セムコ」ではどのような経営が行われているのでしょうか。
「セムコ」は、多様な業種を扱うコングロマリットで、約3,000人の社員を抱える大企業。
学生が就職したい企業ナンバーワンに輝いたこともある人気企業です。
「セムコ」では、経営者は「人の行動を監視することは、窃盗よりも危険な行為」とまでいっています。
同社の多角化経営の特徴は、社員をコントロールしないこと。
ノルマやマニュアルもなければ、組織図や人事部さえない。
社員を管理する仕組みが全くなく、社員の自主性に任されています。
例えば、出張旅費の精算も「いくらまで」という明確なルールがあるわけではなく、社員の自主性に任せる。
管理部門を置くコストがもったいない、というわけです。
性善説にもとづいた経営は、不正が起きないか心配になる経営者の方も多いでしょう。
しかし、社員同士が数字を自主管理すると同時に、お互いを牽制しているので、意外とそうした問題は起きないとのこと。
むしろ社員のモチベーションを上げることに成功しています。
2.支援者の役割を果たしながら組織を育てるポイント
セムコ社ほどではありませんが、当社も社員一人ひとりが主体性をもって利益を出すために知恵を絞り、それを社長である私が下支えするという経営をこれまで実践してきました。
当社が実践してきた全員参加型経営の「システム経営」も、支援型という意味で「リーダーシップ3.0」の一種といえます。
ここからは、当社の事例を参考に、組織を育てる経営のポイントをご紹介します。
指示せず権限を委譲する
もし本気で人を育て、組織を育てたいならば、仕事を部下に任せて権限を委譲し、どんどん失敗を経験させるべきでしょう。
当社では多角化を目指して、既存事業のほかに新規事業を数多く立ち上げ、軌道に乗せてきました。
新規事業のタネを見つけてきて、芽が出るまで育てるのは経営者の大切な仕事なので、企画段階から事業責任者を任命しつつ私自身も実務に関わります。
しかし、いったん事業が軌道に乗ったら実務から身を引き、あとは事業責任者に任せます。
こうすることで、私は次の新規事業のタネを探すことに注力することができ、部下はたくさんの失敗を繰り返しながら成長していくことができるのです。
ところが多角化がうまくいかない経営者は、ついあれこれ指示を出してしまって部下に任せることができません。
このやり方だと、部下は経営者の顔色ばかり伺う「指示待ち人間」になってしまいます。
組織を育てるために大切なのは、仕事を任せたら口出ししたい気持ちを抑え、権限を委譲することなのです。
我慢して答えを与えない
人を育て、組織を育てるためには、経営者の我慢が必要です。
社員を見ていると「自分のやり方のほうが売上が増える」と思ってしまい、「あれをやれ」「これはやったらダメだ」といいたくなる時もあるでしょう。
経営者が指示を出すと一時的に業績は上がるかもしれませんが、結局社員は成長できなくなり、いつまでも経営者が実務まで行わなければならなくなります。
大切なのは、部下に考えさせること。
私の場合、さすがに180度違う方向へ行こうとしていたら軌道修正を促すこともありますが、基本的には部下のやり方に委ねています。
うまくいかなかった時も答えを与えるのではなく「どうしたらもっと売上が伸びると思う?」などと質問して気付きを促します。
経営者は自分がやるほうが早いと思っても、グッとこらえて部下に任せましょう。
部下は自分で考え、悩み、苦しむかもしれませんが、そうした濃い経験が部下を成長させます。
人は失敗を通じて成長していきます。
経営者の我慢が部下を育てることにつながるのです。
責任は経営者が取る
仕事は部下に任せますが、責任まで押し付けてはいけません。
責任を押し付けてしまうと、部下は失敗を恐れて小さくまとまってしまうからです。
失敗したときの責任は「丸投げ」した経営者にあると考えましょう。
「俺が責任をとるから思いっきりやれ」ということですね。
責任は経営陣にあるということを、部下に伝えておくことがポイントです。
そもそも、失敗したからといって会社全体の信用が失墜するケースはごくまれです。
小さな損害よりも、部下が成長して会社が拡大していくことに目を向けましょう。
当社が実践している「システム経営」とはどんなものか、社員の自主性を育てる方法などについては、こちらもぜひご覧ください。
社員の自主性と主体性を育てる方法は?メリットや成功させるポイント《システム経営の3本柱》 第1回:自主計画
3.組織を育てる社長になるには「支援者」の役割を果たそう
組織を育てる経営者に求められるのは、支援者のスタンスです。
究極の「リーダーシップ3.0」を実現しているという「セムコ」では人事部も組織図もありません。
社員の能力や可能性が十分に発揮される環境を整え、業務を社員の自主性に任せることで、モチベーションの高い組織が作られています。
経営者が支援者として人や組織を育てるポイントは、指示せず権限を委譲し、答えを与えず考えさせ、社員に失敗を経験させること。
仕事は任せても責任は押し付けないことに注意しましょう。
社長は社員やメンバーをコントロールしようとせず、支援に徹する。
これからの新しい経営スタイルとして定着していくような気がしています。
私は経営者に支援者としての役割が求められていると気づいてから、とても気持ちが楽になりました。
中小企業の組織づくりのお手伝いができれば、と「連邦・多角化経営実践塾」を始めたのも、そうした私自身の経験があったからです。
経営者はぐいぐいと引っ張る先導者でなくても良い。
後ろから支えにまわる支援者であれば良い。
まずは、意識を変えてみてください。
ヒントを簡単にひとつだけいうと「なんでも自分1人で決めないで、周囲に相談し巻き込んでみる」こと。
それだけで組織に変化が生まれていくでしょう。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

ヤマチ連邦多角化経営実践塾 塾長
山地 章夫
ヤマチユナイテッド代表。経営を楽しみ、社員820名、50事業・年商258億円の企業グループの舵を取る。本業を中心に事業を次々と立ち上げ、売上げを積み増す「連邦多角化経営」を実践。経営の安定化と人材育成を両立する独自の経営手法が、多くの中小企業経営者の注目を集める。