現代型ワンマン経営とは?社員がついていけないワンマン社長の末路と対策
組織・給与制度


こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。
経営者が「うちの会社はうまくいっている」と思っていても、本当にそうでしょうか。
もしかすると、社員が本音を言えずに静かなだけで、実は「現代型ワンマン経営」に陥っている可能性があります。
怒鳴らない優しい社長であっても、構造的にワンマン経営になっているケースは少なくなく、そのままでは社員から「ついていけない」と思われてしまう危険性があります。
今回のコラムでは、現代型ワンマン経営の特徴や社員心理、静かな組織の危うさ、そしてワンマン社長が迎える末路についてお話します。
「実質ワンマン経営なのでは?」と不安を抱える経営者の方に、社員の自律を育てる組織変革への具体的な道筋をお伝えします。
ワンマン経営から脱却できる会社の特徴についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
- 「現代型ワンマン経営」とは?独裁でなくても社員がついてこない理由
- 社員が「ついていけない」と感じる瞬間とは?静かな組織の危うさ・ワンマン社長の末路
- なぜ「ワンマン経営」から脱却できる会社とできない会社があるのか?
- 脱・ワンマン経営への第一歩!社員の自律性を育てる組織改革の流れを3ステップでご紹介
- ワンマン経営の末路を避けるには、社長の覚悟と組織改革が必要
「現代型ワンマン経営」とは?独裁でなくても社員がついてこない理由
「ワンマン社長」と聞くと、昔ながらの強権的なリーダー像を思い浮かべる方が多いかもしれません。
社員を怒鳴りつけたり、意見を聞かずに独断で決めたりする姿です。
ところが近年では、そのようなわかりやすい独裁型の社長は少なく、代わりに増えているのが「優しいワンマン社長」です。
ワンマン経営の本質的な定義から確認
ワンマン経営とは、社員が意思決定に関われず、判断・決裁権・責任が社長に集中している状態を指します。
社長が最終判断を担うのは当然ですが、そこに至るまでのプロセスが一方通行なら、それは「ワンマン経営」といえるでしょう。
- 見た目は穏やかで社員の話にも耳を傾けているように見えても、意思決定のプロセスをたどると最終的には全てが社長に集中している
- 社員が「相談」しているように見えても、実態は判断を仰いでいるだけで双方向の議論にはなっていない
- 会議では「社長が決めたことを伝えるだけ」に終始し、社員が考え、意見する余地はほとんどない
このように、態度が柔らかくても意思決定の構造が一方通行であれば、それは「現代型ワンマン経営」なのです。
ワンマン経営自体がダメなわけではないが、限界が来る
創業期には、社長のリーダーシップで率いるトップダウンのワンマン体制が自然に機能します。
社員数が数名から十数名程度なら、社長が一手に判断することも可能で、それはむしろスピード感があるでしょう。
しかし、組織が拡大し、事業や拠点が複数に分かれていく段階で同じやり方を続けていると、社長がボトルネックになり、どこかで限界が来てしまうのです。
トップダウン経営自体が必ずしも悪いというわけではありません。
トップダウン経営とボトムアップ経営の違いについては、こちらのコラムで詳しく解説しています。
トップダウン経営とボトムアップ経営(社員参加型経営)の違いとは?
社員が「ついていけない」と感じる瞬間とは?静かな組織の危うさ・ワンマン社長の末路

社員が社長についていけないと感じるのは、必ずしも厳しい言葉を浴びせられたときではありません。
むしろ「何を言っても変わらない」「どうせ決まっている」と悟ったときに、諦めが芽生えます。
諦めの蓄積が生む悪循環
意見を出しても「それは違うから」と片づけられたり、結論が覆る理由が説明されなかったりすると、社員は次第に発言しなくなります。
やがて社内は波風が立たない「静かな組織」になりますが、これは決して健全な静けさではありません。
そもそも、何も言わなくても社長が全部決め、それで会社が回っている状況は社員にとっては楽ですし、社長も機嫌が良い状態が続きます。
しかし、その結果、社員はだんだんものを言わなくなり、波風が立つことを避ける雰囲気が強まっていくのです。
問題提起がなく、提案も生まれない状態は、表面的な平穏と引き換えに社員の主体性が奪われているサインです。
「任せたつもり」問題の深刻さ
現代型ワンマン経営で多いのが、「任せたつもり」問題です。
よくあるパターンは、指示命令でやらせている状態。
社長にとっては任せているつもりでも、実際は細かく口を出して裁量権も渡していないなら、実行部分をやってもらっているだけで、実際には任せていないのと同じです。
また逆に、責任の範囲や判断基準を示さず、丸投げするパターンもあります。
この場合、失敗の責任所在が不明確となり、社員にとっては不安要素となるでしょう。
どちらの場合も、社員は「余計なことをしないほうが無難だ」と考えるようになり、指示待ちの姿勢が定着してしまいます。
ワンマン経営の限界と末路
ワンマン経営が続く会社の未来に待っているのは、成長の限界です。
会社が大きくなって新規事業や新たな支店を展開しても、任せられる人材が育っていなければ、結局は社長が全てを兼任することになります。
そうなると社員は指示待ちのままで、社長だけが疲弊していきます。
ここで突然、社員に仕事を任せようとしても、今まで指示待ちで仕事をしていた社員は「考える仕事が増えた」「どうしてそこまでしなくてはならないのか」という思考回路になってしまいます。
「今までどおりが良い」「責任を負いたくない」と考える社員は離職するかもしれません。
その結果、後継者が育たず、事業承継が困難になることもあります。
これが「ワンマン経営の末路」です。
最初は強いリーダーシップで会社を引っ張っても、社長の体力やキャパシティに限界が来たとき、「頼れる人材がいない」という現実に直面してしまうでしょう。
なぜ「ワンマン経営」から脱却できる会社とできない会社があるのか?
同じような現代型ワンマン経営に陥っていても、そこから脱却できる会社とできない会社があります。
その違いはどこにあるのでしょうか。
自分に原因があると気付けるかどうか
最も重要なのは、経営者が「問題の原因は自分にある」と気付くことです。
そして、「自分が変わる」という覚悟を持てるかどうかが分かれ道となります。
現代的ワンマン経営の会社は、静かな組織になっているので、経営者は「うちの会社は大きな問題もないし、うまくいっている」と錯覚しがちです。
そのため、ワンマン経営に陥っていることに気付きにくい傾向があります。
気付きのサインとしては以下のようなものがあります。
- 業績が伸び悩む
- 社内トラブルが頻発する
- 離職が増える
- 自分が忙しくて手一杯になる
- 現場仕事に振り回される
このような問題が起こったときに、外部環境のせいにするのではなく「自分が成長しなければならない」と考えられるかどうかが、ワンマン経営から脱却する鍵です。
時間をかけて社員との関係性を再構築できるかどうか
会議のあり方を見直し、社員との対話を増やし、幹部を巻き込んで時間をかけて育成していくことが重要です。
「今までは決めたことを伝えていたが、これからは会議で一緒に考えるチームになりたい」「会社にもっと主体的に関わってほしい」と宣言し、方針を示すことで少しずつ変化が生まれます。
社員との関係性を再構築するには時間がかかりますが、変わろうとする意思と覚悟がある会社は、少しずつでも変わっていきます。
一方で、「制度を整えれば大丈夫」「社員が変わってくれれば良い」と考えている会社は、結局、社長自らが変わる必要性を認識していません。
社長自身が変わり、時間をかけてコミュニケーションを取り続けない限りは、どんな制度を導入しても形骸化し、元のワンマン経営に戻ってしまうのです。
脱・ワンマン経営への第一歩!社員の自律性を育てる組織改革の流れを3ステップでご紹介
実際にワンマン経営から脱却するための改革の流れを、3つのステップに分けてご紹介します。
ステップ1:方針を決めて伝える
脱・ワンマン経営への第一歩は、社長が自ら方針を明確に伝えることです。
「これからは社員参加型の経営にしていく」と宣言することで、幹部や社員が動きやすくなります。
方針が明確になることで、今後の行動の指針ができるからです。
ここで重要なのは、過去を否定するのではなく「これまでは自分が引っ張ってきたが、これからは協力して進めたい」と伝えることです。
ステップ2:社員の本音を「見える化」する
次に必要なのは、社員の本音を見える化する仕組みを作ることです。
ヤマチユナイテッドでは、以下のような制度を導入、活用しています。
- ES調査(従業員満足度調査)
- 自己申告書の活用
- 個別面談・対話の機会
- 匿名アンケートの実施 など
これらを通じてコミュニケーションの土台を作り、普段は言えない思いや課題を引き出していきます。
「問題はない」と思っていた会社でも、現状を正確に把握することで、隠れていたさまざまな思いが明らかになるでしょう。
今まで不満が表面化していなかったとしても、それが本当に「存在しない」のではなく、「言えていなかっただけ」という場合も多いのです。
社員の主体性を育てるには本音を言える環境作りが欠かせません。
こちらのコラムもあわせてぜひご参考ください。
「本音を言わない部下」の本当の理由は?会社が強くなるには聞く器が重要
ヤマチユナイテッドでは、今回ご紹介した「従業員満足度(ES)調査票」と「自己申告書」のフォーマットを無料配布中です。
以下のリンク先からダウンロードしてご活用ください。
"記名式"で実施する「社員満足度(ES)調査表」フォーマット
ステップ3:「任せる準備」として仕組みや型を整える
仕事を任せるには、社員が安心して判断・行動できる環境が必要です。
具体的には、以下のような仕組みを整えていきます。
- 管理会計を整備して公開する
- 数字の見方を学ぶ研修・教育を行い、経営の考え方を共有する
- 計画作りに社員を参加させ、裁量範囲を事業計画で明確に示す
- 予算を付与し、判断や実行の権限を委ねる
会議を「決定事項の伝達」から「一緒に考える場」へと変えることで、幹部が主体的に関わる土壌ができます。
「一緒に経営してほしい」という期待を伝え、経営数字や判断軸を共有するのです。
また、裁量の範囲が明確になれば、社員は安心して挑戦できます。
こうした仕組みにより「自分たちの業績だ」という意識が芽生え、主体的に動けるようになります。
さらに、幹部層の育成も重要です。
社長が結論を先に出すのではなく「考えさせる」→「フィードバックする」というキャッチボールを繰り返すことで、判断力が磨かれます。
時間はかかりますが、これが中間層を育てる近道です。
このような仕組みやベースの型を整えることで、準備を整えた上で業務を任せるという環境を作ります。
これらのステップは、ヤマチユナイテッドで開講している研修塾「連邦・多角化経営実践塾」の初回講義でも、経営者の皆さまにお伝えしている内容です。
仕組みを整えるのは1〜2年で可能ですが、文化として根付かせるには3〜5年程度はかかります。
抵抗が出ても、方針をぶらさず続けることが大切です。
社長が忙しさから解放され、幹部が主体的に動き、相談に応じる程度で経営が回るようになれば、一つの壁を乗り越えたといえるでしょう。
ただし成長に終わりはなく、改善は継続的に必要です。
ワンマン経営の末路を避けるには、社長の覚悟と組織改革が必要
「ワンマン社長についていけない」と社員が感じるのは、厳しく叱られるからではありません。
優しく見えても意思決定が一方通行であれば、社員はやがて諦め、静かに指示待ちの組織になっていきます。
その先にあるのは、社長の孤立や疲弊、そして組織の成長停滞、社員の離職というワンマン経営の末路です。
ワンマン経営から脱却できる会社は、社長が「自分が変わる」という覚悟を持ち、社員と一緒に組織をつくり直そうとする会社です。
社員の本音を引き出し、幹部を育て、粘り強く取り組むことで、初めて自律的に動く組織へと変わることができます。
変化には時間がかかることを理解し、粘り強く取り組み続けることが成功の鍵となります。
社員がついていけないと感じてしまう前に、今から組織改革に着手することをおすすめします。
ヤマチユナイテッドでは、社員の本音を見える化する仕組みとして「従業員満足度(ES)調査」や「自己申告書」制度を導入、活用しています。
以下のリンク先からフォーマットをダウンロードして、ぜひご活用ください。
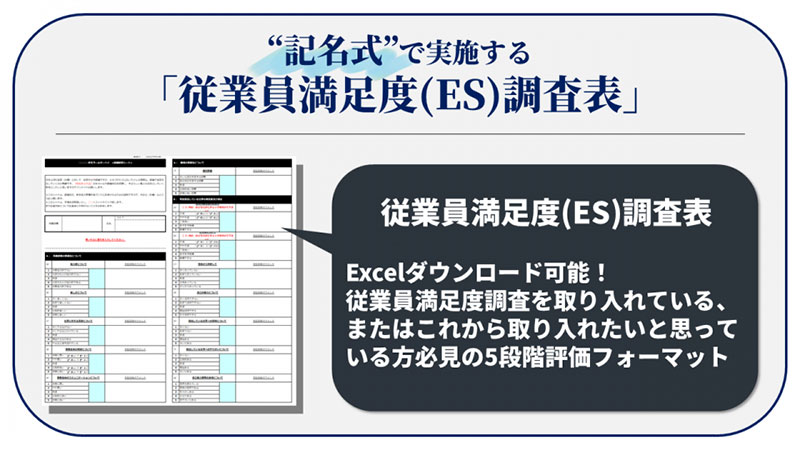
"記名式"で実施する「社員満足度(ES)調査表」フォーマット
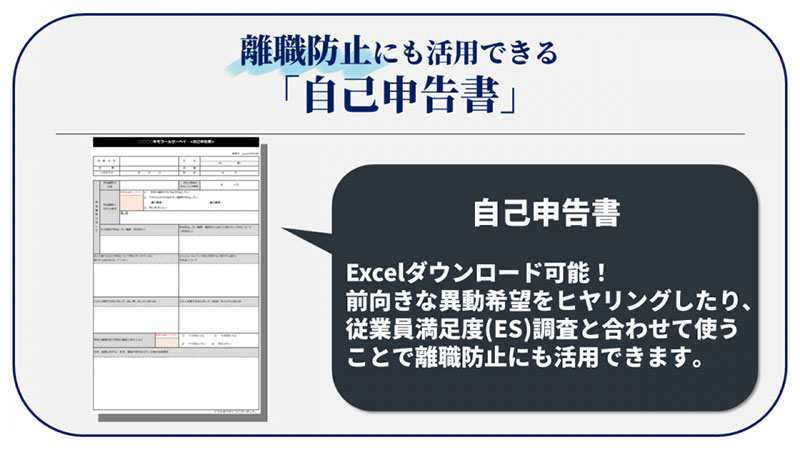
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員
石崎 貴秀
1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。
連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。
入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。

