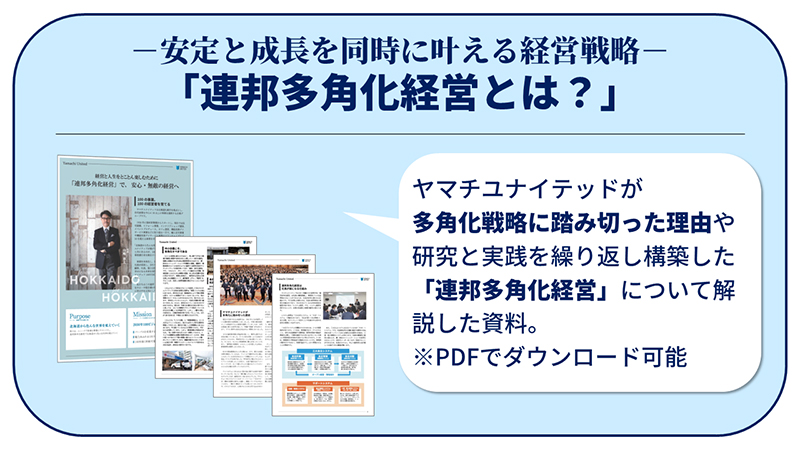市場縮⼩しても⽣き残るための経営戦略とは?ヤマチの事例をご紹介
業績管理・経営計画


こんにちは。ヤマチユナイテッドの石崎です。
日本社会は今、少子高齢化や人口減少に加え、技術革新や消費者の価値観やニーズの多様化など、社会の大きな変化に直面しています。
こうした社会の動きは、さまざまな業界において市場構造を根本から変容させつつあります
「今は何とかなっているけれど、将来に向けた展望に不安がある」
そんな思いを抱えている経営者の方も少なくないのではないでしょうか。
実際、これまで安定していた市場が、急激に縮小していくケースも増えています。
「社会が大きく変化していく中で、企業としてどのように対応していくべきか?」
「市場開拓を進めるべきか?」「新サービスを出すべきか?」と、進むべき方向に悩む経営者の声も多く聞かれます。
そこで今回は、市場縮小が進む時代でも生き残り、さらには成長を実現するための経営戦略について、ヤマチユナイテッドの実例を交えてご紹介します。
目次
- 市場縮小とは?現状から確認
- 衰退・縮小していく市場で生き残るには?ヤマチが考える成功する経営戦略
- 変化の時代における市場縮小の対策は?ヤマチの戦略事例をご紹介
- 市場縮小に負けない多角化戦略で持続的成長を実現
市場縮小とは?現状から確認
まずは、市場縮小が起こる背景や、その影響を受けている業界について見ていきましょう。
市場縮小の主な要因
市場縮小の最大の要因は、やはり人口減少と少子高齢化です。
消費者の数そのものが減っていく中では、どんなに頑張っても、市場全体のパイが小さくなっていくことは避けられません。
人口減少と少子高齢化の影響を受けない業界は、ほとんど存在しないと言っても過言ではないでしょう。
さらに近年では、技術革新によって従来の商品やサービスが別の手段に置き換えられるケースも増えています。
例えば、フィルムカメラはデジタルカメラやスマートフォンへと変化し、固定電話は携帯電話やスマートフォンに取って代わられました。
こうした変化のスピードは非常に速く、従来のビジネスモデルの根本が変わってしまうことも珍しくありません。
さらに見逃せないのが、消費者の価値観やニーズの変容です。
- モノ消費よりもコト消費への移行
- 所有から利用への意識変化
- 環境配慮や社会貢献を重視する価値観の浸透 など
こうした傾向により、従来のマーケティング手法や商品・サービスの提供方法では、響かなくなっているケースが多数見られます。
これらの変化は相互に作用し合い、市場縮小を加速させる要因となっています。
市場縮小の影響を受けている業界
実際に市場縮小の影響を受けている業界としては、以下のような分野があります。
<人口動態の変化による影響>
- 教育業界:子どもの絶対数の減少により、学習塾や教材市場が縮小
- 着物・呉服業界:着用世代の高齢化、文化の変化による需要減
<技術革新による影響>
- 新聞・印刷業界:紙媒体からデジタルメディアへの移行
- CD・DVDレンタル業界:配信サービスの普及により店舗型ビジネスが大幅縮小
- フィルム・現像業界:デジタルカメラやスマートフォンへの代替
<消費者価値観・ニーズの変化>
- 葬儀・ブライダル業界:簡素化・合理化を求めるニーズの拡大
- パチンコ業界:娯楽の多様化や健全志向の浸透
このように、挙げればキリがないほど多くの業界が影響を受けています。
ヤマチユナイテッドグループでいえば、住宅事業も縮小市場の一つです。
住宅を建てる世帯数が減少しているため、戸建て住宅、マンションともに着工数は年々減っています。
多くの業界が市場縮小の影響を受けている状況の中で、「このまま続けていても、いずれ立ち行かなくなる(=じり貧になる)のは明らかだ」という危機感を抱く経営者が増えているのも、無理のないことかもしれません。
衰退・縮小していく市場で生き残るには?ヤマチが考える成功する経営戦略

市場縮小という逆風の中で企業が取るべき重要な戦略は、「縮小していく市場の中で競争する」のではなく、事業の「構造」そのものを変えることです。
ヤマチユナイテッドが長年にわたり実践してきた戦略を基に、市場縮小への具体的なアプローチをご紹介します。
市場縮小に対応する3つの選択肢
衰退・縮小していく市場で企業が生き残るための選択肢は、大きく3つあると考えます。
選択肢①:耐える・残存者利益を狙う
資本力や体力がある企業であれば、競合他社の撤退を待ち、残存者利益を狙うという戦略があります。
市場が縮小しても競合が減るため、その中で勝ち残れれば、一定の利益は確保できます。
選択肢②:既存事業の見直し・改善
市場全体は縮小傾向にあっても、自社のシェアがまだ小さいのであれば、既存事業の中でも取り組み次第では、成長の余地が残されている可能性があります。
DX化、省力化、省人化による業務効率の向上を進めながら、ビジネスモデルをブラッシュアップする。
商品開発で新しい価値を生み出したり、提供方法を見直したり、販売エリアの拡大、新たな販路を変えるといった自助努力による既存事業の改善が必要です。
選択肢③:新規事業による多角化
既存事業の見直し・改善だけでは低成長・低収益から脱することができない場合、新規事業を模索するステップに進みます。
多角化戦略には、以下のような型があります。
- 水平型:同じ業界で事業の幅を広げる
- 垂直型:バリューチェーンの川上・川下に展開する
- 集中型:既存ノウハウを活用して異分野に進出する
- コングロマリット型:既存事業と無関係な分野へ展開する
自社の強みや市場環境を踏まえ、どの方向に多角化するかを慎重に選択する必要があるでしょう。
ご紹介した3つの選択肢のうち、特に「③新規事業による多角化」は、既存の事業構造にメスを入れ、構造を変える戦略の入り口となります。
多角化戦略の4つの分類については、「多角化経営とは?多角化戦略のメリットと成功へ導くポイント」でも解説しています。
「構造」を変えることで変化の波をチャンスに変える
ここで重要なのは、「市場の縮小は企業の努力では止められないが『構造を変える』ことはできる」という考え方です。
構造を変えるアプローチは、大きく分けて以下の3つがあります。
①収益構造を変える
一つの事業における収益モデル(何をどのように収益化するか)を見直します。
例えば、このような方法があります。
- 収益の割合を変える
- 新しい収益源を加える
- ストック型ビジネスの導入などにより、収入を増やして安定させる
②事業構造を変える
会社・グループの中で事業の種類を複数持つことで、単一事業への依存から脱却します。
事業の多様化により軸足をいくつも持つことで、リスクの分散が可能になります。
③組織構造を変える
事業構造が多角化すると、それに伴って組織構造も変える必要があります。
しかし、組織構造の変更は極めて重要である一方で、実行の難易度も高い取り組みです。
組織構造変更の重要性と柔軟性のある組織作り
単一市場への依存から脱却し、複数の収益源と柔軟な組織構造を持つことで、変化の波をチャンスに変える。
これが、ヤマチユナイテッドが実践してきた「多角化戦略」の核心です。
ただし、単に事業を増やすだけでは、成功にはつながりません。
多角化を成功に導くには、それを支える柔軟な組織体制の構築が不可欠です。
なぜ柔軟な組織が必要なのか?
一般的に、多角化経営において事業ごとに独立した組織経営を行うと、事業ごとの独立性が強まりすぎて、横の連携がなくなってしまうことが多いです。
責任者を置いて任せるだけでは、その責任者の能力に依存してしまい、組織や事業が育たないというジレンマに陥ります。
さらに、「自部署さえ良ければ良い」という意識になりがちで、本来は同じ資本の仲間のはずなのに、他部署への協力意識が失われてしまうことも。
これでは、硬直化した柔軟性のない組織になってしまいます。
柔軟性のある組織づくりに必要な仕組み
柔軟性のある組織をつくるために、以下のような仕組みが必要です。
- 情報共有システムの整備:各事業の状況や課題をグループ全体で把握できる仕組みを整える
- 人事異動をしやすい制度:適材適所の人材配置を機動的に実現できる制度を設ける
- グループ全体の業績を重視する運営:各事業の最適化(局所最適)だけではなく、グループ全体の成果(全体最適)を追求し、組織全体に浸透させる
例えば、既存事業A・B・Cから、それぞれ2〜3人ずつ人材を出してもらって、新規事業を始めるとします。
このとき、硬直化した組織では、「人材が抜けると自部署の業務に支障が出る」という理由で反対されがちです。
しかし、グループ全体の成功を見据える組織なら、積極的に新規事業のスタートに協力し、人材を提供し合える風土が育っています。
それぞれの事業で「人が抜けた分をカバーするぞ!」という認識を持てるかどうかが重要です。
また、一部の事業の業績が悪くなってしまったときには、経営資源(人材)を他の事業にスムーズに再配置できる体制を整えておけば、リスクヘッジにもつながります。
多角化を成功させる柔軟な経営体制を実現するためには、まずオーナー社長自身が考え方を改め、役員・幹部に方針を共有し、共通認識を持つ場を作ることが大切です。
これが、ヤマチユナイテッドの「連邦・多角化経営」の考え方です。
事業拡大や多角化戦略については、「事業拡大のメリットとは?拡大方法・リスク・成功事例を知って成功へ」もぜひあわせてご覧ください。
多角化による事業拡大の具体的な方法やリスク対策について詳しく解説しています。
さらに、連邦・多⾓化経営についてもっと詳しく知りたい方へ、資料をプレゼントいたします。
以下のリンク先からダウンロードしてご活用ください。
-安定と成長を同時に叶える経営戦略-「連邦多角化経営とは?」
変化の時代における市場縮小の対策は?ヤマチの戦略事例をご紹介
変化の時代における市場縮小の対策について、ヤマチの戦略事例とともにご紹介します。
ヤマチの創業と建材卸売業の課題
ヤマチユナイテッドの創業事業は、建材の卸売業です。
1958年にスタートした建材商社として、1980年代の半ばまで建材卸売事業を中心に展開してきました。
しかし、建材卸売事業には構造的な課題がありました。
<建材卸売業の課題>
- 薄利多売のビジネスモデル:売上は上がるが、利益率が低い
- 差別化が困難な商材:他社でも同じ商材を扱うため、価格競争になりやすい
- 高い回収リスク:高額の売掛金で支払いサイトが長く、回収リスクが高い
- 中間業者としての立場:メーカー・商社・問屋・販売店・工務店の図式で中間マージンを取る構造
建材卸売業は売上規模が大きいものの、当時は売掛金の回収に半年ほどかかるのが一般的で、手形での代金回収が主流でした。
売掛金が積み上がる中でお客さまが倒産してしまうと、1億円を超える不良債権が発生してしまう。
このようなリスクを常に抱えていたのです。
さらに流通業界では、「中間業者はいらないのでは?」という風潮も強まっており、メーカーが直接販売を始める動きも出てきていました。
ヤマチでも当然、このような構造的な課題を抱えた建材卸売業に対して「このままではきつい」という危機感を持っていました。
低成長・低収益の事業構造から脱却するには、利益率の高いビジネスモデルを組み合わせる必要があったのです。
そこで、新規事業を段階的に追加しながら、収益構造と事業構造を変革。
同時に組織構造も整理することで、多角化してもバラバラにならない、一体感のある経営体制を構築してきました。
収益構造を変える取り組み
まず取り組んだのが、既存の建材事業における収益構造の改善です。
ヤマチユナイテッドでは、以下の取り組みにより、建材事業の収益構造を改善することができました。
輸入建材の取り扱い開始
ヤマチでは創業してからしばらくは国産メーカーの建材のみを扱っていましたが、海外に建材を探しに行き、アメリカやヨーロッパの建材を仕入れるようになりました。
当時、海外の建材は日本では他社が扱っていないものが多く、価格決定権を持つことができました。
「問屋的な立場」から「メーカー的な立場」になり、価格競争から一歩抜きんでることができたのです。
OEM商品の開発
輸入建材のノウハウを生かして、自社オリジナルのOEM商品を開発し、粗利率の高い商品を作りました。
事業構造を変える多角化戦略
続いて、「収益構造の改善だけでは根本的な解決にならない」と判断し、事業構造そのものを変える多角化戦略に踏み切りました。
単一事業への依存から脱却し、複数の収益源を持つことでリスク分散を図る戦略です。
住宅事業「ジョンソンホームズ」の立ち上げ
収益構造の改善と並行して取り組んだのが、住宅事業「ジョンソンホームズ」の立ち上げです。
これまでお客さまであった建築会社と同じ業種、つまり今まで卸していた建材を使った周辺事業を始めました。
住宅事業への参入は大きなメリットがありました。
住宅業界は下流に行けば行くほど利益率が上がる構造であるため、薄利多売から脱却できたこと。
また、現金回収となるため回収リスクがなくなり、キャッシュフローが大幅に改善されました。
建材事業で培ったノウハウを生かすことができるため、ゼロからの事業立ち上げよりもリスクを抑えて新規事業を立ち上げることができたのです。
事業の掛け合わせによる成長戦略
フランチャイズパッケージの開発と全国展開
建材事業と住宅事業を掛け合わせて、住宅のFC(フランチャイズ)パッケージを開発しました。
- 建材卸流通業として培った全国納品ノウハウ
- 住宅事業で蓄積した設計ノウハウ
- これまで培った営業ノウハウ
これらを組み合わせることで、自社オリジナルのブランドと独自ルートの輸入建材を使った輸入住宅パッケージを開発し、FCで全国展開したのです。
これは、住宅の受注が増えれば、建材の受注も自動的に増えるという好循環を生み出しました。
また、住宅は「フロー商材(販売が一回きりの売り切り型ビジネス)」ですが、FC自体は「ストック商材(ロイヤリティ収入)」という側面を持っています。
この組み合わせも、収益の安定化に大きく寄与しています。
フランチャイズ活用から自社ブランド化
ヤマチでは、多角化のプロセスとして「FC活用→自社ブランド化→横展開」という流れもあります。
まず大手FCに加盟してノウハウを学び、成功事例を作ったあと、自社でブランド化して展開するという手法です。
イベント事業「アンカー」の例
例えば、イベントの企画運営や関連機材のレンタルを主な業務とする「アンカー」は、最初は大手レンタルサービス会社のFC店として参入しました。
ビデオカメラや旅行カバンの貸し出しからスタートし、運動会用品やイベント用品へと扱う商品の領域を拡大。
やがて自社で道具を揃え、イベント資機材のレンタルに特化して独自路線を歩むようになりました。
コロナ禍でイベント事業が大きな打撃を受けた際も、リモート会議などのニーズを捉えてウェブスタジオ事業を開始。
変化に即応した事業転換で、ピンチをチャンスに変えたのです。
組織構造の変革による連邦・多角化経営の実践
多角化を進める中で最も重要だったのが、組織構造の変革でした。
事業が増えると、縦割り化が進み、社長が忙しくなる傾向にあります。
問題が起きるたびに直接介入して解決しなければならず、現場仕事に追われて前向きな仕事ができなくなってしまいます。
ヤマチユナイテッドではこれを避けるため、事業に横串を刺す「連邦・多角化経営」を導入しました。
連邦・多角化経営を実現するためには、「理念」「仕組み」「人材」という3つの要素を有機的に結び付けることが不可欠です。
どれか一つが欠けても、多角化した事業を統制することはできません。
①理念の共有
グループ共通のビジョン(パーパス、ミッション、コアバリュー)をしっかりと作り、各社・各事業がこの傘の下で運営するという軸を整備しました。
②仕組みの整備
まず、ホールディングス体制で事業会社を統制管理する物理的な形を整備しました。
次に、グループ本部という組織機能を置いて共通制度・ルールを整備し、新しいことに取り組む際には本部で管理やサポートできる体制を構築。
さらに、事業を横断する会議や委員会を設置し、社内SNSなどのコミュニケーションツールも整備することで、グループ全体の連携を強化しています。
③人材の流動化
人材、仕組み、理念を中心に置き、どんな事業であってもグループ全体として組織的に経営する体制を構築しました。
「経営計画を立て、業績評価をして、利益が出たら配分する」という基本的な事業運営の流れを、オーナー社長ではなく、幹部中心に回せるようにしました。
市場縮小や環境変化に強い、柔軟な経営体制へ
この連邦的な組織構造により、「人・もの・金」の組織資源を柔軟に采配できるようになりました。
業績が落ち込んだり、新規事業が増えたりしても、当たり前のようにカバーし合える。
市場縮小や激しい環境変化にも対応し得る、柔軟性のある組織。
このような組織作りが、多角化戦略を成功に導く鍵となっています。
自社の「人材・仕組み・理念」を中心に置くことで、「戦略の汎用性」を高める。
どんな新規事業を始めても、グループとして組織的に取り組める体制を整えることが重要なのです。
「市場縮小にどう立ち向かうか?」
その問いに対するヒントが詰まった、ヤマチユナイテッドの「連邦・多角化経営」、多角化の実践例をまとめた資料を無料で配布中です。
-安定と成長を同時に叶える経営戦略-「連邦多角化経営とは?」
市場縮小に負けない多角化戦略で持続的成長を実現
市場縮小は、社会の変化に伴う避けられない現象です。
しかし、「構造」を見直すことで環境変化の中でも生き残り、成長していく道があります。
特に重要なのは、以下の3つの構造変革です。
- 収益構造の変革:既存事業の中でも収益モデルを見直し、より高い粗利率を実現する
- 事業構造の変革:単一事業依存から脱却し、複数の収益源を持つ
- 組織構造の変革:多角化に対応できる柔軟性のある組織を構築する
ヤマチユナイテッドは建材卸からスタートし、住宅事業、イベント事業、介護福祉事業へと多角化を進めてきました。
その過程で学んだのは、「事業を増やすだけでなく、それを支える組織構造の変革が不可欠」だということです。
市場縮小の波は止められませんが、それを乗り越える「構造」を作ることはできます。
単一市場依存から脱却し、変化の波をチャンスに変える多角化戦略こそが、中小企業が持続的成長を実現するための勝ち筋と言えるでしょう。
ヤマチユナイテッドの連邦経営、多角化の実践知をまとめた資料を無料で配布中です。
SHARE! この記事を共有する
Authorこの記事の著者

株式会社ヤマチマネジメント|取締役 |グループ執行役員
石崎 貴秀
1996年入社。営業課から国際課を経て、総務部チームリーダーへ。その後グループ経営推進会議事務局にて経験を積み、2009年(株)ヤマチマネジメントを設立、移籍。グループ管理本部の統括マネージャーとして采配を振るう。2017年(株)ヤマチマネジメント取締役就任。
連邦・多角化経営実践塾」の開塾にも携わり、2014年以降、第1期~現在までシステム経営のメイン講師として活躍。
入塾した企業約70社にシステム経営を指導してきた。現在はシステム経営のコンサルティングも担当。